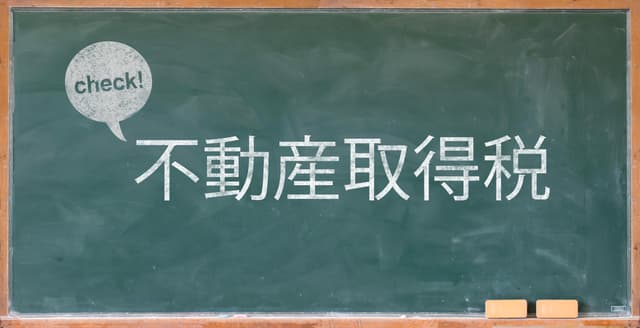工業専用地域とは|工業地域との違いや店舗は建てられるものなのかを詳しく解説

建物を建てることが目的である市街化区域では、用途地域を定めることが決まりとなっています。購入対象の建物がどの用途地域に属していて、どのような規制を受けるかを知ることは不動産の営業マンにとって不可欠です。
建物の種類によって規制を受けるばかりでなく、建蔽率や容積率なども細かく決められています。買主様から質問されることも多いため、正確に理解する必要があります。
今回は、住宅や商業施設の規制が厳しい「工業専用地域」に的を絞って解説していきます。
Table of Contents
工業専用地域とは
工業専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域の1つです。コンビナートや工業団地の建築を想定したエリアとなります。したがって、住宅を建てて住むことができません。
工業に専念するための地域であるため、工場でない建物は住宅以外にも立地が制限されています。具体的には、住宅や老人ホーム、学校や病院も建てることができません。
逆に、工場であればどんな建物でも建てることができます。
その他の用途地域については以下の表を参考にしてください。
| 用途地域の種類 | 説明 |
| ➀第一種低層住居専用地域 | 低層住宅(高さ10~12m)における良環境を保つための地域。
住居を兼ねた50㎡までの店舗や事務所、小規模程度の公共施設及び小中学校や診療所などを建てられる。 |
| ②第二種低層住居専用地域 | 低層住宅を主とした良環境を保つための地域。
150㎡までの店舗(一定条件あり)や小中学校などを建てられる。 |
| ③第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅における良環境を保つための地域。
500㎡までの店舗(一定条件あり)や、中規模程度の公共施設及び病院や大学などを建てられる。 |
| ④第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅を主とした良環境を保つための地域。
1,500㎡までの店舗や事務所など(一定条件あり)や、病院及び大学などを建てられる。 |
| ⑤第一種住居地域 | 住居における良環境を保つための地域。
3,000㎡までの店舗・ホテル・事務所など(一定条件あり)や、環境に影響を及ぼさない非常に小規模な工場を建てられる。 |
| ⑥第二種住居地域 | 住居を主とした良環境を保つための地域。
10,000㎡までの店舗・ホテル・事務所に加えてパチンコ店やカラオケボックスなど(一定条件あり)や、環境に影響を及ぼさない非常に小規模な工場を建てられる。 |
| ⑦田園住居地域 | 農地及び農業関連施設と低層住宅との調和を保つための地域。
500㎡までの農産物の販売を行う店舗や、ビニールハウス・農業用倉庫といった農業に関連した施設を建てられる。 |
| ⑧準住居地域 | 道路及び自動車関連施設などと住居との調和を保つための地域。
10,000㎡までの店舗・ホテル・事務所・パチンコ店・カラオケボックスなどに加えて小規模程度の映画館や倉庫及び車庫(一定条件あり)、そして環境に影響を及ぼさない非常に小規模な工場を建てられる。 |
| ⑨近隣商業地域 | 近隣住民における日用品を対象とした店舗の利便促進を図った地域。
面積規制なし。商業施設のほとんどを建てることができ、それ以外にも住居や小規模程度の工場を建てられる。 |
| ⑩商業地域 | 商業全般における利便促進を図った地域。
面積規制なし。商業施設のほとんどを建てることができ、それ以外にも住居や小規模程度の工場を建てることができます。また、指定容積率の限度も高いため高層ビルも建てられる。 |
| ⑪準工業地域 | 軽工業など環境悪化を招く恐れがない工場の利便促進を図った地域。
工場以外にも住居や店舗を建てることができる。 |
| ⑫工業地域 | 主として工業全般における利便促進を図った地域。
全ての種類の工場以外にも住居や店舗を建てることができる。ただしホテルや病院・学校などは建てることができない。 |
| ⑬工業専用地域 | 工業全般における利便促進を図った地域。
全ての種類の工場を建てることができる。。ただし、住居や店舗・ホテル・福祉施設・病院・学校などは建てることができない。住居を建てることができない唯一の用途地域。 |
工業専用地域で建てられる建物一覧
工業専用地域には、建てられる建物と建てられない建物があります。具体的にどのような建物が建てられるのか、以下にまとめました。
工業専用地域で建てられる建物
| 建物名 |
| 事務所等 |
| 運動施設(特記事項がなければOK) |
| 巡査派出所、公衆電話、郵便局等 |
| 神社、寺院、教会等 |
| 公衆浴場、診療所、保育所等 |
| 老人福祉センター、児童厚生施設等 |
| 自動車教習所 |
| 公園内の公衆便所、休憩所 |
| 自治体の支部 |
| 電気、ガス、水道、鉄道等の事業の為の施設 |
| 車庫、倉庫、畜舎等 |
| カラオケボックス |
| 自動車車庫(2階以下で床面積の合計が300平方メートル以下) |
| 営業用倉庫(3階以上又は床面積の合計が300平方メートルを超えるもの) |
| 工場 |
| ガソリンスタンド |
| 火薬、石油、ガス等の危険物の貯蔵施設 |
| その他、特定行政庁が許可したもの |
工業専用地域で建てられない建物
| 建物名 |
| 住宅、共同住宅、宿舎等 |
| 兼用住宅 |
| 物品販売店舗、飲食店 |
| ホテル、旅館 |
| マージャン店、パチンコ店等 |
| 劇場、映画館等 |
| ボウリング場、スケート場、スキー場等 |
| 幼稚園、小・中学校、高等学校 |
| 大学、専門学校等 |
| 博物館、美術館等 |
| 病院 |
| 老人ホーム、障碍者福祉施設等 |
| キャバレー、ナイトクラブ |
| 風俗店(ソープランド) |
工業地域と工業専用地域の違い
13個ある用途地域の中で、工業専用地域と似た名前で「工業地域」という地域があります。名前は似ていますが、工場以外の建築物の規制内容に違いが見られます。
それぞれの用途地域の違いをまとめました。
| 建物名 | 工業地域 | 工業専用地域 |
| 住宅、共同住宅、下宿 | できる | できない |
| 兼用住宅の内、店舗の規模が一定以下の建物 | できる | できない |
| 図書館 | できる | できない |
| 老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム等 | できる | できない |
| 床面積の合計が150平方メートル以内の店舗、飲食店 | できる | 物品販売店、飲食店は建築できない |
| 床面積の合計が500平方メートル以内の店舗、飲食店 | できる | 物品販売店、飲食店は建築できない |
| 上記以外の物品販売業を営む店舗 | 10,000平方メートル以下の場合に建築できる | できない |
| ボウリング場、スケート場等 | できる | できない |
| 麻雀店、パチンコ店等 | 10,000平方メートル以下の場合に建築できる | できない |
最も大きな違いは、工業専用地域では一切建築できない住宅や店舗の建築が、工業地域では建築できる点です。
店舗を作りたい場合は工業専用地域ではなく、工業地域であれば建築可能という事です。店舗の床面積によって工業地域でも規制の対象になることがあるため、市役所の建築指導課などで確認するようにしてください。
工業専用地域で受ける制限
工業専用地域で受ける制限は、建物の種類だけではありません。建築する建物について、建蔽率や容積率、斜線制限など細かい規制が設けられています。
具体的な規制内容をまとめましたので、確認してください。
建蔽率
工業専用地域の建蔽率は、30%、40%、50%、60%のいずれかが都市計画で定められています。建築物は、決められた建蔽率を超えてはいけません。
ただし、一定の条件で建蔽率が緩和されることがあります。具体的には、特定行政庁が指定する角地にある建築物、防火地域内にある耐火建築物に関しては建蔽率の制限が10%緩和されます。
関連記事:イメージが湧きにくい建ぺい率を具体例も含めてわかりやすく解説
容積率
工業専用地域の容積率は、100%、150%、200%、300%、400%のいずれかが都市計画で定められています。定められた容積率を超えて建築することはできません。
ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、幅員に10分の6をかけた数値と比較して小さいほうの容積率を採用します。
関連記事:「容積率」とは何かわかりやすく解説|調べ方・緩和特例・緩和要件なども紹介
道路斜線制限
道路斜線制限とは、敷地の周囲の道路から発生する斜め線による制限です。工業制限地域においても、この数値を超えて建てることはできません。
制限の内容は、「傾斜勾配」と「適用距離」の2つです。
傾斜勾配とは、敷地と接する道路の反対側の境界線までの距離の1.25倍または1.5倍まで建物の高さが制限されることです。
工業専用地域の傾斜勾配は「1.5」です。
適用距離とは、道路から一定の距離が離れていれば、傾斜勾配を無視して直線的に建物を建築できる長さのことです。建物の容積率によって、以下のように変わってきます。
| 工業専用地域の容積率 | 適用距離 |
| 200%以下 | 20メートル |
| 201%~300% | 25メートル |
| 301%~400% | 30メートル |
| 401%以上 | 35メートル |
隣地斜線制限
工業専用地域は、隣地境界線から発生する斜め線による制限も受けます。
具体的には、31メートルの基準高さから隣地境界線までの距離の2.5倍以下に収まるように建物の高さが制限されます。
その他
防火地域や準防火地域、高度地区に指定されている地域については、各自治体が定めた規制内容にしたがって建物を建てる必要があります。
また、用途地域は「騒音規制法」による制限も受けます。工業専用地域は住宅を建てることができないため規制は厳しくありません。最も規制が厳しい第1種区域から規制が緩い第4種区域がある中で、工業専用地域は第4種区域に指定されています。
第4種区域における規制の定義は、「主として工場等の用途に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある地域」とされています。
具体的な騒音の規制数値は、以下の通りです。
| 区分に対応する規制基準(単位:デシベル) | ||||
| 朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 | |
| AM6:00~AM8:00 | AM8:00~PM7:00 | PM7:00~PM10:00 | PM10:00~AM6:00 | |
| 第4種区域 | 65(60~70) | 70(65~70) | 65(60~70) | 55(55~65) |
なお、自動車による騒音の規制については、工業地域及び工業専用地域においては対象外となっています。
まとめ
今回は、市街化区域で定められる用途地域のうち「工業専用地域」の規制内容を紹介しました。規制を受ける建物、受けない建物を正確に理解して買主様からの疑問を解消することが必要です。
世論を受けて、規制が緩和されたり強化されたりすることもあります。常に最新の情報を仕入れておくようにしましょう。
あわせて読みたい:不動産営業実務マニュアル / 基本