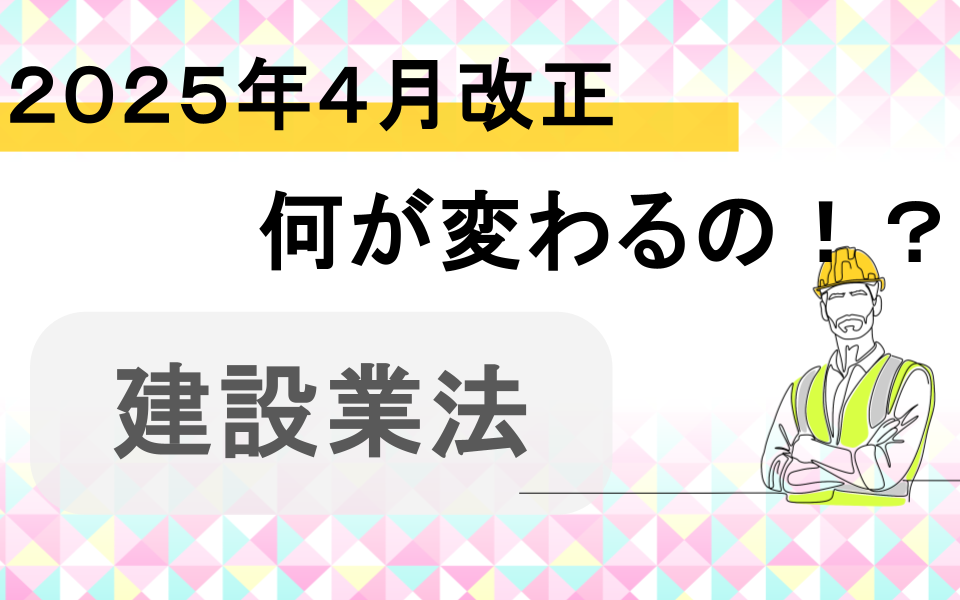建築確認済証がない場合はどうなる?再発行はできるの?重要書類が損失した時の対処法

不動産を売却しようとしたときに、絶対に必要になる書類がいくつかあります。「建築確認済証」もその1つです。ただし、新築や建て替えの時に発行されてから年月が経ってしまって、建築確認済証がない売主様も少なくありません。
その場合は、「建築確認済証」に記載された内容を改めて取得することが必要です。
今回は、「建築確認済証」の重要性と、万が一紛失した場合の対応方法について紹介します。
Table of Contents
建築確認済証がない時の対応方法
通常、建物を新築してから売却を決意するまでは長い時間が経っています。10年以上経っていれば、大切に保管していても紛失してしまうことは十分考えられるでしょう。
しかし、紛失してしまうと絶対に建物を売却できないわけではありません。
自治体の役所で特定の書類を発行することで、「建築確認済証」の代わりにすることができます。
次に紹介する方法のうち、いずれか1つの書類を取得すれば代用可能です。
建築計画概要書を取得する

画像引用:門真市|建築計画概要書について
「建築計画概要書」は、建築確認の際に「建築確認申請書」と同時に自治体に提出する書類のことです。建築確認の完了後は一般公開されることから、建築確認が済んだ建物の概要を調べる際に利用されます。
「建築計画概要書」には、建築に係る各検査の履歴が載っているほか、建築確認番号と検査済番号を見ることができます。
市役所の建築指導課で500円前後で発行できるほか、閲覧のみであれば無料の自治体もあります。
台帳記載事項証明書を取得する
台帳記載事項証明書とは、「建築確認済証」と「検査済証」のデータが載っている書類のことです。「建築確認通知書」を紛失した場合に、代わりの書類として利用できます。
ただし、作成された当時の記載方法によっては必要項目が不明になっていることがあるほか、台帳そのものがない可能性もあります。
詳細は自治体ごとに問い合わせが必要ですが、ない場合は別の書類を発行しなければいけません。
なお、台帳記載事項証明書を取得するためには以下が必要です。
- 申請者の氏名
- 建築した人の本人確認書類
- 建築当時の地名地番(現在の地名地番でない点に注意)
- 建築した人の氏名・建築確認番号・建築確認年月日・階層
3については図書館に設置されているブルーマップで確認するか、法務局に問い合わせれば教えてくれます。
4については、各自治体に保管された建築確認台帳か、登記事項証明書の記載を確認する手続きが別途必要です。
あわせて読みたい:台帳記載事項証明書とは|建築確認済証を失くした時の手続き方法
確認済証・検査済証を紛失した場合に発行される
台帳記載事項証明書は、あくまで「建築確認済証」または「検査済証」を紛失した場合に発行できる書類です。
また、「建築確認済証」や「検査済証」が発行された時の番号などが記載されるため、そもそも建築確認や完了検査がされている必要があります。仮に完了検査が行われていない場合などは、台帳記載事項証明書は作成されていません。
建築確認済証とは|再発行できない大切な証明書

建築確認とは、新築や建て替えの計画の段階で、建築基準法の規定通りに設計されているかを確認する手続きのことです。
そして、建築確認が済んでいることを証明するために発行されるのが「建築確認済証」です。
物件の引き渡しの際に、建築会社から買主様に渡されるのが一般的です。
別の呼び方として「建築確認通知書」や、単に「確認済証」と呼ばれることもあります。
建築確認をクリアした証明として発行される
建築確認で法令上問題ないことを確認した後、自治体に必要書類を提出して建築確認申請を行います。
申請が受理された場合に、自治体から発行されるものが「建築確認済証」です。
「建築確認済証」がない状態では、新築したり建て替えたりすることはできません。勝手に建物を建てることは建築基準法違反になります。
不動産を売却する時に必要
「建築確認済証」は、買主様に渡された後、買主様でなくさないように大切に保管しなければいけません。
将来的に不動産を売却して引き渡す時に、必ず提出する書類だからです。
紛失すると、「建築確認済証」に記載された内容を確認できず、法的に許可された建築物であると証明できません。そのため、不動産を売却することができなくなります。
不動産の売却で必要な書類一覧
不動産を売却する時には、「建築確認済証」以外にもさまざまな書類が必要になります。
売却時に必要な書類は以下の通りです。
- 身分証明書・住民票・実印・印鑑証明
- 登記済み権利書(登記識別情報でも可)
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産税評価証明書
- 土地測量図
- 建築確認済証
- 検査済証
- 建築設計図書・工事記録書
その他、「購入した時の重要事項証明書・売買契約書」も必要になる場合があります。
紛失しても再発行できない
「建築確認済証」を大切に保管しなければいけない理由は、再発行ができないからです。紛失しても代わりの書類で代用はできるものの、「建築確認済証」として発行することはできません。
紛失した場合は、自治体の役所に出向いて台帳記載事項証明書等の書類を発行することで「建築確認済証」の代わりになります。とはいっても手間と費用がかかるため、紛失せずに保管しておくことがベストです。
検査済証との違い
「建築確認済証」と混同しやすい書類に「検査済証」があります。
「検査済証」とは、建築確認・中間検査・完了検査の全てが完了したことを証明する書類です。建物が完成した段階で完了検査が行われ、法令に適合することが確認されることで発行されます。
建築確認のみを証明する「建築確認済証」と異なり、証明する項目が3つあるのが特徴です。
また、「建築確認済証」がないと建物を建てられないのに対し、「検査済証」が無いと建物を使用できない点でも違いがあります。
あわせて読みたい:検査済証とは|確認済証・中間検査合格証との違いを見本つきで解説
確認済証は工事が適法かを判断するものではない
「建築確認済証」は、あくまで「計画段階での適法性」を証明する書類で、実際に行われた工事が適法かどうかを判断できる書類ではありません。
実際の工事が適法かどうかを証明する役割は、中間検査と完了検査の結果を示す「検査済証」が担うことになります。
計画段階と実際の工事の両方の適法性を示すために、不動産の売却時は「建築確認済証」と「検査済証」の両方の提出が必要なのです。
建築確認申請書との違い
もう1つ、混同しやすい書類に「建築確認申請書」があります。
「建築確認申請書」とは、自治体に建築確認を申請するために提出する書類のことです。「建築確認申請書」と「建築計画概要書」を同時に提出し、自治体が指定する検査機関に提出します。
検査機関での建築確認が完了した後、自治体から発行されるものが建築確認済証です。
確認の申請を行う書類が「建築確認申請書」、確認が完了したことを証明する書類が「建築確認済証」という違いになります。
建築確認済証の発行方法
「建築確認済証」は、建築確認の申請後に問題が無ければ約3週間で建築主事(建築確認を行うための公務員)から発行されます。
工事の着工から建物の完成までは建築会社で保管され、建物の引き渡しのタイミングで買主様に渡されるのが一般的です。
再発行できない重要書類のため、確実に買主様の手元に渡っていることを確認するのが大切です。
まとめ
今回は、「建築確認済証」の重要性と紛失した場合の対応方法について紹介しました。
■建築確認済証がない時の対応方法
- 建築計画概要書を取得する
- 台帳記載事項証明書を取得する
「検査済証」と共に再発行できない重要書類ですが、年月が経ってしまって見つからないこともあり得ます。問い合わせがあった際にお客様を安心させられるよう、対応方法を理解しておきましょう。
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事
- 不動産業務効率化
- 不動産DXサービス特集
- 不動産DX導入インタビュー
- 不動産業界DX
- 不動産営業とは?仕事内容と成約率アップのポイントを解説
- 賃貸管理会社はどこが良い?管理戸数ランキングと選び方を紹介