差し押さえとは?財産の強制回収に関する仕組みをわかりやすく解説

債務者が債務不履行を起こした場合に、債権者が債権を回収するために行う手続きが「差し押さえ」です。差し押さえられた物件は競売にかけられますが、債権者と任意売買の話がつけば競売をやめて売買することも可能です。
今回は初めて「差し押さえ」について学ぶ不動産営業を対象に、制度の概要や売却までの流れを解説します。
差し押さえられた物件を売買する業務に携わることがある方は、差し押さえ~売却までの流れを身につけておきましょう。
Table of Contents
「差し押さえ」のしくみを分かりやすく解説

「差し押さえ」は、借金やローン返済といった債務履行を行わない債務者に対して、債権者が債権回収するための手続きです。
公権力を持つ裁判所・地方公共団体・税務署などが債務者の不動産などの財産を押さえることで、 お金を返さない債務者が所有する財産を勝手に売却しないようにします。
差し押さえの仕組み
差し押さえは強制執行の前段階であり、債務者の財産処分権を制限するための仕組みです。
よって、差し押さえただけでは債権回収はできません。差し押さえた財産を強制執行してはじめて債権が回収できます。つまり、基本的に差し押さえと強制執行は同時に行われます。
強制執行とは、不動産で言えば「競売」のことです。
強制執行される競売手続きでは、不動産競売申立から債権者へ配当がされるまで、概ね半年~1年程度かかります。
債務者としては債務不履行になっている分を一括返済するなど、債権者が認める返済を行って差し押さえを解除してもらわないと、差し押さえられた財産を失うことになるのです。
差し押さえの対象になる財産
具体的には以下の3つの財産が、債務不履行の際に差し押さえ対象になる可能性があります。
債権
債務者が別の第三者に対して持っている債権(特定の行為や給付を請求できる権利)は、差し押さえの対象です。
たとえば金融機関に対する預金債権があげられます。預金残高がある場合、預金者は金融機関に対して残高の払い戻しを請求する債権を持っているため、差し押さえの対象に含まれます。
モノの使用収益を提供する代わりに賃料を受け取る「賃料債権」も同様です。
不動産
住宅ローンの返済不履行などの場合、不動産が差し押さえられると競売にかけられます。
ただし、差し押さえは他の債権者が不動産に抵当権を設定していると抵当権が優先されます。
動産
動産とは現金、骨董品、ブランド品、自動車など「動かすことのできる財産」のことです。動産の所在地を管轄する裁判所に申し立てをすると執行官が現地を訪れ、差し押さえが可能な動産を選別する形で差し押さえが行われます。
差し押さえから競売、売却までの流れ

実際に差し押さえから売却が行われるまでの流れは財産によっても若干異なります。今回は不動産をテーマに、差し押さえから売却までの流れをまとめました。
実際の差し押さえから売却の大まかな流れは以下のとおりです。
- 不動産競売申し立て
- 競売開始決定・差し押さえ
- 現況調査・評価
- 売却基準価額・買取可能価額の決定
- 物件明細書の作成・売却
- 代金納付・配当
債権者が不動産の所在地を管轄する地方裁判所に不動産の競売申し立てを行うことで、手続きが始まります。
裁判所が競売開始を決定して差し押さえの登記が設定されたあとは、不動産の所有者は自由に不動産を処分できません。
裁判所に任命された執行官と評価人によって不動産が評価され、売却基準価額(不動産の標準的な価額)と買受可能価額(買受申出が可能な下限額)が決まります。
裁判所は不動産の権利関係などを記載した物件明細書を作成し、裁判所は売却の日時・場所・方法を定めます。一般的には裁判所における期間入札の方法で売却が行われます。
- 最高価で落札した人(買受人)に対して売却が許可され、買受人は裁判所に物件代金を納付します。代金納付後、債権者に対して配当が行なわれ、債権者はここにきて債権を回収できます。
差し押さえのメリット・デメリット
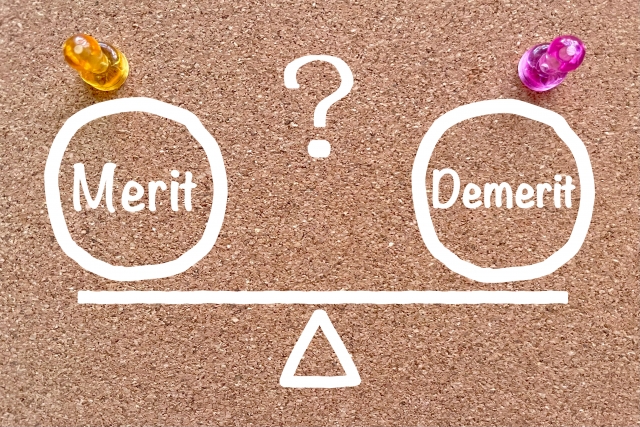
債権回収を行うにあたって債権者の助けとなる強力な効力がある差し押さえですが、メリットばかりではありません。
ここでは差し押さえのメリット・デメリットについて紹介します。
差し押さえのメリット
差し押さえのメリットは以下の2つです。
強制的な取り立てが可能
債務を支払うための原資になる財産(現金、不動産、自動車など)を持っているとしても、債務者が自分から処分して返済に回してくれるとは限りません。
請求しても返済が実現しない場合、差し押さえたうえで強制執行手続きを行うことで、債権者は返済してくれない債務者から債権を取り立てることができます。
強制執行前に債務者が勝手に財産を処分できなくなる
財産を持っている債務者が財産を処分していると、債権を回収できない恐れがあります。
強制執行を行う前には、債務者が財産を処分できないようにしておきましょう。
差し押さえることで債務者が財産を自由に処分できなくなり、強制執行による換価がスムーズに進められます。
差し押さえのデメリット
差し押さえたからといって絶対に債権が回収できるわけではありません。以下のデメリットに注意が必要です。
財産がある債務者にのみ有効
差し押さえはあくまでも財産を押さえる手続きであり、財産がない場合はうまく利用することができません。最低限の生活に必要な財産以外全く持ち合わせていない債務者の場合、債権回収ができない事態になってしまいます。
差し押さえられない財産もある
債権者であっても、以下のように差し押さえが禁止されている財産があります。
- 生活に必要な衣類
- 1ヶ月分の食料品
- 寝具
- 生活家電
- 実印
- 66万円未満の現金
- 生活保護給付・児童福祉手当などの請求権
- 労災などの請求権 など
給与債権は、「手取り額の4分の1まで(手取り金額が44万円を超える場合は33万円を差し引いた金額まで)」という決まりがあります。全額を差し押さえてしまうと債務者の生活が成り立たないためです。
上記のような最低限の財産しかもっていない債務者からは全く債権回収ができないか、一部しかできません。
差し押さえに必要な費用
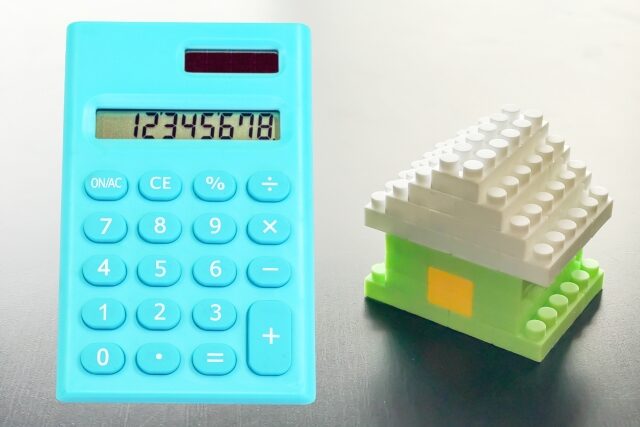
差し押さえを実際に行うために必要になる費用が主に2つあります。
裁判所にかかる費用
裁判所にかかる費用は「どの財産」を差し押さえるかによっても違いがあります。
| 差し押さえる財産 | 費用の内訳 |
|---|---|
| 債権 | 手数料:4,000円
郵便切手:3,217円(ただし、債権者数によっても変わる) |
| 動産 | 予納金:2万円~5万円
開錠業者費用:1万円~5万円 |
| 不動産 | 手数料:4,000円 郵便切手:92円 予納金:60万円債権額に応じて異なる) 登録免許税:債権額の1,000分の4 |
弁護士費用
差し押さえから強制執行までの流れは、専門的な知識を持つ弁護士に依頼して行うことが一般的です。
弁護士費用は弁護士によって千差万別です。一般的な目安はありますが、回収の見込みなどによって費用の増減を行うこともあります。依頼予定の弁護士に見積もりをしてもらうことをおすすめします。
まとめ
不動産をはじめとした財産を持つ債務者が返済に応じない場合、自由に売買できないように制限をかけるのが「差し押さえ」の主な役割です。債権回収のために強制執行が行われることもありますが、場合によっては任意売却を行うこともあります。
不動産営業として差し押さえられた物件の売買に携わる可能性があるなら、事前知識として差し押さえについて理解を深めておきましょう。
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事
- 不動産業務効率化
- 不動産DXサービス特集
- 不動産DX導入インタビュー
- 不動産業界DX
- 不動産営業とは?仕事内容と成約率アップのポイントを解説
- 賃貸管理会社はどこが良い?管理戸数ランキングと選び方を紹介

















