仮登記とは何かわかりやすく解説|メリット・デメリットや条件付所有権移転仮登記についても解説

不動産にまつわるさまざまな権利は「登記(とうき)」を行うことによって守られており、これによりスムーズな取引が実現できています。
しかし、不動産の所有権・貸借権・抵当権などの権利に関するトラブルに、登記が大きく関わっていることもあります。
不動産売買において権利関係のトラブルが起こると、その権利を取り戻すのに時間がかかったり、手続きが煩雑になったりすることでしょう。
これを防ぐために行われる「仮登記」について、どのようなメリットがあるのか、詳しい意味や事例について見てみましょう。
Table of Contents
仮登記とはわかりやすく解説
仮登記(かりとうき)とは、不動産について誰が権利を持っているのか、その不動産の情報などとともに記録される「登記」を仮に行うことを言います。
現段階では書類がそろっていないなどの理由で本登記ができないものの、仮登記を行うことによって今後本登記ができる順位をキープしておくのが目的です。
不動産における仮登記はあくまで仮であり本登記ではないため、他の人も仮登記をしようとする場合があります。
その際に注目されるのが、仮登記を行った順番です。
後に本登記をすると、仮登記の順位で本登記が行われるため、他に仮登記をしていた人への対抗力を持つことができるようになります。
つまり、不動産売買における登記競争を行うために、事前に仮登記をしてリザーブ(予約)しておくというイメージです。
また、一口に不動産の仮登記と言っても、複数の種類があります。
次から仮登記の種類について詳しく見てみましょう。
仮登記の種類
不動産における仮登記の種類には、以下のものが挙げられます。
(知りたい仮登記の種類をクリックしましょう)
それぞれどのような意味を持つ仮登記なのか、ご紹介していきます。
1号仮登記(物件保全の仮登記)
まず、1号仮登記とは、権利が実際に動いた時に行う仮登記を指します。
すでに不動産が人の手に渡るなど、実際に権利が動いている状態にも関わらず、手続きが遅くなってしまったり書類がそろわなかったりして本登記ができない状態に行われる登記です。
たとえば、不動産の所有権に関して第三者の同意や承諾が得られているにも関わらず、それを証明するための書類がない場合。
このような時に行われるのが、物件保全の仮登記である1号仮登記です。
仮登記ができる理由は、前述の通り書類がそろわなかったり、後にその不動産を購入することが決まっていたりする場合であり、登記にかかる費用が支払えないといった理由では仮登記が認められません。
ちなみに、不動産登記法105条1号によって決められているため、1号仮登記と呼ばれています。
2号仮登記(請求権保全の仮登記)
続いては、請求権保全の仮登記となる2号仮登記です。
こちらは1号仮登記とは違い、実際に権利が動いていない状態で行う仮登記のことです。
現状では権利変動がなくても、今後発生するだろう権利変動の請求権を持っている場合、それを守るために行う仮登記を意味します。
たとえば、農地を売買するためには都道府県知事の許可を得る必要がありますが、その許可を前提とした売買契約を行っている場合などです。
今後許可が下りれば売買契約が進められる、つまり農地の所有権が変動することが見込まれています。
このように、本登記をしたい不動産の権利変動が実際に起こった時、それまでに持っていた権利を守るのが2号仮登記です。
所有権移転仮登記
続いては、所有権移転仮登記です。
仮登記のうち、1号仮登記に当てはまる仮登記、つまり権利はすでに移転しているものの、その移転を証明できる書類などがそろっておらず、本登記ができていない状態を指します。
不動産を売買する際に行われるのは、お金のやり取りだけでなく所有権を移すやり取りも行われます。
このように、不動産売買で所有権を移転させることを「所有権移転」と言い、その仮として登録されている情報が所有権移転仮登記です。
所有権移転請求権仮登記
所有権移転請求権仮登記は、2号仮登記に当てはまる今後の権利を仮登記したものを指します。
現状ではまだ不動産が人の手に渡っていませんが、すでに売買を行う双方で合意して契約を行っているため、今後実際に不動産の所有権が移転するとわかっている場合に行われます。
売買とともに所有権が移った際、所有権移転ができるよう、あらかじめ売買をする双方によってその権利を予約しておくというイメージです。
条件付所有権移転仮登記
条件付所有権移転仮登記とは、何らかの条件を満たすことを前提に不動産の売買を行ったものの、その条件が満たされていないために所有権を移転できない時に行われる仮登記です。
たとえば、農地を売買する際、所有権を移転させるためには都道府県知事の許可(農地法の許可)が必要です。
農地法の許可を得ることが前提に売買された場合、許可を得ないままであれば所有権移転登記(本登記)はできないままです。
このように、何らかの条件を付けた状態で売買が行われる際の仮登記を、条件付所有権移転仮登記と言います。
抵当権設定仮登記
最後は、抵当権設定仮登記です。
住宅ローンを組む際、銀行などが設定する抵当権を本登記するまでの間、設定側となる銀行が持つ権利を守るための仮登記です。
抵当権とはいわゆる担保のことで、ここまでご紹介した仮登記の中でも抵当権設定仮登記が最も利用されています。
土地の購入や家の購入に利用される住宅ローンですが、ローンを組む銀行や間に入る保証会社が抵当権(担保)を購入する家・土地に設定します。
今後、抵当権設定の本登記を行うため、その順位を守ってくれるのが抵当権設定仮登記です。
あくまでも仮登記であり、本登記を行わない限り設定された抵当権(担保権)が実行されることはありません。
しかし、仮登記を行うことで他の金融機関がローンの融資を申し入れることが減り、抵当権の権利を設定する銀行や保証会社が本登記を行うまで優先順位が守られる仕組みです。
仮登記が行われるケース
さまざまな仮登記がありますが、実際にどのような時に仮登記が行われるのかを見てみましょう。
- 住宅ローン利用時における抵当権(担保)設定時
- 不動産買時に登記済証(権利証)などを失くしてしまった時
- 不動産の所有者が亡くなった後に贈与してもらう契約を交わす時
仮登記は住宅ローン利用時をはじめ、さまざまな時に利用されている登記です。
ローンを組むために担保を設定する時や、登記済証を失くしたために売買ができない時は、これまでご紹介した通り1号仮登記を行います。
さらに、不動産を持っている方が亡くなった際、この不動産を誰かに譲り渡す契約を行っている時にも仮登記を行うことができます。
これを「死因贈与契約」と言い、今後亡くなることを条件に所有権の変動が起こるので、現在は本登記ができず仮登記を行います。
このように、不動産に関連した仮登記は幅広く行われていることがわかります。
仮登記の効力とは
続いては、仮登記がどのくらいの効力を持つのかを見てみましょう。
仮登記はあくまで「仮」であり、本登記を行っていない状態のため、第三者に権利を主張する抵抗力はありません。
しかし、仮登記を行っている人が複数いた場合に本登記が行われると、最初に仮登記を行っていた人が優先されるため、仮登記の順位は本登記の順位と言えます。
これを「順位保全効力」と言い、仮登記を行っておく最大の目的と言えるでしょう。
仮登記のメリット
自分が仮登記をし、その後で他の人が仮登記を行ったとします。
後で本登記ができる条件を満たした時に登記の手続きを行うと、後から仮登記を行った人は本登記ができなくなるため、自分が有利になるメリットがあります。
また、1号仮登記のように書類がそろっていない段階でも手続きすることができるため、第三者への抵抗力がなくても早く予約をしたい場合にもメリットがあると言えるでしょう。
仮登記のデメリット
仮登記は、第三者に対する抵抗力はありません。
また、本登記ではないため実際に所有権が移動しているわけでもなく、あくまで本登記のための「予約」という位置づけです。
そのため本登記に移行する際には利害関係人・第三者の承諾が必要になります。
仮登記の抹消
いったん行った仮登記はさまざまな理由で取り止める、つまり抹消することができます。
本登記を行うため、他の人が行っていた仮登記を取り消してもらう(抹消する)ことも可能です。
その他、どのような場合に不動産の仮登記が抹消できるのかという状況や、条件について詳しく見てみましょう。
仮登記の抹消が必要な場合
仮登記の抹消が必要な場合ですが、よくあるのが不動産を売買するにあたって調べたところ、仮登記がついていたというパターンです。
購入しようと検討していた不動産に仮登記がついていた場合、そのまま購入をして所有権移転登記が行われたとしても、その後仮登記を行っていた人が本登記を完了させると自身は所有権を失ってしまいます。
そのため、仮登記がついた不動産の売買は、仮登記を抹消してもらうよう権利者に協力してもらいましょう。
また、相続した農地に古い仮登記がついていた場合も抹消が必要です。
農地は農地法の許可を得ることによる条件付所有権移転仮登記をつけることができますが、古くにつけられた仮登記の場合はその権利者(買い主)が死亡していることも考えられます。
権利者となる買い主が農地に対して10年間まったく手付かずの状態を維持していた場合、買い主の権利は消滅することになっています。
そのため、権利が消滅していれば仮登記の抹消が可能です。
仮登記の抹消の条件
では、仮登記をどのようにすれば抹消できるのか、その条件を見てみましょう。
- 相続人など、不動産の所有者と仮登記権利者が共同で申請をする
- 仮登記権利者が単独で申請をする
- 事前に仮登記権利者から承諾を得ている場合、不動産所有者が単独で申請できる
基本的には、不動産の所有者と、その不動産に仮登記をしている権利者が共同で仮登記抹消の申請を行います。
しかし、仮登記権利者が単独で抹消の申請ができる他、事前に仮登記権利者から許可を得ている場合のみ、不動産の所有者のみで仮登記抹消の申請ができます。
仮登記抹消の必要書類
続いては、仮登記の抹消を行う際に必要になる書類を見てみましょう。
- 登記申請書
- 登記済証
- 印鑑証明書
- 登記原因証明情報
これらのものを用意し、不動産所有者と仮登記権利者の双方で協力しながら仮登記抹消の申請を行います。
仮登記担保とは
法整備のため現在では利用されることはなくなりましたが、1979年4月にとある法律が施行されるまで行われていたのが「仮登記担保(かりとうきたんぽ)」です。
債権(借金)を抱えた人(債務者)が債権者に対して返済ができない場合、保有している不動産を売却したり、債権の代わりとして不動産で弁済したりすることを言います。
この取り決めを所有権移転請求権仮登記として仮登記をし、保有している不動産を担保にするという仕組みです。
ただ、このような方法で担保を設定するためには、債務者にとって大きなデメリットであり、債権者にとって債権以上のプラスになる可能性があります。
これを考慮して、1979年4月に仮登記担保法がスタートしました。
債務の額が不動産の額を超える場合、債権者は超過分を債務者に還さなくてはならないとされました。
仮登記の時効

仮登記には時効があります。
所有権移転請求権仮登記では、仮登記そのものには時効と言う考え方はありません。
しかし、仮登記は本登記に向けた「予約」を行うもの。
仮登記のように所有権移転の予約を行う権利を「予約完結権」と言いますが、不動産の売買を行う契約を取り決めてから10年を経過すると時効になります。
時効を迎えると、仮登記後に行う本登記請求権、つまり本登記を優先的に行う権利もなくなってしまいます。
仮登記後の本登記の方法
仮登記を行った後、条件が満たされたり書類がそろったりしていよいよ本登記を行う場合には、注意点があります。
本登記を行う際には、現在の仮登記を抹消して「仮」状態から真の登記をします。
本登記を行うためには現在の登記名義になっている人、つまり現時点で不動産を所有している人の承諾が必要になり、承諾を得た後に本登記が可能です。
登記を行う際に自動的に仮登記の抹消が行われますので、本登記以外に特別な申請は必要ありません。
本登記の詳しい手順については、『所有権保存登記とは|申請に必要な書類・手続きから費用までを解説』で詳しく解説しています。
仮登記と登録免許税
不動産の所有権移転をはじめとした登記を行う際、日本では国税である「登録免許税」という税金がかかります。
ただ、不動産の所有権移転(本登記)を行う際、事前に仮登記をしていると通常の所有権移転登記より、税額が減額されるというメリットがあります。
つまり、仮登記をせずいきなり本登記を行うのではなく、あらかじめ仮登記をしてから本登記を行うという段階的な方法を取った方が、登録免許税が安く済むということです。
仮登記物件を購入する場合の注意点
ここまでを踏まえて、仮登記がついている物件を購入する際の注意点を振り返ってみましょう。
仮登記はあくまで「仮」の状態ではあるものの、その後本登記を行った際には優先的に登記が成立する仕組みです。
仮登記が行われている不動産を購入する場合、後で仮登記権利者による本登記が行われると、そちらへの権利が優先されてしまいます。
購入前に、必ず所有権移転請求権仮登記を抹消してもらうように要求しましょう。
「仮」だからと言って放置したまま不動産を購入し、その後本登記が行われると不動産に対する権利を失ってしまうおそれがあります。
必ず仮登記の抹消を行ったことを確認してから、不動産購入を行いましょう。
まとめ
最後に、仮登記の種類についてまとめておきました。
- 1号仮登記とは:権利が実際に動いた時に行う仮登記
- 2号仮登記:請求権保全の仮登記
- 所有権移転仮登記:1号仮登記に当てはまる仮登記、つまり権利はすでに移転しているものの、その移転を証明できる書類などがそろっておらず、本登記ができていない状態
- 所有権移転請求権仮登記:2号仮登記に当てはまる今後の権利を仮登記したもの
- 条件付所有権移転仮登記:何らかの条件を満たすことを前提に不動産の売買を行ったものの、その条件が満たされていないために所有権を移転できない時に行われる仮登記
- 抵当権設定仮登記:住宅ローンを組む際、銀行などが設定する抵当権を本登記するまでの間、設定側となる銀行が持つ権利を守るための仮登記
不動産売買において必ず確認しておかなくてはならないのが、仮登記です。
仮登記が行われていることで、後々大きな権利トラブルに発展する可能性もあります。
仮登記がどのような意味・仕組みなのかを知るとともに、物件購入の際には必ず仮登記の権利を抹消してもらうこと、決して仮登記を放置しないことが、トラブルを避けて物件購入を行うためにも大切なことです。
質の高い不動産業務を提供するためにも業務効率化は必須といえます。「いえーるダンドリ」なら住宅ローンに関する業務を代行することができ、業務効率化を図ることができるので、ぜひご活用ください。
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事
- 不動産業務効率化
- 不動産DXサービス特集
- 不動産DX導入インタビュー
- 不動産業界DX
- 不動産営業とは?仕事内容と成約率アップのポイントを解説
- 賃貸管理会社はどこが良い?管理戸数ランキングと選び方を紹介


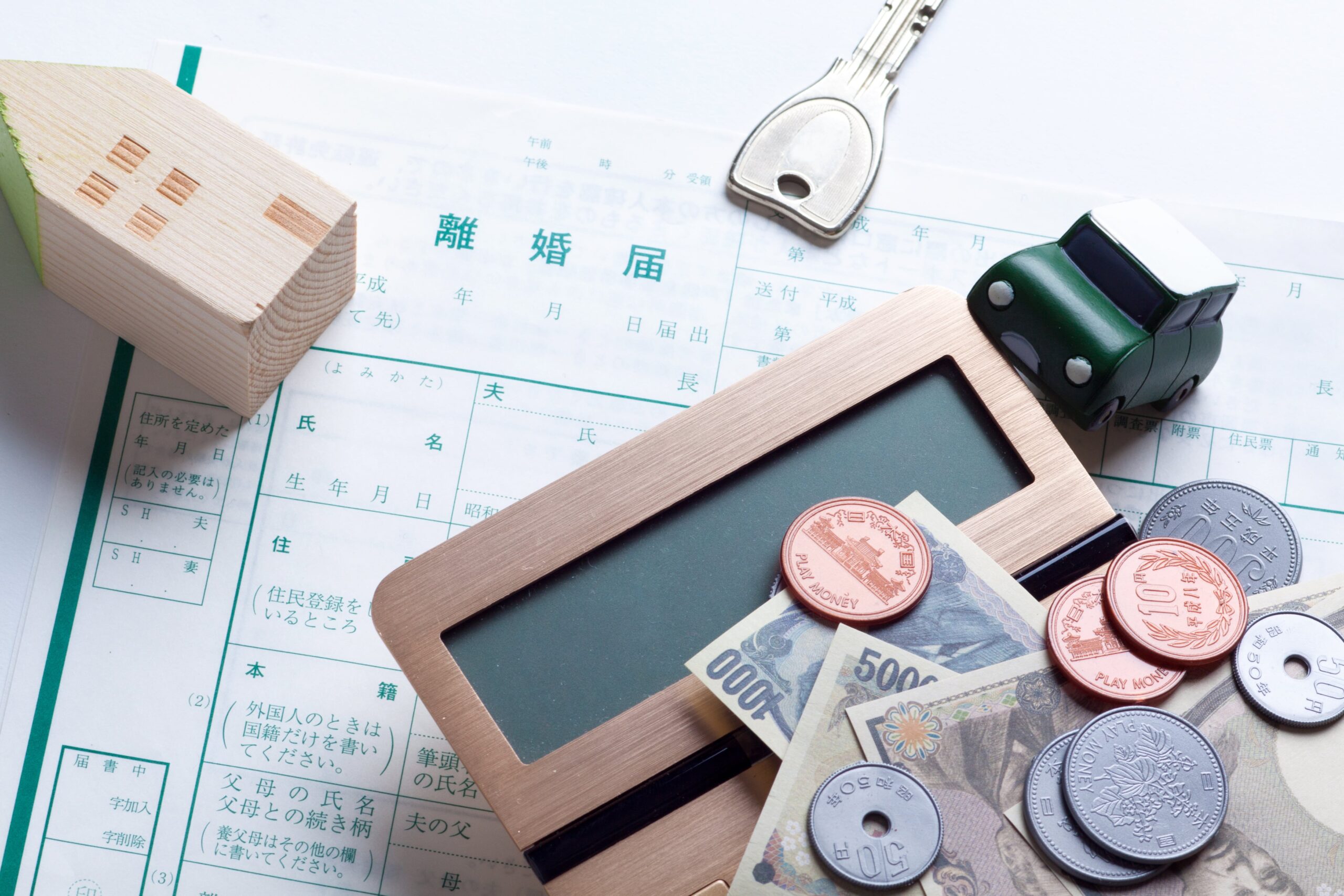






登記とは|目的や費用・手順について解説-3.jpg)







