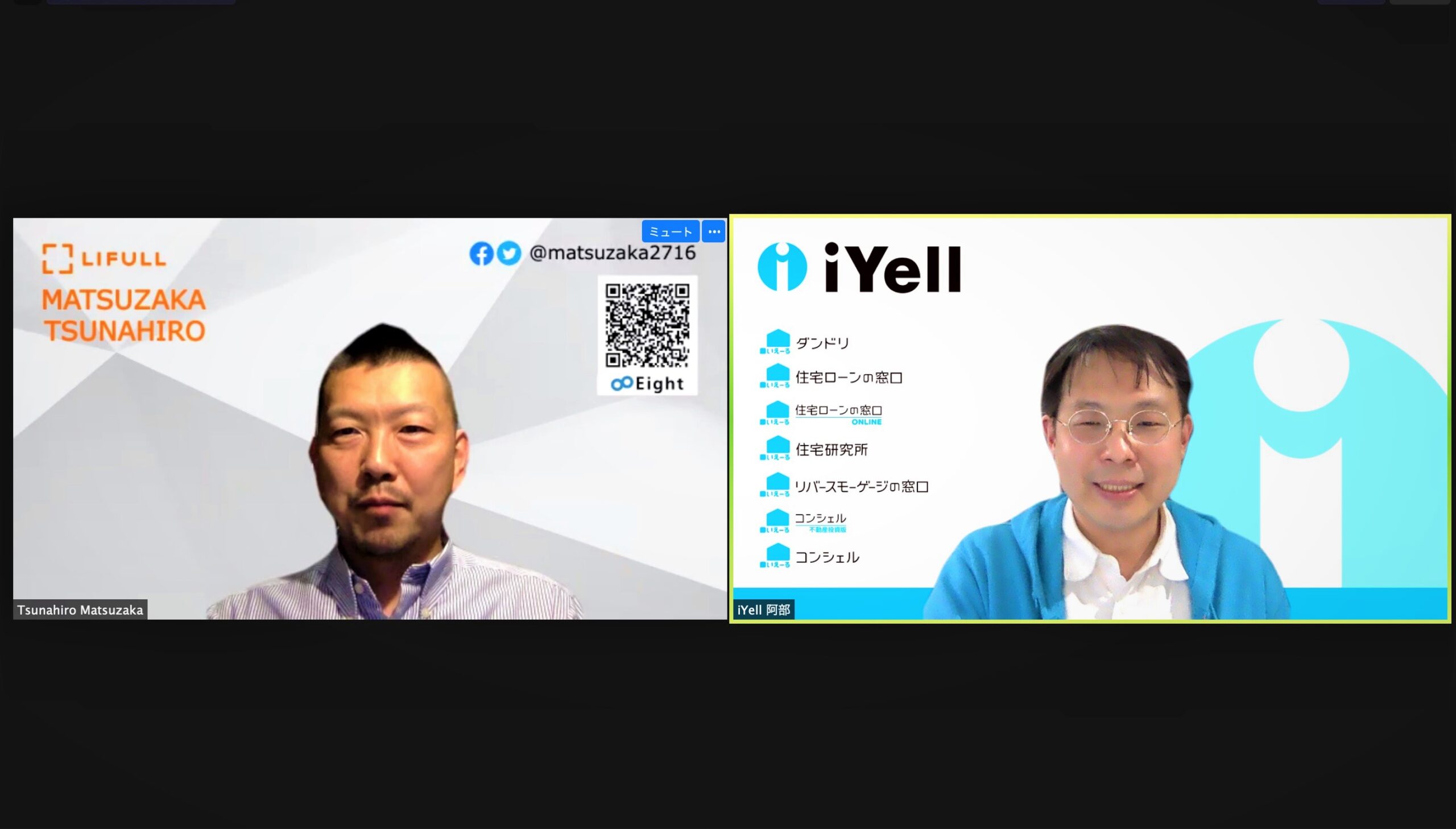ミニタイプ投入で話題に | エネファームメーカー各製品を徹底比較!

エネファーム市場は東芝とENEOSの撤退で一時活気が失われた感がありましたが、2019年10月に京セラが新製品を発表したことで再び注目されるようになりました。
今回は再注目のきっかけとなった京セラの新製品と、以前から製造・販売を続けているパナソニック・アイシン精機の製品を比較解説します。
エネファームを導入したいけど、どの製品を購入すればよいか迷っている方はぜひ参考にして下さい。
Table of Contents
エネファームとは
エネファームは正式名称を「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」と言い、家庭内における光熱費の削減を目的とした発電及び給湯システムです。
エネファームという名称自体は2008年に「燃料電池実用化推進委員会(FCC)」によって、家庭用燃料電池を一般の人にもわかりやすく認知してもらうための愛称として命名されました。
エネファームの仕組み

画像引用:一般社団法人燃料電池普及促進協会 | エネファームについて
エネファームは、家庭用燃料電池の機能とコージェネレーションの機能を合わせたもので、燃料電池が発電の役割を、コージェネレーションが給湯等の役割をそれぞれ担っています。
エネファームの仕組みやメリット・デメリットについては以下のページをご参照ください。
あわせて読みたい:未来の生活が体験できる | エネファームの仕組みやメリットを徹底解説
燃料電池とコージェネレーション
エネファームは燃料電池を用いて発電を行い、発電時に発する排熱によって給湯等を行います。
そして排熱を給湯等に再利用するシステムの事をコージェネレーションと言います。
エネファームのメリット
エネファームには以下のようなメリットがあります。
- 送電ロスがない
- 発電時のエネルギー効率が高い
- 補助金制度やガス料金優待プランがある
- 自家発電のため、電気料金を削減できる
- 貯湯タンクによって常時暖かいお湯を使うことができる
- 他の発電機と比べて騒音が小さい
- 付属モニターによって発電の様子が観察できる
エネファームのデメリット
エネファームが抱えるデメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 初期費用が高い
- 設置場所の確保が難しい
- 基本的に売電はできない
- 製品の寿命が短い
- 貯湯タンクのお湯の温度によっては発電が制限される
- 世帯人数が少ない場合はかえって割高な光熱費になる
- 天然ガス相場の影響を受けやすい
エネファームの製造メーカーを比較
エネファームは2020年3月現在パナソニック・アイシン精機・京セラの3社が製造を行っており、各メーカーがいろいろな特徴をもった製品を市場に送り出しています。
ここからはエネファーム製造メーカー3社の製品の特徴について解説します。
パナソニック

画像引用:Panasonic HP | 家庭用燃料電池「エネファーム」
パナソニックは、1999年頃から燃料電池の開発を始め、2009年にエネファームを製品化しました。
その後も、約2年ごとに新しいモデルを投入し、現在ではエネファーム市場でのトップシェアを誇っています。
・パナソニック製エネファームの特徴
①貯湯タンクが大容量
パナソニック製エネファームの最大の特徴といえるのがこの大容量の貯湯タンクです。本体サイズの高さが最大1.6mと他社製品よりも大きいことが貯湯タンクの大容量化を実現しています。
②発電アシスト風呂予約
発電アシスト風呂予約は貯湯タンクが満杯になる前に自動的にお湯張りを行い、貯湯タンクがお湯でいっぱいになったときの発電停止を防ぐ役割を担っています。
③12年間の発電設計
比較的製品寿命が短いと言われているエネファームですが、細かく発電と停止を行うことでエネルギー効率だけでなく、少しでも製品の寿命を延ばせるような設計がされています。
・パナソニック製エネファームはこんな人におすすめ
- 家庭におけるお湯の使用量が多い
- 家族の人数が多い
- 長く製品を使い続けたい
アイシン精機

アイシン精機は大阪ガス・京セラ・トヨタ自動車といった企業と共同でエネファーム開発を行っています。
燃料電池には固体酸化物形燃料電池(SOFC)を使用するなど、アイシン精機のエネファーム製造に関する特徴は技術力の高さにあります。
・アイシン精機製エネファームの特徴
①世界最高水準の発電効率と最小サイズ
2018年に発売された最新型の「typeS」は発電効率52%を誇り、また本体サイズも従来の製品より小型になっています。
②現状の給湯器に後付けできる
「typeS」は「燃料電池ユニット+給湯器」という新しいシステム構成によって、従来のモデルが対象としていたノーリツ製給湯器に加えて、リンナイやパーパス製の給湯器にも対応できるようになりました。
・アイシン精機製エネファームはこんな人におすすめ
- エネファーム本体の設置場所が広くない
- 既存の給湯器をそのまま使用することでエネファーム導入のコストを抑えたい
- 世界水準の技術力を体感することで省エネを実感したい
京セラ

京セラは主にセラミックや電子部品を製造しているメーカーですが、2019年10月に東京ガスと共同で製品開発を行った「エネファームミニ」の販売を開始しました。
エネファームミニはパーツ毎に開発メーカーが異なっている点が特徴です。
- 燃料電池ユニット:ダイニチ産業
- 出湯制御:パーパス
- 燃料電池のセルスタックシステム:京セラ
・京セラ製エネファームの特徴
①世界最小のコンパクトサイズ
エネファームミニは燃料電池ユニットと貯湯ユニットの双方を室外機程度の大きさにすることで、2019年現在世界最小サイズを謳っています。
②スマホと連携
エネファームミニのもう1つの特徴がスマホによって遠隔操作ができる点です。
「パーパスコネクト」というアプリを利用することで遠隔操作にプラスして、エネルギー使用量などのさまざまな状況を把握することができます。
・京セラ製エネファームはこんな人におすすめ
- 密集した住宅地や集合住宅に住んでいる
- 外出する時間が多く家にいる時間が少ない
エネファームの導入費用(価格)や補助金制度

エネファームが出始めた頃は本体価格と諸費用とを合わせて導入するのに平均300万円以上しましたが、現在では若干値段が下がり約250万円程度で導入ができるようになりました。
しかし、まだまだ手軽に導入できる値段とは言えないのも事実です。
そこで国や地方自治体では導入における負担を少しでも軽減するために補助金制度を設けています。
ここからは各メーカーの価格と補助金制度の中身について解説します。
本体価格
エネファームは、体購入にかかる費用だけでなく、本体に付属するリモコンや配線カバーセット、設置工事費などの諸費用が別途必要となり、諸費用の合計は約30~80万円ほどになります。
2020年3月現在における各メーカーの価格表です
| 製造メーカー | 本体価格(税抜き) | 付属品・諸費用含む金額 |
| パナソニック | 150~170万円
(オープン価格) |
200~230万円 |
| アイシン精機
(自立運転機能無し) |
132万円 | 220~250万円 |
| アイシン精機
(自立運転機能付き) |
168万円 | 220~250万円 |
| 京セラ | オープン価格 | – |
京セラ製品の価格に関しては、リフォーム会社などに問い合わせた上で下見を行う必要がありますが、諸費用含めた総額は他社よりも安くなることが多いといわれています。
補助金制度やガス料金優待プラン
・補助金制度
補助金制度は国と地方公共団体の両方がそれぞれ制度を設けています。
①国
国では「一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)」を通じて補助金の受付を行っています。
補助金の金額や申請期間などの詳細についてはこちらのHPでご確認ください。
参考:一般社団法人燃料電池普及促進協会 | 補助金制度のご案内
②地方自治体
地方自治体の場合は各自治体のホームページなどに詳細が記されていることが多いため、一度ご自身の住む自治体が補助金制度を設けているかどうかを調べてみるとよいでしょう。
・ガス優待料金プラン
ガス会社によってはエネファームを導入することで、エネファーム用のガス料金プランが適用され、ガス料金が割引されるという特典を受けられる場合があります。
エネファームを導入する前に、一度契約しているガス会社が割引プランを実施しているか確認してみるとよいでしょう。
例として東京ガスでは「エネファームで発電エコぷらん」という割引プランが提供されています。
エネファームが担う更なる役割

エネファームはガスを利用することで、発電とその際に生じた排熱による給湯等によって、省エネルギー性能を高めることを目的に開発・製造されてきました。
しかし、近年では蓄電や貯湯の特性を活かすことで、災害時におけるエネルギー確保の一環としても注目されています。
災害時におけるエネファームが担う役割については以下のページをご参照ください。
あわせて読みたい:省エネだけじゃない 意外と知らないエネファームのレジリエンス機能
まとめ
今後のエネファームの動向としては、製品自体の小型化と低価格化が進むことが予想されます。
京セラが参入したことで再び活気を取り戻しつつあるエネファーム市場ですが、さらなる技術革新を行うためには今まで以上に市場を活性化する必要があると言えるでしょう。
あわせて読みたい:未来の生活が体験できる | エネファームの仕組みやメリットを徹底解説
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事
- 不動産業務効率化
- 不動産DXサービス特集
- 不動産DX導入インタビュー
- 不動産業界DX
- 不動産営業とは?仕事内容と成約率アップのポイントを解説
- 賃貸管理会社はどこが良い?管理戸数ランキングと選び方を紹介