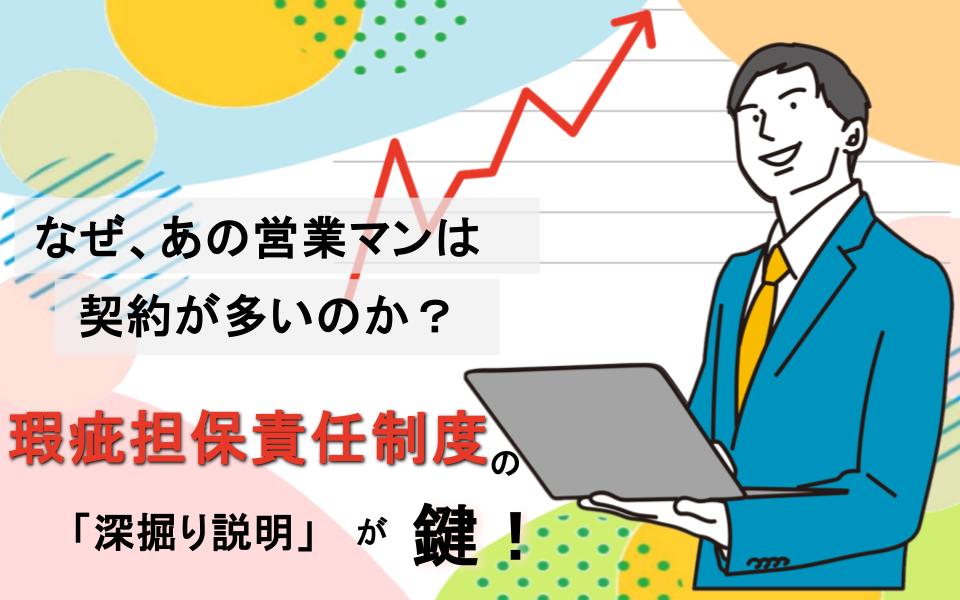売買契約書の重要事項「手付金と手付解除」の定め方|契約当事者を守ろう

「手付金」とは
不動産売買契約を締結すると、買主様が売主様に「手付金」を支払います。これには単純に「分割払いの1回目」というだけではない、大きな意味を持ちます。
売買契約書で契約を締結し、手付金を授受すると、その時点で「契約」が成立するのです。
契約が成立したら、それ以降は両当事者に法的責任が生じます。そのため、それ以降の契約解除には、契約書で定めたペナルティに従う義務も発生するのです。
「売買契約締結(契約書を交わす)」+「手付金の授受」= 契約成立 → 法的責任の発生!
「手付金」に関する注意点
手付金に関する契約誘引行為は禁止
手付金は、宅建業者である私たちが貸し付けたり、後払いを許可することはできません。契約誘引行為(契約を促したり急かしたりする行為)として、宅建業法第47条違反となるのです。
手付金に関する違反例
- 売買契約を先に済ませ、後日に手付金を授受する→「信用供与」による契約誘引行為
- 買主様に手付金を貸し付け、契約を行う→「手付金貸し付け」による契約誘引行為
宅建業者なら「手付金の保全措置」が必要
売主様が宅地建物取引業者の場合、一定額を超える手付金は第三者に保管させるよう、宅建業法第41条で定められています。これを「手付金等の保全」と言います。
万が一、売主様が物件を引き渡せない事態になっても、買主様にきちんと手付金が返還されるよう、買主様の権利を守る目的で定められているのです。
手付金の保管を請け負うのは、銀行・保険会社・指定保管機関などです。
「手付金の保全措置」の条件
- 未完成物件:売買価格の5%または1,000万円を超える場合
- 完成物件:売買価格の10%または1,000万円を超える場合
「手付解除」「手付解除期日」とは
「手付解除」とは、契約締結後、一定期間までなら、買主様は手付金を放棄することで、原則理由を問われずに契約を解除できるという取り決め方です。
売主様の場合は、買主様から契約時に受け取った手付金を返金し、さらに手付金と同額を買主様に対して支払うことで、同じく理由を問われず契約を解除できます。これを「手付流しの倍返し」と言います。
このように、手付解除ができる期間を定めたのが「手付解除期日」です。手付解除期日を過ぎてからの解約には、違約金の支払いなどペナルティが課せられます。
「手付金」「手付解除期日」の定め方
「手付金」「手付解除期日」の目安
「手付金」と「手付解除期日」の適正な定め方は、各案件により異なります。ただし、不動産業界でよく採用される定め方は以下の通りですので、目安にするといいでしょう。
- 「手付金」の目安…売買価格の5~10%
- 「手付解除期日」の目安…契約締結日から約30日
両当事者に中立的な設定をする
契約解除によるリスクが売主様・買主様のどちらか一方に偏ると、不公平な契約になってしまいます。そのため、「手付金」と「手付解除期日」を適正に定め、両当事者に公平な契約にする責任があります。
関連記事
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事