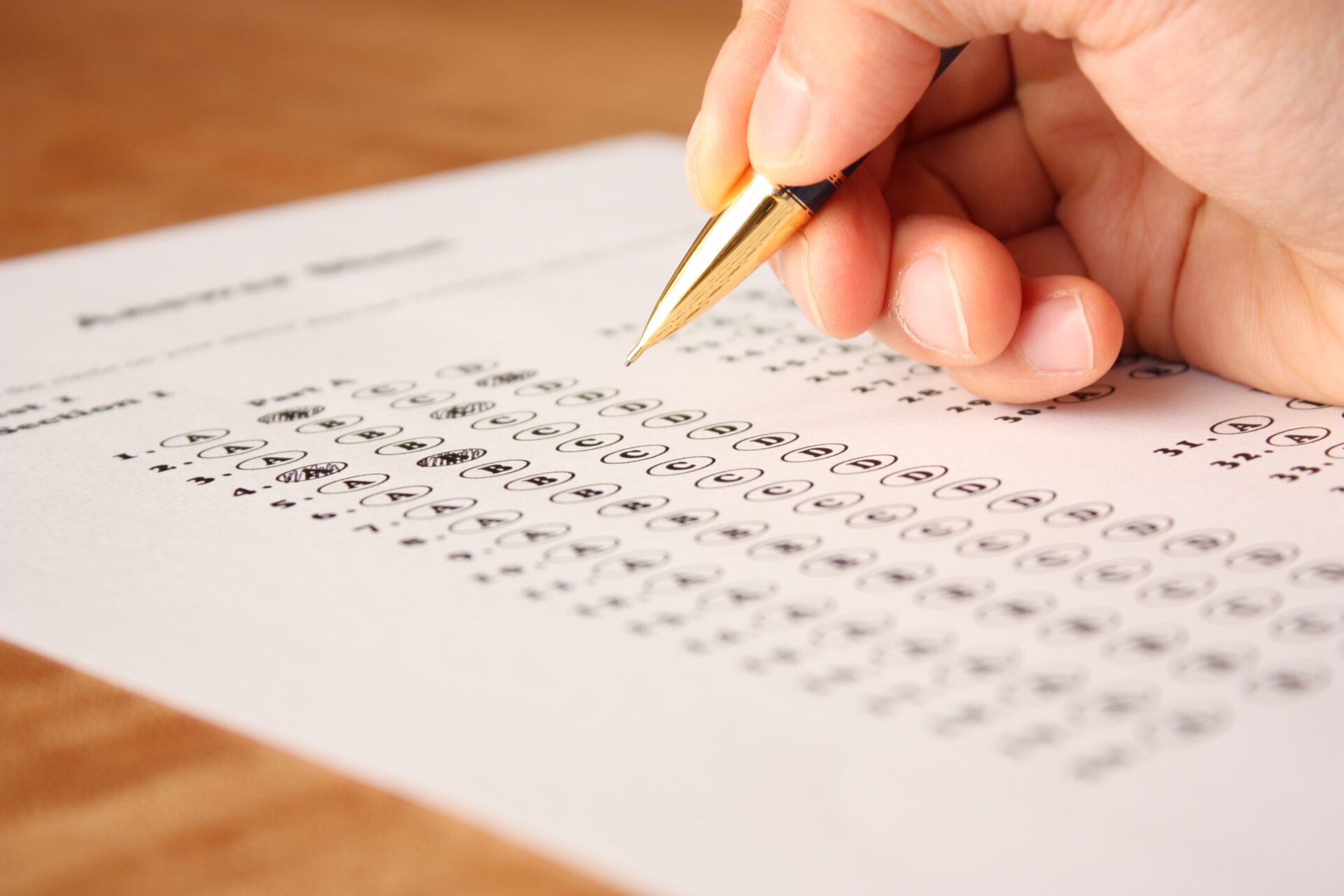営業保証金の還付と取戻し|供託金を渡す相手と条件・方法等を確認

営業保証金とは、宅建業者が取引相手に与えた損害を供託所が代わりに弁済するために供託所に預ける金銭等のことですが、供託所に預け入れられた営業保証金はどのようにして取引相手、または宅建業者自身の手に戻るのでしょうか。
今回は「営業保証金の還付」と「営業保証金の取戻し」について解説します。
Table of Contents
「営業保証金の還付」の解説

営業保証金の還付とは、宅建業者の取引相手が当該宅建業者との取引によって受けた損害の弁済を供託所に請求して、宅建業者の代わりに弁済してもらうことです。
還付を受けられる者
営業保証金の還付を受けられるのは以下の対象者です。
- 宅建業者と取引をした者
- 宅建業者に取引の媒介・代理を依頼した者
上記(1)(2)とも、還付の時点で「取引により生じた債権を有している」ことが条件となります。例えば債権が第三者弁済などにより既に消滅している場合には、営業保証金の還付は受けられません。
還付を受けられない者
上記の対象者であっても、損害を受けたのが別の宅建業者である場合には営業保証金の還付は受けられません。
また、当該取引に関連した債権であっても、事業融資・広告料・工事代金・給与等に関しては直接的な宅建業の取引による債権とは見なされないため、還付の対象から除外されます。
還付限度額
還付される上限金額は、宅建業者が供託していた営業保証金の範囲内です。
例えば、宅建業者が1,000万円の営業保証金を供託しており、取引による損害が1,500万円であった場合には、損害のうち1,000万円を供託所が弁済し、残る500万円は宅建業者の他の財産から弁済されます。
請求先
還付請求は損害を受けた者自身が、供託所に対して行います。
還付により供託金が不足した場合
供託所が請求者に営業保証金を還付し、供託すべき営業保証金が不足した場合には、宅建業者は還付額相当の営業保証金を新たに供託しなければいけません。
免許権者から営業保証金の不足があると通知された際には、宅建業者は通知から2週間以内に不足分を供託し、供託した旨を免許権者に届け出る必要があります。
期限を過ぎても供託しない宅建業者には業務停止などの罰則があります。
「営業保証金の取戻し」の解説

営業保証金の取戻しとは、営業保証金を供託する必要がなくなった宅建業者が供託所から営業保証金を返還してもらうことです。
取戻しができる者
供託所に営業保証金の取戻しを請求できる者は、当該の供託所に営業保証金を供託していた宅建業者自身です。
取戻しを請求するケース
取戻しを請求するケースは以下の事由が発生したときです。
- 免許が失効もしくは取り消しとなったとき
- 主たる事務所が移転して新たな供託所に営業保証金を供託したとき
- 一部の事務所を廃止などして供託額が必要な営業保証金の額を超えたとき
- 宅建業者が保証協会の会員になり営業保証金の供託が免除されたとき
取戻し方法
取戻し方法は、上記の事由が(1)(2)であるか、それとも(3)(4)であるかによって異なります。
事由(1)(2)の場合
事由の(1)(2)が発生した際には、当該宅建業者はまず債権者および損害賠償請求者に対して6ヶ月以内に権利を申し出るよう公告を行います。またその際には免許権者(国土交通大臣もしくは各都道府県知事)に対して公告した旨を届け出ます。
期間内に権利を申し出る者がいなかった場合、宅建業者はその旨を免許権者に申し出て、証明書の交付を請求します。証明書を受領した後、宅建業者は供託所に営業保証金の取戻し請求をすることができます。
なお、取戻し事由発生から10年を経過している場合には債権が時効により消滅していると考えられるため、上記の公告は不要となります。
事由(3)(4)の場合
公告は不要となり、直ちに取戻し請求が行えます。
「営業保証金の還付・取戻し」に関連する法律
この項目に関連する法律は以下のとおりです。
| 宅地建物取引業法(令和2年3月1日時点)
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。 2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。 |
実際に過去問を解いてみよう
問題:
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として 1,000 万円の金銭と額面金額 500 万円の国債証券を供託し、営業している。この場合、本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000 万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。(平成28年度本試験 問40より抜粋)
答え:×(限度額は1,500万円)
解説
営業保証金の還付は本店・支店の区別なく供託した営業保証金の額が還付限度額になります。よってAと取引をした者は1,000 万円の金銭と額面金額 500 万円の国債証券の合計額である1,500万円を限度として債権の弁済が受けられます。
宅建受験者はここをチェック!

「営業保証金の還付・取戻し」の試験科目
宅建業法
「営業保証金の還付・取戻し」が含まれる試験分野
営業保証金
「営業保証金の還付・取戻し」の重要度
★★★★☆ 営業保証金制度を理解しましょう
「営業保証金の還付・取戻し」過去10年の出題率
60%
2023年宅建試験のヤマ張り予想
営業保証金制度は、過去の宅建試験でも90%以上の確率で出題されている頻出項目です。
「供託」についての出題が最も多く、「還付」「取戻し」に関する問題は、出題率が若干低くなっています。
しかし、出題率が高いことには変わりありませんので、営業保証金制度全体についてよく理解しておく必要があります。
宅建士を目指している方は「目指せ!宅建士への道」を参考にしてみてください。
「営業保証金の還付・取戻し」ポイントのまとめ
この項目で押さえておくべきポイントは以下のとおりです。
- 「営業保証金の還付」は損害を受けた取引相手が供託所から弁済を受けることを指す
- 還付の限度額は営業保証金の範囲内
- 還付により不足した供託金は2週間以内に補填しなければならない
- 「営業保証金の取戻し」は供託の必要がなくなった宅建業者が供託所から返還を受けることを指す
- 取戻しに際して公告が必要な場合と必要でない場合がある
- 公告期間は6ヶ月以上
最後に

今回は、供託した営業保証金の還付、あるいは取り戻しについて解説しました。
「還付」と「取戻し」は似ている言葉ですが、それぞれ金銭等が渡る相手が違います。
混同しないように気をつけて、それぞれの場合の決まりごとをしっかり理解しましょう。
次の記事(弁済業務保証金制度とは何かを解説|分担金の納付から保証協会の供託まで)を読む
前の記事(営業保証金とは何かわかりやすく解説|供託の目的や方法、期限なども紹介)を読む
スペシャルコンテンツに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
宅建に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事
質の高い不動産業務を提供するためにも業務効率化は必須といえます。「いえーるダンドリ」なら住宅ローンに関する業務を代行することができ、業務効率化を図ることができるので、ぜひご活用ください。