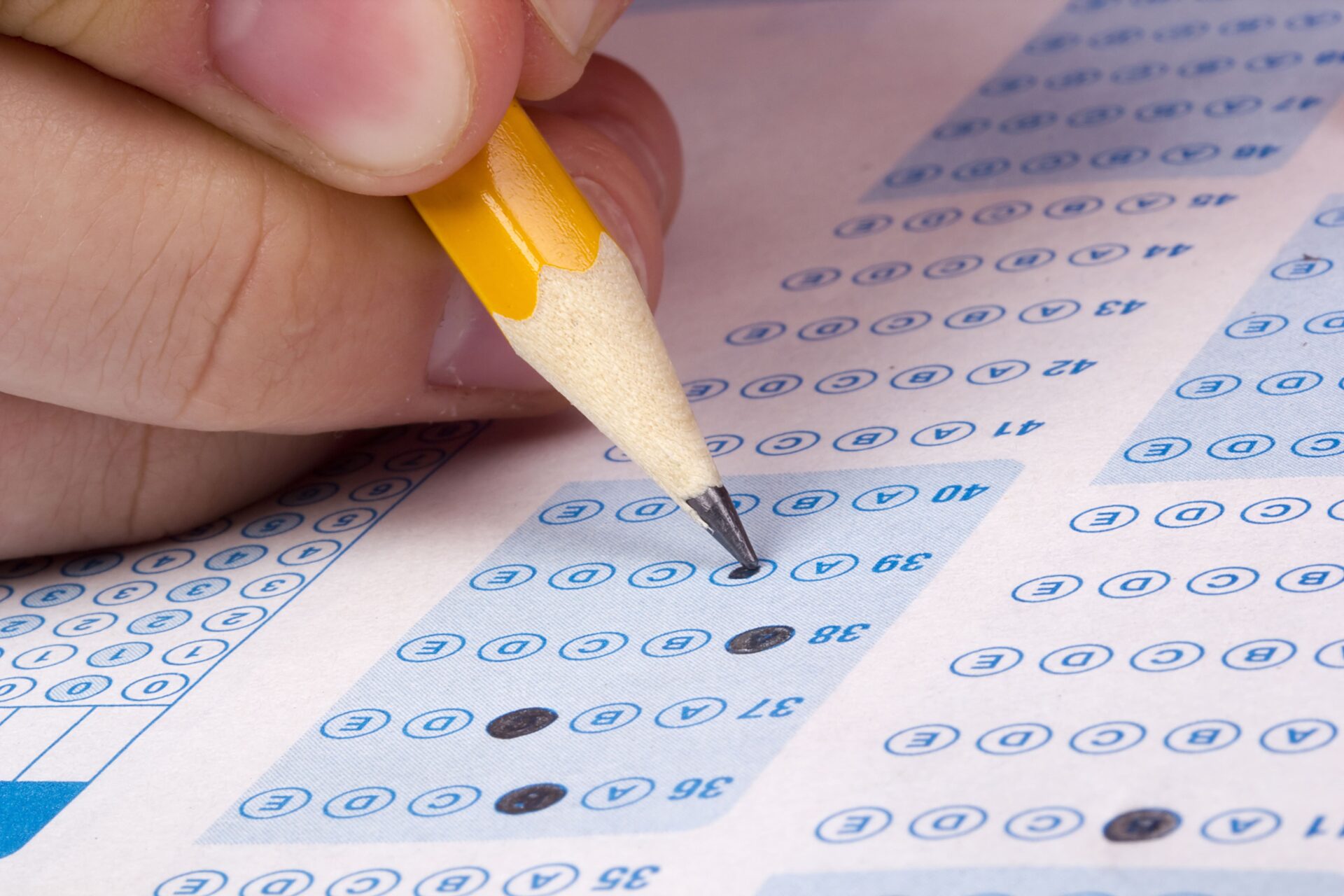【宅建業法】事務所とは何か|定義や事務所に必要な標識も徹底解説

宅建業を営む上では「事務所」の設置が必要になります。
では、その事務所とは何でしょうか。いわゆるオフィスのこととして考えれば良いのでしょうか。
宅建業法では「事務所」を定義し、事務所として営業するために必要なものを義務付けています。
今回は宅建業法における事務所とは何かについて解説します。
Table of Contents
宅建「事務所」とは

宅建業法で定義している事務所とは、宅建業者が宅建業務を行うために営業している事業所のことです。
事務所は宅建業者により以下の3つに分類されます。
- 本店(主たる事業所)
- 宅建業を営む支店(従たる事業所)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの
本店と支店
複数の拠点で営業している企業の場合、本店と支店が存在します。企業で行う業務が多岐にわたる場合、すべての事業所で宅建業を営んでいるとは限りません。
本店・支店における宅建業務の有無と事務所とみなされるかどうかの関係を、宅建業法では以下のように定義しています。
【本店】
| 宅建業を営んでいる | 事務所として扱われる |
| 宅建業を営んでいない | 事務所として扱われる(支店に対しての司令塔の役目を果たすため) |
【支店】
| 宅建業を営んでいる | 事務所として扱われる |
| 宅建業を営んでいない | 事務所として扱われない |
案内所等
企業の事業所でなくても「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」である案内所等は事務所と同様に扱われます。具体的には現地案内所や分譲マンションのモデルルームなどです。
なお、現地オープンハウスなどに設けられたテント張り案内所は継続的な業務を行わないために事務所とはみなされません。
宅建「事務所」に必要な掲示物および備付け

上記で「事務所」として定義された事業所には、以下の掲示および備付けの義務が課せられます。
- 標識の掲示
- 報酬額の掲示
- 業務に関する帳簿の備付け
- 従業者名簿の備付け
それぞれの規定を確認しましょう。
標識の掲示
標識は正式には「宅地建物取引業者票」と言います。
縦30㎝以上×横35㎝以上の耐久性がある材質で作成したものを、宅建業者自らが作成して掲示します。

画像引用:公益社団法人全日本不動産協会 東京都本部|不動産業者を訪れよう
標識の規定
宅地建物取引業者票には以下の項目を記載します。
- 免許証の番号
- 免許の有効期間
- 会社の商号(または名称)
- 代表者の氏名
- 事務所に設置した専任の宅地建物取引士の氏名
- 主たる事務所の所在地と電話番号
報酬額票の掲示
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額をあらかじめ掲示します。

画像引用:有限会社キンタロウ|報酬額表(宅地建物取引業者)【最新版】
業務に関する帳簿の備付け
取引の都度記載する帳簿(取引台帳)を各事務所に備え付け、その事務所で行った取引履歴を5年間保存する義務があります。
また、宅建業者自らが売主となった新築住宅に係る取引については10年間保存します。
帳簿に記載する事項
帳簿(取引台帳)に記載する事項は以下のとおりです。
- 取引年月日
- 宅地建物の所在・面積
- 取引態様(売買・交換又は売買・交換・賃借の代理・媒介の別)
- 取引相手もしくは代理人の氏名・住所
- 取引に関与した宅建業者の商号または名称
- (宅地の場合)現況地目・位置・形状その他の概況
- (建物の場合)構造上の種別・用途その他の建物の概況
- 売買金額・賃料・交換物件の品目及び交換差金
- 報酬額
- 特約
- その他
従業者名簿の備付け
各事務所で宅建業に従事する全ての従業員に関する名簿を作成し、最終の記載をした日から最低10年間は保存しなければいけません。
従業者名簿に記載する事項
従業者名簿に記載する事項は以下のとおりです。
- 従業者の氏名
- 従業者証明書の番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 宅地建物取引士であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となった年月日
- (当該事務所の従業者でなくなった者は)その年月日
取引先等より閲覧請求があったとき
従業者名簿の閲覧請求を取引先等より受けたときには、閲覧に供する義務があります。
これは不動産取引の関係者の利益を保護するために、従業者のなりすまし防止や従業者がミスを犯した際の責任追及ができるようにするためです。
宅建「事務所」に関連する法律
この項目に関連する法律は以下のとおりです。
| 宅地建物取引業法(令和2年3月1日時点)
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 |
実際に過去問を解いてみよう
問題:
宅地建物取引業者Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第 50 条第1項に規定する標識を掲示しなかった。この場合Aは宅地建物取引業法の規定には違反していない。(平成28年度本試験 問29より改題)
答え:×(違反している)
解説
一団の宅地建物の分譲をする際の現地案内所は、たとえ契約の締結や申込の受付を行わなくても標識を掲示しなければいけません。宅地建物取引業法の規定に違反しているため、答えは×です。
宅建受験者はここをチェック!

「事務所」の試験科目
宅建業法
「事務所」が含まれる試験分野
事務所
「事務所」の重要度
★★★★★ 試験だけでなく実務でも重要
「事務所」過去10年の出題率
70%
2023年宅建試験のヤマ張り予想
例年の宅建試験でも事務所に関する出題率は高く、特に事務所に必要な掲示物等については十分な知識が求められます。
また、本記事でご説明する内容は、今後宅建業界で働く上では当然必要になってくる基本的な知識です。試験対策としてだけでなく、宅建業界人としてしっかり理解しておきましょう。
宅建士を目指している方は「目指せ!宅建士への道」を参考にしてみてください。
宅建「事務所」ポイントのまとめ
この項目で押さえておくべきポイントは以下のとおりです。
- 事務所は宅建業者が宅建業を営むために営業している事業所のこと
- 事務所には本店・支店・継続的な業務を行う案内所等がある
- 事務所には標識・報酬額の掲示義務、帳簿・従業者名簿の備付け義務がある
最後に

今回は宅建業法が定義している「事務所」について解説しました。
事務所とは、宅建業界で働く皆さんが実際に仕事をする場所です。どんな規定があり、その目的は何かをよく理解しましょう。
前の記事を学ぶ:宅建業に該当する行為・しない行為の仕分けと宅建免許がいらない特例
次の記事を学ぶ:宅建業者の設置義務|従業者証明書や成年者である専任の宅地建物取引士の設置も紹介
宅建を学びたい方:目指せ!宅建士への道
関連記事
宅建業の開業に必須の免許制度を解説|免許権者と免許の基準とは
免許の効力と各種変更時の届出・申請を確認|免許証と名簿の管理
事務所以外の場所における3つの義務|標識・宅建士の設置・案内所等の届出