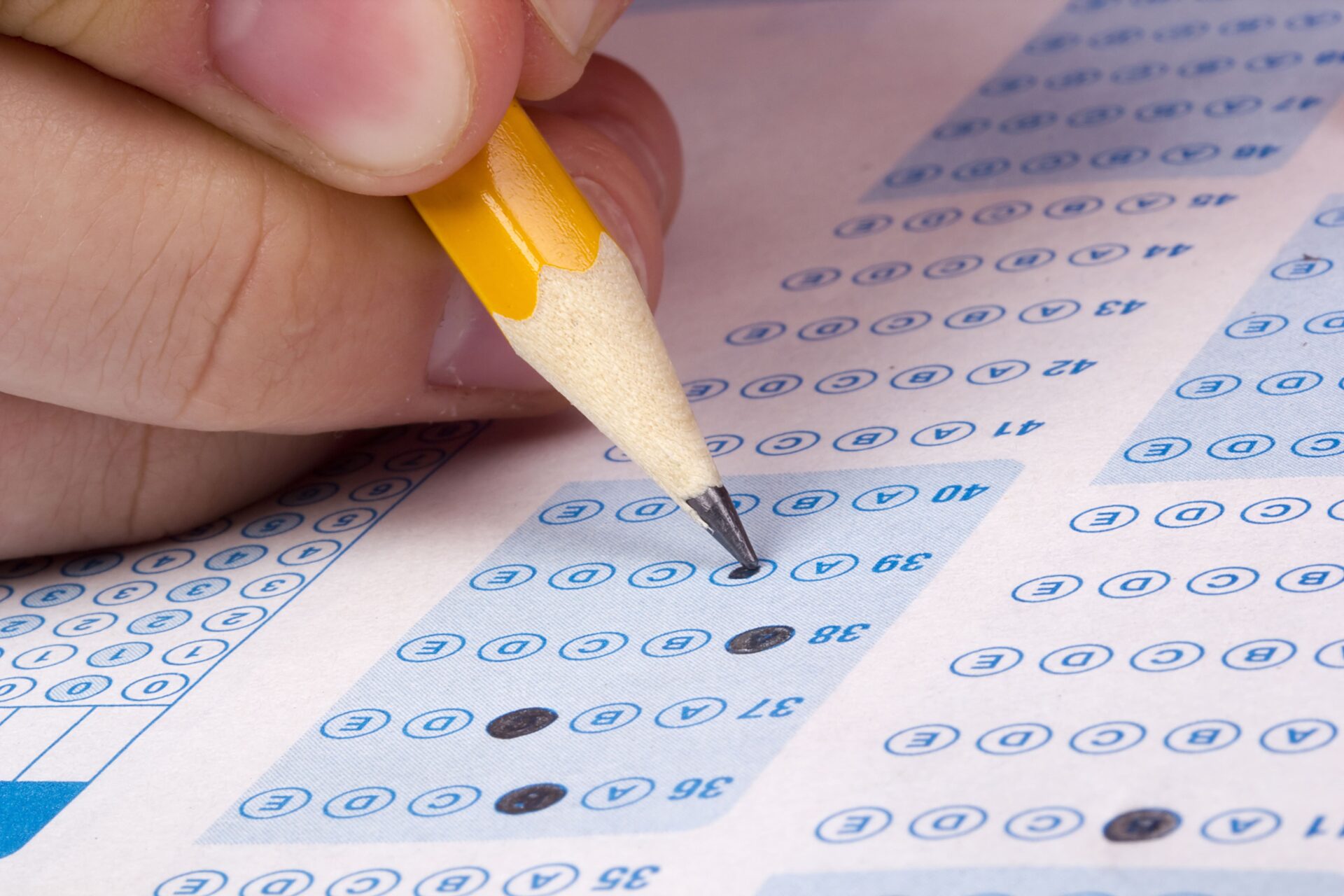宅建業に該当する行為・しない行為の仕分けと宅建免許がいらない特例

宅地建物取引業法には、初めに「宅建業とは何か」が定義されています。この定義に該当する行為を行う場合には免許が必要であり、該当しない場合は不要です。
そのため、この仕分けは宅建業に関わる場合に重要となります。宅建試験でも、免許が必要か不要かを問う問題がよく出題されます。
そこで今回は、宅建業に該当する行為としない行為の区分けについて解説し、宅建業の定義を明確にしたいと思います。
また、例外的に免許不要で宅建業を営める者・団体についてもご説明します。
Table of Contents
「宅建業に該当する行為・しない行為/免許がいらない特例」の解説

宅地建物取引業(宅建業)の定義
まずは、宅建業の定義を確認しましょう。宅建業は、その言葉通り「宅地または建物の取引を業とすること」です。
宅地・建物・取引・業のそれぞれの語句は、以下のように定義されています(宅地建物取引業法第2条)。
| 宅地 | ①建物の敷地に供される土地
②用途地域内の土地 |
| 建物 | 住宅や事務所・店舗・工場・倉庫など
※マンションの1室も1つの建物とする |
| 取引 | ①自らの宅地または建物の売買・交換
②宅地または建物の売買・交換・貸借の代理 ③宅地または建物の売買・交換・貸借の媒介 |
| 業 | 不特定多数の者に対して、反復継続して取引を行うこと |
宅建業に該当する行為・しない行為
前項で示した定義から、宅建業に該当する行為としない行為は、以下のように分類することができます。
| ①「宅地」に該当するか | ||
| 地目が違う土地(例:山林など)を建物を建てる目的で取引 | →建物を建てる目的であれば地目が違っても「宅地」扱いとなる | 宅建業に該当する |
| ②「取引」に該当するか | ||
| 他人に代理・媒介をしてもらい自己所有の宅地や建物を売買 | →「自らの宅地または建物の売買」に当たる | 宅建業に該当する |
| 自己所有の宅地や建物の賃貸 | →自己所有の不動産であれば、貸借は取引に該当しない | 宅建業に該当しない |
| 賃借した宅地や建物の転貸 | →「自ら賃借」に当たる | 宅建業に該当しない |
| ③「業(不特定多数)」に該当するか | ||
| 企業が自社の社員のみに対して行う宅地や建物の売却 | →自社の社員は「特定」の相手とみなされる | 宅建業に該当しない |
| 多数の友人・知人に対する宅地や建物の売却 | →「不特定多数」とみなされる | 宅建業に該当する |
| 多数の公益法人を対象とした宅地や建物の売却 | →「不特定多数」とみなされる | 宅建業に該当する |
| ④「業(反復継続)」に該当するか | ||
| 宅地や建物の分譲 | →「反復継続」に当たる | 宅建業に該当する |
| 多数の宅地や建物を一括して売却 | →「反復継続」とみなされない | 宅建業に該当しない |
| 多数の宅地や建物の売却について一括して代理を依頼 | →代理人は宅建業として取引するため、その法的効果は当事者である売主に帰属する | 売主の売却行為は宅建業に該当する |
免許不要で宅建業を行える例外

原則として、宅地建物取引業に該当する行為を行う者は、免許を取得しなくてはならず、無免許での営業は罰則の対象となります。しかし、以下の者は例外的に免許不要で宅建業を行うことができます。
①信託会社・信託銀行
信託業法による一定の免許を受けた信託会社や、信託業務を兼営する金融機関(信託銀行など)は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされます(第77条)。
ただし、宅建業を営もうとする場合には、国土交通大臣に届出をする必要があります。また、宅建業法の免許に関する規定は適用されません。
②国・地方公共団体
国(または都市再生機構)や地方公共団体(または地方住宅供給公社)には、宅建業法は適用されません(第78条)。そのため、本来なら宅建業とみなされ免許を受けていなければ行えない取引も、免許不要で行うことができます。
③破産管財人
個人や法人が自己破産を申立てた場合に、財産や財団の換価を行う際、破産管財人は自ら売主となって売買取引を行います。
この破産管財人の取引行為は、破産法に則して裁判所の監督下で行われるため、宅建業とはみなされません。そのため、反復継続して行う場合も免許は必要ありません。
ただし、その代理・媒介は宅建業法の「取引」に該当します。
「宅建業に該当する行為・しない行為/免許がいらない特例」に関連する法律
宅地建物取引業の定義と免許不要の特例に関する法律には、以下の条文が挙げられます。
| 宅地建物取引業法(令和元年9月14日時点)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。 (以下省略)
第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。 2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。 2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。 |
実際に過去問を解いてみよう
問題:
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
- 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
- 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
答え:4〇
解説
信託業法による一定の免許を受けた信託会社や、信託業務を兼営する金融機関(信託銀行など)は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、免許不要で宅建業を行えます。
ただし、宅建業を営もうとする場合には、国土交通大臣に届出をする必要があります。
宅建受験者はここをチェック!

「宅建業に該当する行為・しない行為/免許がいらない特例」の試験科目
宅建業法
「宅建業に該当する行為・しない行為/免許がいらない特例」が含まれる試験分野
宅地建物取引業の定義
「宅建業に該当する行為・しない行為/免許がいらない特例」の重要度
★★★★★ 超頻出問題の解答に直結する知識
「宅建業に該当する行為・しない行為/免許がいらない特例」過去10年の出題率
100%
2023年宅建試験のヤマ張り予想
宅建業の定義に関する問題は、毎年のように出題されています。2022年も出題される前提で学習を進めましょう。
特に、今回解説する内容のように、宅建業に該当するか、免許が必要かを問う問題が多いため、合格に直結する試験範囲としてしっかり確認してください。
「宅建業に該当する行為・しない行為/免許がいらない特例」ポイントのまとめ
この項目で押さえておくべきポイントは以下のとおりです。
- 建物を建てる目的であれば、地目が宅地でなくても、宅建業法上は宅地とみなされる
- 他人の代理・媒介で自己所有の宅地や建物を売買する行為は、宅建業に該当する
- 企業が自社の社員に宅地や建物を売却する行為は、宅建業に該当しない
- 多数の友人・知人に対する宅地や建物の売却は、宅建業に該当する
- 宅地や建物の分譲は取引の反復継続とみなされ、宅建業に該当するが、一括売却は該当しない
- 多数の宅地や建物について一括して売却の代理を依頼した場合、代理行為が宅建業に当たるため、売主の行為も宅建業とみなされる
- 信託会社・信託銀行・国・地方公共団体・破産管財人は宅建業を免許不要で行える
最後に

宅建業の定義に関する問題とは言え、出題形式は事例問題のように個別のケースについて解答することが多くなります。そのため、学習範囲として暗記量が多く、混乱しやすい部分と言えます。
それを、ただ丸暗記しようとするのは非効率ですので、「宅地」「建物」「取引」「業」それぞれの語句が意味する範囲を明確にし、答えとその理由を紐づけて覚えるようにしましょう。
質の高い不動産業務を提供するためにも業務効率化は必須といえます。「いえーるダンドリ」なら住宅ローンに関する業務を代行することができ、業務効率化を図ることができるので、ぜひご活用ください。
次の記事(宅建業とは|宅地・建物・取引・業それぞれの意味や定義を解説)を読む
前の記事(契約トラブルを解決する民法規定|債権者代位権・詐害行為取消権・不当利得)を読む
スペシャルコンテンツに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
宅建に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事