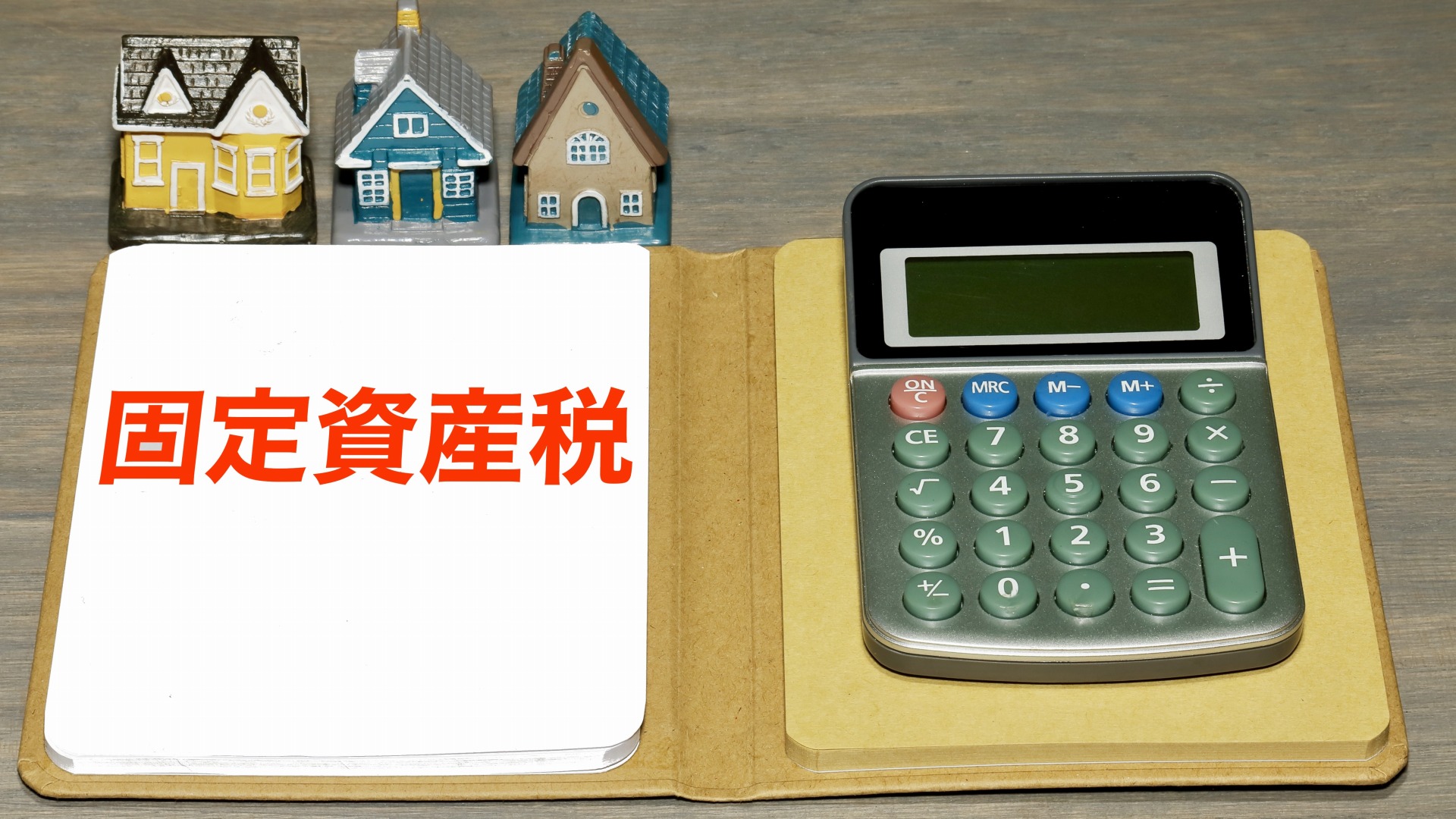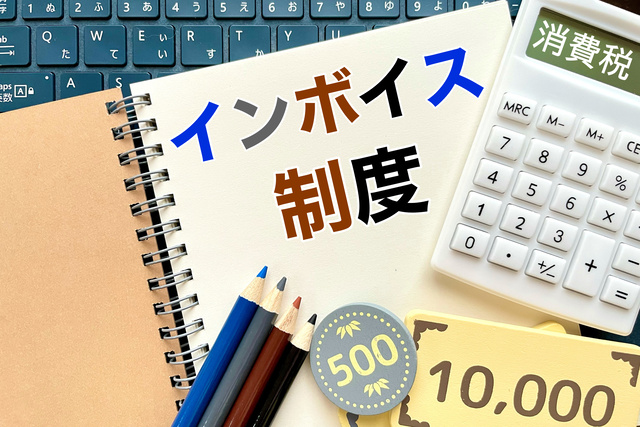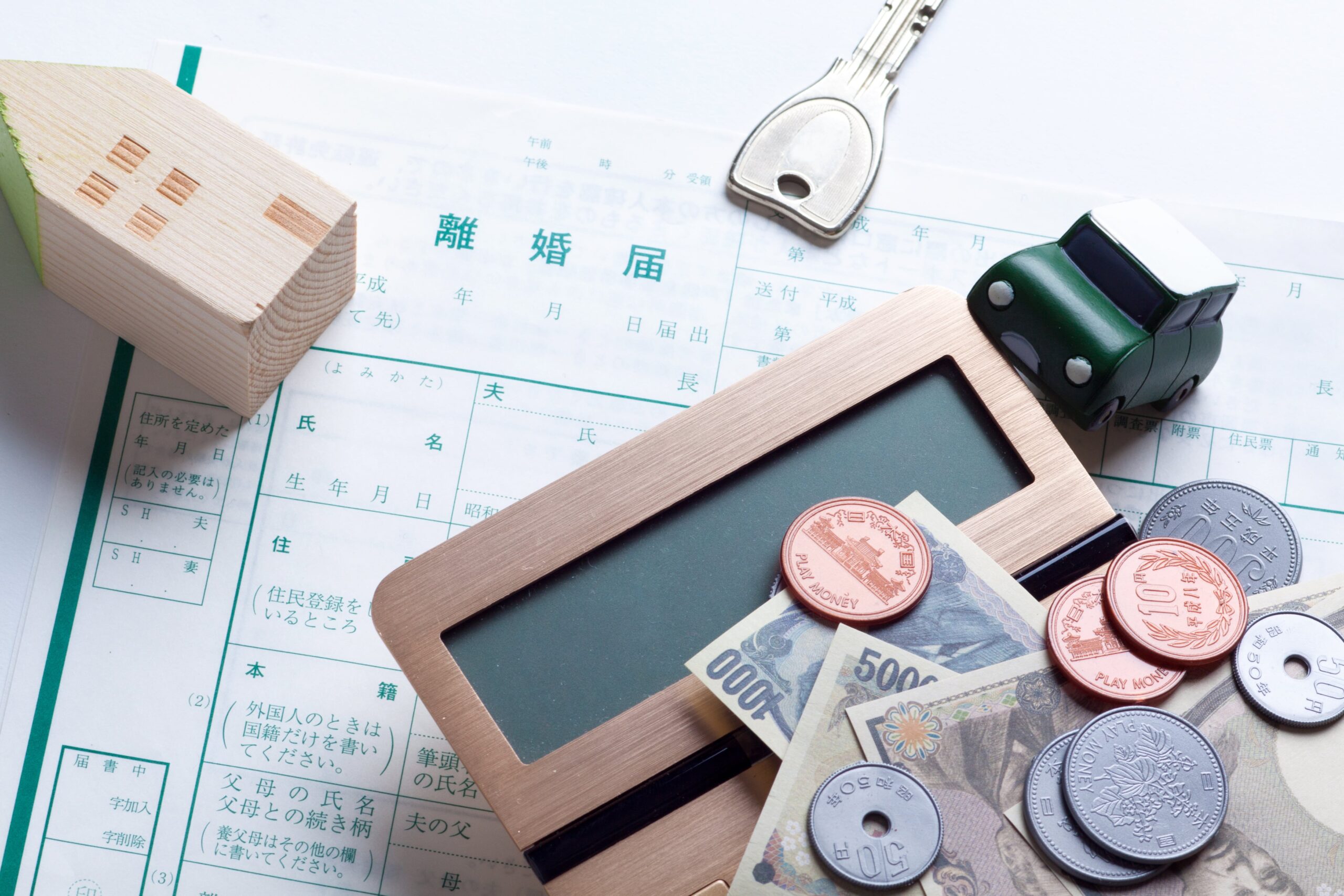住宅取得等資金の贈与税の非課税とは|省エネ住宅等購入の際にチェック

お客様が家を購入するときの選択肢として、光熱費がかからずに環境にも優しい省エネ住宅や、地震に強い住宅、そしてバリアフリー性の高い住宅を候補に挙げている人も多いのではないでしょうか。
上記で述べた住宅に関しては税制上の優遇措置を受けることができます。
今回はこの税制上における優遇措置について詳しく解説していきます。
Table of Contents
住宅取得等資金の非課税制度とは
冒頭で述べた税制上における優遇措置とは、住宅取得等資金の非課税制度の事を指します。
住宅取得等資金の非課税制度とは、2021年12月31日までに直系尊属(両親・祖父母・曾祖父母)から不動産を購入するための資金として贈与を受けた場合、それぞれの条件に当てはまる非課税限度額に応じて贈与税が非課税になる制度のことを言います。
もう1つの優遇措置として相続時精算課税制度があります。こちらも贈与税に関する特例制度になりますが、住宅購入に関しては住宅取得等資金の非課税制度のほうが直接的に関わってくるため、ここでは住宅取得等資金の非課税制度を中心にして解説していきます。
住宅取得等資金
住宅取得等資金として該当するケースは以下の2つになります。
- 自分が住むための家屋の新築での取得及び増改築
- 家屋を建てる土地の借地権など権利の取得
ただし、親族とは特別な関係にある人と契約(例:建設会社の人と請負契約など)を結んで、家屋の使用に充てる資金については住宅取得等資金には含まれません。
計算方法
計算方法は利用する制度によって2通りの方法があります。
➀住宅取得等資金の非課税制度のみを利用する場合
非課税となる金額+基礎控除110万円
この場合年110万円までは税金がかからない基礎控除を加えることが可能です。
②相続時精算課税制度を併用する場合
非課税となる金額+相続時精算課税2,500万円
相続時精算課税は生涯で2,500万円まで相続税が掛からない制度です。
・消費税率が10%以外や消費税が掛からない場合の非課税限度額一覧
| 非課税となる金額 | ||
| 契約の締結日 | 良質な住宅用家屋 | 一般住宅用家屋 |
| 2015年12月まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 2016年1月~2020年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
| 2020年4月~2021年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
| 2021年4月~2021年12月 | 800万円 | 300万円 |
・消費税10%が掛かる場合の非課税限度額一覧
| 非課税となる金額 | ||
| 契約の締結日 | 良質な住宅用家屋 | 一般住宅用家屋 |
| 2019年4月~2020年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 2020年4月~2021年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 2021年4月~2021年12月 | 1,200万円 | 700万円 |
条件
・利用できる人
- 住宅を取得するために金銭等の贈与を受け、それを住宅取得資金に充当していること。
住宅そのものの贈与や住宅取得後の金銭贈与は対象になりません。 - 直系尊属(両親・祖父母・曾祖父母)からの贈与であること
- 贈与を受ける人がその年の1月1日の時点で20歳以上であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受け居住していること、また居住することが見込みである場合は、贈与を受けた年の翌年12月31日までに住み始めること
- 贈与を受ける人は贈与を受けた年の取得金額が2000万円以下であること
2000万円を超えている場合(以上×)はこの制度の適用外となります。 - 2009年~2014年の間に旧非課税制度の適用を受けたことがないこと
- 次のいずれかに該当すること
- 贈与を受けた時点で日本国内に住所を有すること
- 贈与を受けた時点で日本国内に住所を有しないが、日本国籍を有しかつ受贈者(贈与を受ける人)または贈与者(贈与する人)が贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
- 贈与を受けた時点で日本国内に住所も国籍も有していないが、贈与者が日本国内に住所を有していること
・利用できる住宅
- 日本国内に存在し、贈与を受けた人の居住用住宅であること
家屋が2つ以上の場合は、主として居住する1つの家屋のみに該当します。 - 建物の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 建物の登記簿上の床面積の2分の1が居住用であること中古住宅の場合は建物の築年数(家屋取得日以前)が、鉄筋建物などの耐火建築物なら25年、木造などの耐火建築物以外なら20年以内であること
但し下記の場合は例外として扱われます。
・新耐震基準に適合している
・既存住宅売買瑕疵保険に加入してる
・新耐震基準に適合していなくても、取得の日までに耐震改修工事の申請等を行い、かつ居住の日までに工事を完了しているもので、贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合していることが証明されたもの
・増改築の場合は上記の1~③に加えてさらに以下の条件が追加されます。
- 増改築等に掛かる契約を2021年12月31日までに締結していること
- 増改築工事等に要した額が100万円以上であること
- 居住部分の工事費が全工事費の半分以上であること
- 増改築等に掛かる工事が、一定の工事としての証明がなされたものであること
手続き
手続きとしては、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける事を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また贈与税が掛からない場合でも、同期限内に贈与税の申告を行う必要があります。
なお、期限の3月15日を過ぎると特例制度の適用を受けられなくなります。
【提出書類】
- 住宅取得等資金の非課税の計算証明書
- 受贈者の戸籍謄本(氏名・年月日・贈与者に対して直系尊属に該当することがわかるもの)
- 受贈者の住民票の写し
- 新築などを行った住宅用家屋の登記事項証明書
- 新築または取得に関する契約書など一定の書類
良質な住宅用家屋

住宅取得等資金の非課税制度を適用する際に、該当する不動産が良質な住宅用家屋であれば非課税枠が500万円増加します。
良質な住宅用家屋の基準を押さえておきましょう。
➀省エネルギー性の高い住宅
- 省エネルギー対策等級(平成27年4月以降は断熱等性能等級)に係る評価が等級4の基準に適合している住宅
- 一次エネルギー消費量等級に係る評価が、等級4・等級5の基準に適合する住宅
よい断熱材ほど断熱性が高く、冷暖房等のエネルギーを消費しない分環境にも優しいですが、建材費などの個人負担が増加するため、負担軽減及び促進を図るのを目的としています。
一次エネルギー消費量とは、外壁など外皮の断熱性能だけでなく、冷暖房など設備機器も含めた建物全体の省エネルギー性能を表した基準です。両者の性能を合わせて計算することで、より省エネルギー住宅の詳細な等級及び基準化を図っています。
②耐震性の高い住宅
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級2・等級3の基準に適合している住宅
- 地震に対する構造躯体の倒壊防止及び損傷防止に係る評価が免震建築物の基準に適合している住宅
耐震等級とは、住宅性能表示制度や耐震診断によって、建物がどれだけ地震に耐えられるかを示した指標です。
免震建築物とは地震と建物を間を絶縁し、短い周期の揺れを緩やかな揺れに変える構造の建築物をいいます。絶縁する部材には積層ゴムアイソレーターなどを使用します。
③バリアフリー性の高い住宅
高齢者等配慮対策等級に係る評価が等級3・4・5の基準に適合している住宅
バリアフリー基準がこのケースに該当します。
良質な住宅用家屋を証明するための書類

画像引用:ダイレクト火災保険
良質な住宅用家屋を証明するためには①②のケースでいずれか1つの書類を取得する必要があります。
①新築住宅
- 住宅性能証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等
- 認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅建築証明書等
②中古住宅及びリフォーム・増改築など
- 住宅性能証明書
- 既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し(耐震等級・免震建築物、高齢者等配慮対策等の専有部分のみ)
上記の書類を取得する前に、当該家屋に関係している不動産業者(工務店など)に証明書類を取得できるか、または取得済みかを確認しておくとよいでしょう。
住宅性能評価書
住宅性能評価書とは、設計段階の審査を評価する設計住宅性能評価書と、現場での審査を評価する建築住宅性能評価書の2つを合わせたものです。通常は設計住宅評価を行ってから建築住宅性能評価を行います。
また住宅性能評価書には住宅性能表示制度に基づく10項目の審査項目から、住宅の性能レベルを現場視察や図面によって評価を行っています。
住宅性能証明書
住宅性能証明書とは、住宅性能評価書における住宅性能表示制度に基づく10項目の内、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性に関する部分を抜粋して、現場視察や図面によって評価されたものになります。
その他の証明書類
①長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等
長期優良住宅とは、平成21年6月に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく、住宅を長く良い状態で長持ちさせるために決められた基準で設計・申請し、都道府県知事もしくは市町村長による認定を受けた住宅のことです。
この内容を証明するための書類が、長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等になります。
②認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅建築証明書等
認定低酸素住宅とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)における認定基準をクリアした建物の事を言います。
この内容を証明するための書類が、認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅建築証明書等になります。
まとめ
今回紹介した省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性に関する税制優遇措置は、現在の日本が抱えている地球環境・災害・高齢化社会といった将来の喫緊の課題と重なるものがあります。確かに贈与税が非課税になることは非常に魅力的なことですが、将来の世代のことを考えた上でこの制度が成り立っていることも、非常に大事なことだといえます。
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事