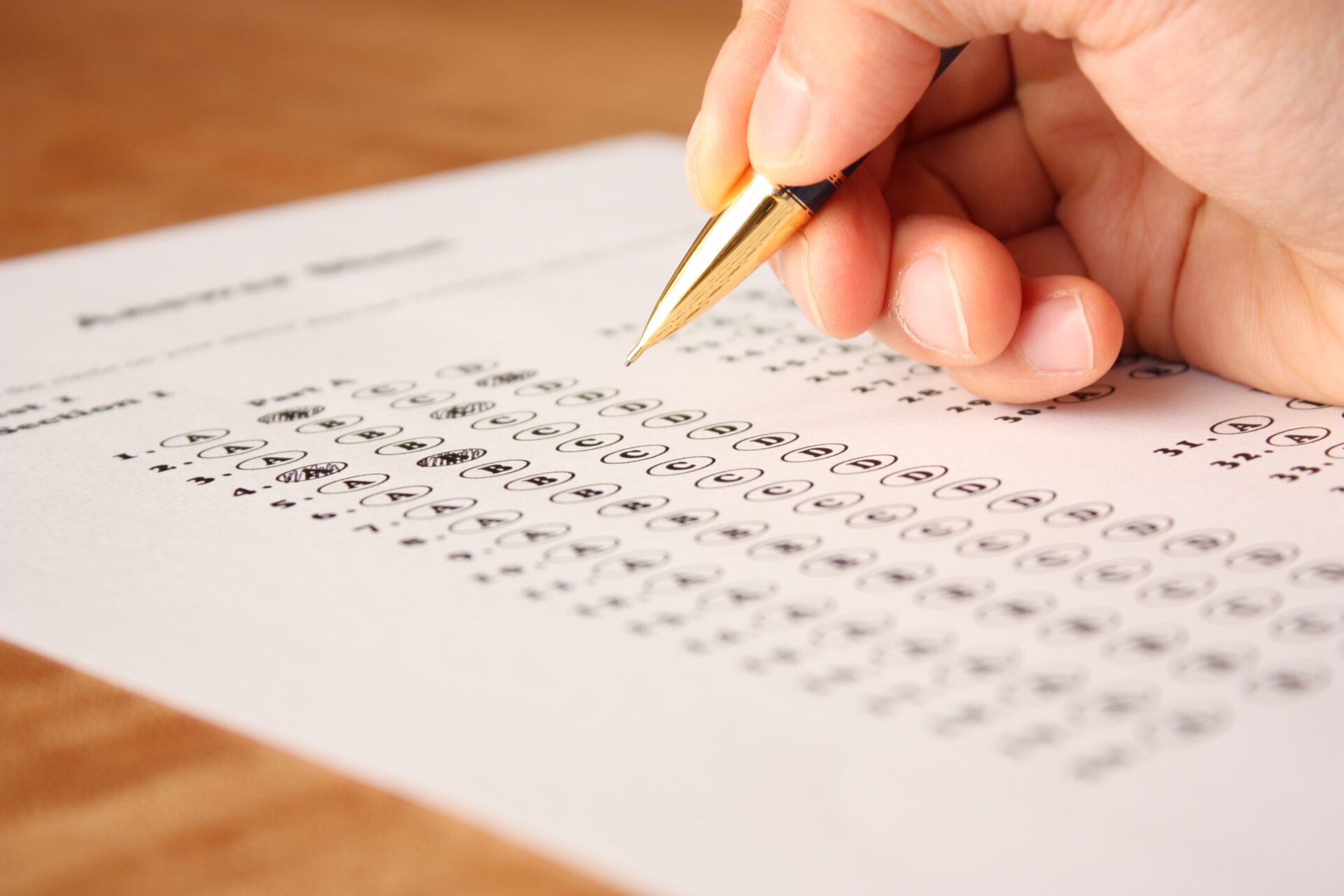建物区分所有法を解説|区分建物の共用部分・専有部分の違いとは

多くの世帯が1つの建物に暮らしているマンションでは、住人が仲良く暮らしていくためのルールが必要になります。
特に分譲マンションの場合には、そのルールは所有者の資産価値を左右するため、各所有者の権利を守るルールを定めておかなければいけません。
今回は分譲マンション等の管理や処分について定めている建物区分所有法について解説します。
Table of Contents
宅建受験者はここをチェック!

「建物区分所有法」の試験科目
権利関係
「建物区分所有法」が含まれる試験分野
建物区分所有法
「建物区分所有法」の重要度
★ ★ ★ ★ ★ 確実に出題される頻出項目です
「建物区分所有法」過去10年の出題率
100%
2020年宅建試験のヤマ張り予想
上記の出題率を見てわかるとおり、建物区分所有法に関する問題は100%の出題率となっている最頻出項目のひとつです。
2020年の宅建試験においても、まず確実に出題されると考えて間違いないでしょう。
特に共用部分の中でも法定共用部分と規約共用部分については、登記との関係性なども理解しておく必要があります。
「建物区分所有法」の解説

建物区分所有法について説明する前に、まずは建物区分所有法の対象となる区分建物とは何かを説明します。
区分建物とは
1つの建物の中で区分けされている部分を住居用に販売・購入・使用できるものを区分建物と言います。
区分建物の例で一番わかりやすいのは分譲マンションですが、長屋やテラスハウスなども区分建物に分類されます。
形態がマンションであっても、賃貸用の収益物件など単独オーナーの建物の場合には区分建物ではありません。
区分所有者とは
区分建物の独立した部分を購入し、居住もしくは賃貸に出すなどして使用している人のことを区分所有者と言います。
区分建物の管理を行うために共用部分を所有している者のことは管理所有者と言います。共用部分・管理所有については後ほど詳しくご説明します。
建物区分所有法とは
マンション等の区分建物のルールを定めた法律が建物区分所有法です。
区分建物では「専用で使用する部分」と「共同で使用する部分」があるため、戸建ての単独所有者が持っている所有権とは別に考えなければいけません。
また、民法においては何らかの行為を行うには基本的に全員合意が必要です。しかし多くの住人が暮らすマンションでは、全員合意を得るのは非常に困難です。
そのため、民法とは違う区分建物独自の法律が制定されています。
マンション等の区分の仕方

区分建物は以下の2つに分けられ、区分所有者は2つのそれぞれについて権利と義務を持っています。
- 専有部分
- 共用部分
上記の2つについて詳しく見ていきましょう。
専有部分
例えば「203号室」など、マンション等の建物の中でも独立している区画のことを専有部分と言います。
専有部分が専有部分として認められるためには、以下2つの独立性があることが条件となります。
| 構造上の独立性 | 区画の上下左右との境が壁・床・天井などで仕切られている |
| 利用上の独立性 | 外部に直接通じる出入口が存在する |

画像引用:LIFULL HOME’S|専有面積とは?一人暮らしではどのくらい必要?一級建築士が詳しく解説
共用部分
マンション等のエントランス・階段・エレベーター・共同ゴミ捨て場など、住人が共同で使用する部分を共用部分と言います。
さらに、共用部分は以下2種類に分かれます。
| 法定共用部分 | 建物の基礎・土台・エレベーター室など、建物の構造上必須な部分 |
| 規約共用部分 | 管理人室・集会室・駐車場など、規約により共同使用することを定めた部分 |
共用部分の所有形態と管理

共用部分はマンション等の住民すべてが使用する場所ですが、所有権はそれぞれの専有部分所有者が持ち合っています。
その割合は1棟の建物の中で専有している区画の床面積によって決まります。つまり3LDKなどの大きめの区画を所有している人は、ワンルームなどの小さめの区画を所有している人よりも共用部分の専有面積も大きくなります。
専有面積における床面積を計算する場合には、区画の内側線で区切られた内法面積(うちのりめんせき)を使って算出します。

画像引用:LIFULL HOME’S|専有面積とは?一人暮らしではどのくらい必要?一級建築士が詳しく解説
共用部分の登記
法定共用部分はもともとマンション等を購入する目的にはならないため、所有権に関する登記を行うことはできません。
規約共用部分については規約で定めなければ専有部分にもなり得る区画なので、所有者を定める登記が必要です。登記しないと第三者に権利を侵害されても対抗できなくなります。
共用部分の管理
共用部分の所有は専有部分の所有に従います。専有部分の所有者は、床面積によって按分された共用部分の持分だけを売却等により処分することはできません。
また、共用部分の管理を円滑にするために、一部の区分所有者や管理者を所有者にすることもできます。管理行為のために共用部分の所有を行う人を管理所有者と言います。
管理所有者は共有部分の管理を行う義務があり、その報酬として区分所有者に対し管理費用の請求する権利があります。また軽微な変更であれば共用部分の変更行為も可能です。
「建物区分所有法」に関連する法律
この項目に関連する法律は以下のとおりです。
| 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 |
実際に過去問を解いてみよう
問題:
各共用者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共用者数で等分することとされている。(平成28年度本試験 問13より抜粋)
答え:×(等分ではない)
解説
各共有者の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります。共有者数で等分はされません。
「建物区分所有法」ポイントのまとめ
この項目で押さえておくべきポイントは以下のとおりです。
- 1棟の独立した部分を複数が所有し住居等に使用する建物を区分建物と言う
- 区分建物は専有部分と共用部分に分けられる
- 共用部分には法定共用部分と規約共用部分とがある
- 共用部分の持分は専有部分の内法床面積により按分される
最後に

分譲マンションは宅建業者としても取り扱うことが多い案件です。
建物区分所有法の目的や基本的な決まりをしっかり理解して、お客様の資産価値を正しく把握できるようにしましょう。
次の記事(区分建物の決まりを確認|規約・集会・管理・復旧及び建替えの条件とは)を読む
前の記事(財産の共有とは|各共有者の権利と義務・共有物の分割方法など)を読む
スペシャルコンテンツに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
宅建に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事