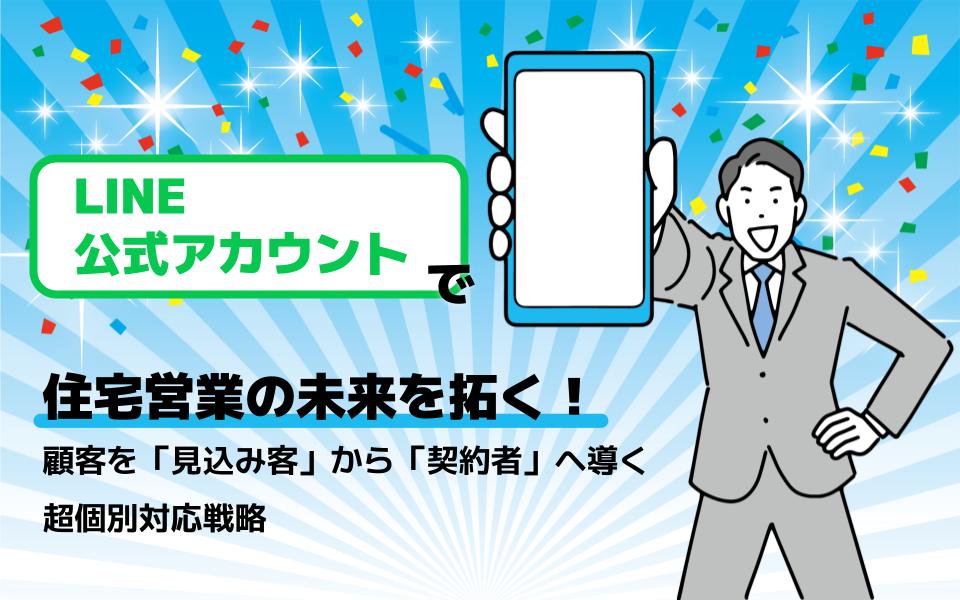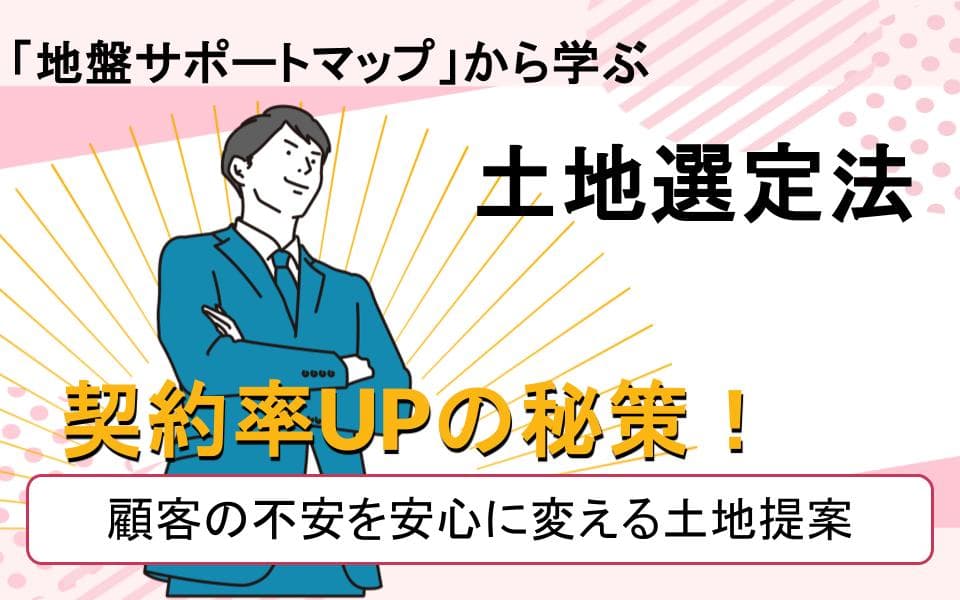【定義】工作物とは何なのか?確認申請の流れや建築物との違いを交えて解説

不動産には工作物と建築物があります。これらは名称が違うだけでなく、売買等の手続きに違いが生じます。両者の違いを把握して、買主様に正確に伝えることが大切です。また、工作物の所有権についても知っておくべきでしょう。
さらに一口に「工作物」と言っても、建築確認が必要なものと不要なものに分かれます。建築確認が必要な場合と手続きの流れについて、買主様に説明できるように理解を深めてください。
今回は、工作物の定義と建築確認の内容、確認手続きの流れについて解説していきます。
Table of Contents
工作物とは何なのか|建築物の違いも解説
不動産には名称によって様々な定義が存在します。その中でも「建築物」と「工作物」は、買主様にとって違いが分かりにくいものの1つです。
2つの定義の違いを解説します。
【定義】工作物とは
工作物とは、土地に密着させて設置した人工物で、建物以外のものを指します。
「建物以外」というのが重要なポイントであり、住宅やマンションは工作物とは呼びません。工作物の一例を、以下で紹介します。
| 立体的な工作物 | 道路、鉄道、ゴルフコース等 |
| 平面的な工作物 | 電柱、看板、堤防、トンネル等 |
後述する「建築物」や「建物」については建築基準法で明確に定義されていますが、工作物は定義されていません。
「建築物」でも「建物」でもないものが工作物だと言うことです。
【定義】建築物とは
建築物とは、工作物の中で一定の条件を揃えたものです。建築基準法で以下の通り定義されています。
| 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋[こせんばし]、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
引用:電子政府の総合窓口e-Gov|建築基準法第2条1項1条 |
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」は、建物のことを指しています。「これに附属する門もしくは塀~」は工作物を指します。
つまり、「建物」と「工作物」を合わせたものが、「建築物」です。
工作物と建築物の違い
建築物とは建物に加えて一定の工作物がついた状態であり、建築物の定義から外れた構造物は、全て工作物として扱われます。
遊園地にあるジェットコースターなどの遊具も、工作物としての扱いを受けます。
建築確認が必要な工作物
建築確認とは、工事の計画が建築基準法に適合しているかを確認する手続きです。工事に着手する前に確認申請を行い、建築主事または検査機関の確認を受けて建築確認済証の交付を受ける必要があります。
建築基準法で定義されていない「工作物」ですが、一定規模を超える場合には建築確認が必要です。
具体的には、「準用工作物」と「指定工作物」について確認申請が必要です。
準用工作物
以下の工作物は「準用工作物」と呼ばれており、建築確認が必要になります。
- 高さ6メートル超の煙突
- 高さ15メートル超の鉄柱、木柱等
- 高さ4メートル超の広告塔、記念塔等
- 高さ8メートル超の高架水槽・物見塔等
- 高さ2メートル超の擁壁
その他、一般交通用以外の観光向けエレベーター・エスカレーターや、遊園地のジェットコースター、観覧車、メリーゴーランドも準用工作物として建築確認の対象です。
指定工作物
建築基準法第88条第2項 建築基準法施行令第138条第3項では「用途規制が適用される指定工作物」として、以下の工作物が指定されています。
| 用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。
屋根を有するものや、屋根がなくても設置面からの高さが8mを超えるものは建築物として扱う)、及び処理施設位置の制限(法51条)を受ける汚物処理場、ごみ焼却場等 引用:電子政府の総合窓口e-Gov|建築基準法第88条2項 |
工作物の確認申請
ここでは、工作物の建築確認を行う場合の流れと必要書類について紹介します。
確認申請の流れ
建築確認申請は、以下のような流れで進みます。
- 自治体との事前協議
- 確認申請
- 審査
- 確認済証の受け取り
事前協議の問い合わせ窓口は、各自治体の「都市計画課」です。土地を管理する自治体が分かっていれば、「建築確認 〇〇市」と検索することができます。
必要書類
上記2番の「確認申請」の時に必要な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 部数 |
| 確認申請書 | 2部 |
| 設計図書 | 2部 |
| 確認申請時の添付書類一覧表 | 1部 |
| 建築計画概要書 | 1部 |
| 建築工事届 | 1部 |
工作物の設置許可基準
工作物の設置許可について、自治体ごとの条例で厳しく指定される場合があります。
具体的には、河川における法定外公共物管理条例に基づく工作物の新築・改築・除却について指定があります。
河川の管理上必要になる一般的技術的な基準を定めたものです。
自治体ごとに条例や基準の内容が変わってきます。詳しくは、各自治体のHPで確認してください。
参考として、静岡市の河川における工作物設置基準の解説資料を紹介します。
【参考:静岡市|静岡市法定公共物(河川)工作物設置許可基準・解説】
工作物の所有権
不動産の売買が発生した時、工作物の所有権が問題になります。
「土地を売却した場合」と「家屋を売却した場合」に分けて解説します。
土地を売却した場合
土地を売却した場合、土地の一部と認識されるものは土地と一緒に所有権が移転します。民法242条で「土地の附合物」として指定されているためです。
| 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。(動産の付合) |
難しく考えず、土地とくっついて取れないものは所有権が移転する、という理解で問題ありません。
例としては、以下のような「擁壁」が挙げられます。

家屋を売却した場合
家屋を売却した場合も、付随する塀や扉といった工作物の所有権は買主に移行します。「売却したのは建物のみだ」という主張をして、家の塀を改造したり除却したりすることはできません。
この場合も、前述の「民法242条」の考え方が用いられています。
まとめ
今回は、工作物の定義と所有権の所在、手続きの流れについて解説しました。建築確認が必要である工作物と不要な工作物の違いを理解し、買主様に正確に伝えることが不動産営業の使命です。
本記事のまとめ
- 工作物とは、土地に密着させて設置した人工物で、建物以外のもの
- 建築物とは、工作物の中で一定の条件を揃えたもの
- 準用工作物とは、「高さ6メートル超の煙突」「高さ15メートル超の鉄柱、木柱等」「高さ4メートル超の広告塔、記念塔等」「高さ8メートル超の高架水槽・物見塔等」「高さ2メートル超の擁壁」の特徴を持つ
設置許可基準等は、法令の改正によって内容が変更になることもあります。常に学習を続けて、知識をアップデートしてください。
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事