制限行為能力者とは|支援が必要な方の不動産取引における権利保護

「制限行為能力者」の科目では、判断能力が不十分な人の行為について法的にどう取り扱うのか学びます。宅建業務では多様なお客様の不動産取引に関わるため、きちんと学んでおく必要があります。
また、宅建士試験においては、出題率の高い「意思表示」の科目内容と関連が深いので、一連の問題として学習すると良いでしょう。
Table of Contents
宅建受験者はここをチェック!
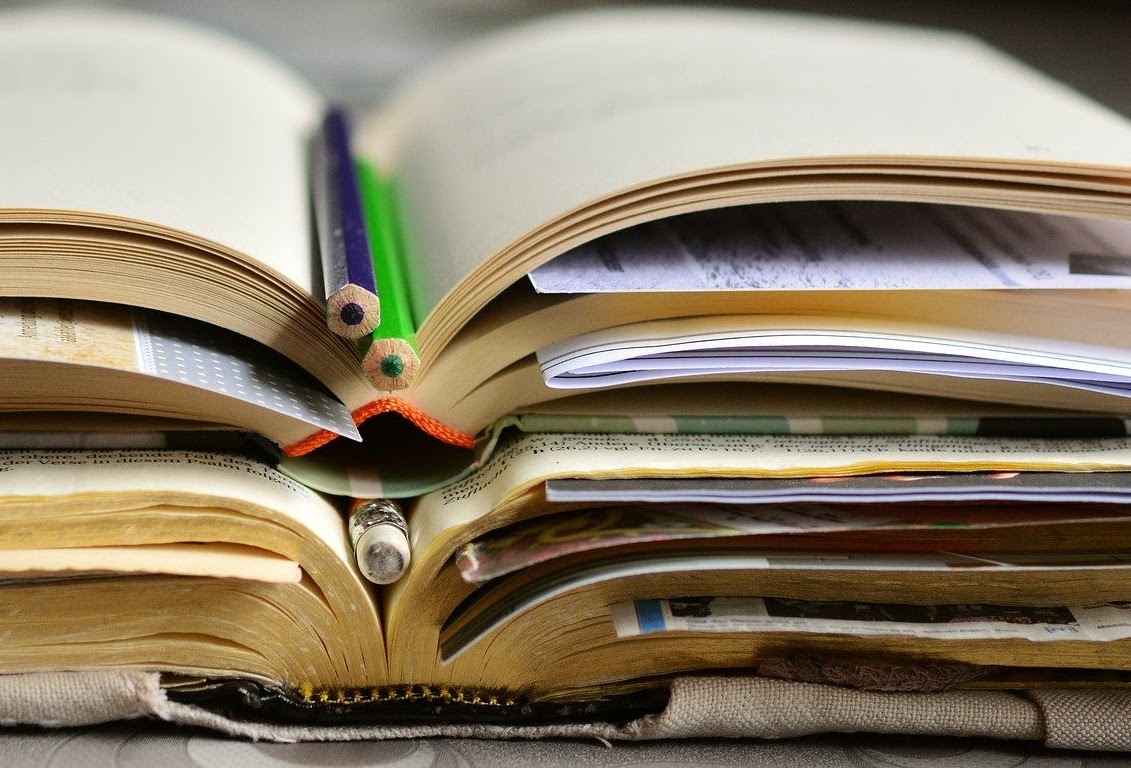
「制限行為能力者」の試験科目
権利関係
「制限行為能力者」が含まれる試験分野
制限行為能力者
「制限行為能力者」の重要度
★★★☆☆ 2020年は出る確率がやや高めです。
「制限行為能力者」過去10年の出題率
50%
2020年宅建試験のヤマ張り予想
本科目はほぼ隔年での出題が続いています。したがって平均出題率は50%です。
しかし、2019年は出題されなかったことから、2020年は出る確率がかなり高いと言えます。
「制限行為能力者」の解説
制限行為能力者制度とは
制限行為能力者制度とは、健常な成人と比べて判断能力が不十分であると考えられる人(制限行為能力者)が法律行為において不利益を被らないように、その権利を保護する制度です。
制限行為能力者には、未成年者や精神障害者などが含まれます。
この制度では、制限行為能力者が単独で行った法律行為について、一定の条件を満たせば取り消すことができます。このとき、行為相手の動機が善意か悪意かは問われません。
また、制限行為能力者の保護者に一定の権利を与え、本人の代理・保護の役割させることとしています。
◆制限行為能力者の種類
- 未成年者(未婚者に限る※)
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
※婚姻している未成年者は、成年者と同等に扱われるため(成年擬制)、制限行為能力者制度の保護対象外となります。
未成年者の権利保護

未成年者(20歳未満の未婚者)は、保護者の同意を得ていない単独の法律行為について、本人または保護者によって後から取り消すことができます(取消権)。逆に、未成年者の未来の行為に同意を与える権利も、保護者には認められます(同意権)。
また、未成年者単独による行為が本人にとって有利な契約である場合には、行為の後から保護者がそれを認めて有効にすることができます(追認権)。さらに、本人の代わりに契約を行う権利(代理権)も認められます。
◆取消せない未成年者の行為
- 保護者の同意を得ている行為
- 保護者の同意を得て行う営業行為(例:商品の売買・仕入れなど)
- 保護者からもらい受けた一定の財産で行う行為(例:おこづかいなど→自由に使用・処分する同意を得ているとみなされる)
- 本人の利益・義務の免除となる行為(不利益から守る目的の法律であるため)
- 婚姻している未成年者による行為
成年被後見人の権利保護
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と定められています。つまり、常日頃から判断能力を欠く状態にある人という意味です。
成年被後見人の保護者は、成年後見人となります。成年後見人には、同意権がありません。なぜなら、同意があったとしても、行為時に成年被後見人に十分な判断能力があったとは断言できないためです。
そのため、例えば保護者に不動産を売却する許可を得ていて、実際に成年被後見人が売却した場合であっても、保護者の判断で後から取消すことができます。
成年被後見人の保護者には、代理権も与えられています。ただし、本人の自宅を売却する契約を代理で行う場合には、家庭裁判所の許可を得なくてはいけません。これには、保護者の権限濫用を防止する目的があります。
◆取消せない成年被後見人の行為
- 日常的な少額の消費行為(例:スーパーやコンビニで弁当を買うなど)
(民法第9条)
被保佐人の権利保護
被保佐人は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」と定義されています。被保佐人の保護者である保佐人は、家庭裁判所によって任命されます(保佐開始の審判)。
被保佐人は成年被後見人に比べて単独行為が認められる範囲が広くなります。そのため、取消権を行使できる範囲は狭くなります。
◆被保佐人が取消せる行為
- 元本の領収または利用
- 借金または保証人になること
- 不動産などの重要な財産に関する権利の売買
- 訴訟行為
- 贈与・和解または仲裁合意
- 相続の承認や放棄・遺産分割
- 贈与の辞退または遺贈の放棄
- 負担付贈与や負担付遺贈の承認
- 新築・改増築・大修繕など
- 一定期間を超える賃貸借契約(土地は5年、建物は3年)
- その他、家庭裁判所が決定した行為
被補助人の権利保護
被補助人とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」と定められ、被保佐人よりも判断能力が高いとされています。保護者である補助人に許可される取消権も限定的で、補助開始の審判の際に家庭裁判所で決定した特定の行為についてのみ取消すことができます。
特定の行為として設定できるのは、被保佐人が取消せる行為の範囲内です。
そして、本人以外の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。
各保護者の権限の違い
| 対象者 | 取消権 | 同意権 | 追認権 | 代理権 | |
| 未成年の法定代理人(親権者・未成年後見人) | 未成年者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成年後見人 | 成年被後見人 | ○ | × | ○ | ○ |
| 保佐人 | 被保佐人 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 補助人 | 被補助人 | △ | △ | △ | △ |
※△…家庭裁判所の審判により特定の行為について認められる。
行為相手の権利保護
制限行為能力者制度では、被保護者の権利を守るため、契約の取消権を認めています。しかし、契約相手にとっては大きな不利益となり、権利が十分守られないのであれば不公平です。そこで、一定の場合には契約相手の権利を保護する法律も定められています。
- 催告権…相手方は1ヵ月以上の期間を設けて、制限行為能力者の保護者や判断能力が回復した制限行為能力者に対して、行為の追認をするか確定し返答するよう催促することができます。期限内に返答しない場合には、追認したものとされます。ただし、被保佐人・被補助人の場合は、催告に返答しなければ、取消したとみなされます。
- 詐術…制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。

「制限行為能力者」に関連する法律
未成年の契約を扱うときにはどこに注意すれば良いのか、関連する条文を理解しておきましょう。
民法未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 |
「制限行為能力者」ポイントのまとめ
- 制限行為能力者が単独で行った行為について、原則として取消すことができるとし、相手方の善意・悪意を問われない
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない
- 未成年者が保護者の同意を得ずに単独で行った行為について、本人の不利益になる場合には取消権が認められる
- 成年被後見人の法律行為については、たとえ保護者の同意があったとしても取消権が認められる
- 被保佐人の行為については、不動産売買などの重要な法律行為であれば取消権が認められる
- 被補助人の行為については、家庭裁判所の審判で決定された行為のみ取消権が認められる
- 制限行為能力者の法律行為において、相手の権利も保護する目的で、相手に催告権が認められる
権利保護と公平さのバランスを理解する

制限行為能力者は弱い立場にある方が多いため、取扱いには慎重になる必要があります。
ただし、不動産取引においては相手も当事者であり、法律では一定の権利保護が認められています。権利の保護と公平さのバランスをとるには、法律を十分に理解しておくことが大切です。
また、宅建試験でも権利関係の科目は重要視されるため、その一分野としての「制限行為能力者について」を他の問題と合わせて学習しておきましょう。
次の記事(制限行為能力者とは|支援が必要な方の不動産取引における権利保護)を読む
前の記事(虚偽表示・錯誤による契約の有効無効と第三者への対抗|宅建試験の頻出項目)を読む
スペシャルコンテンツに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
宅建に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事

















