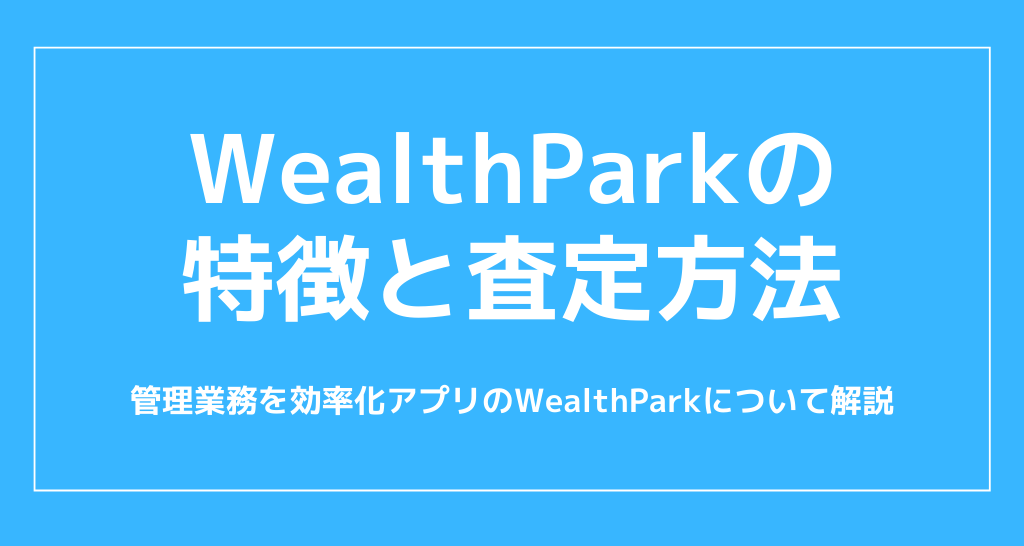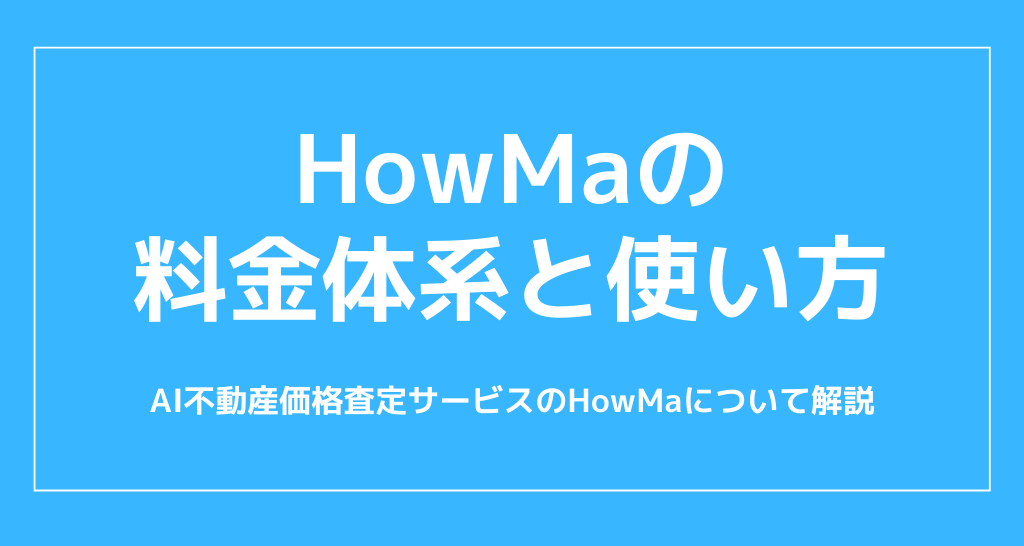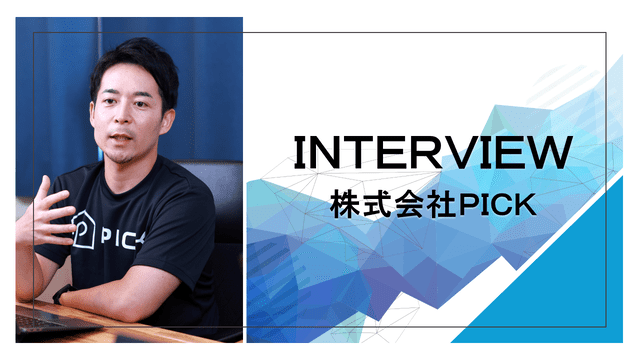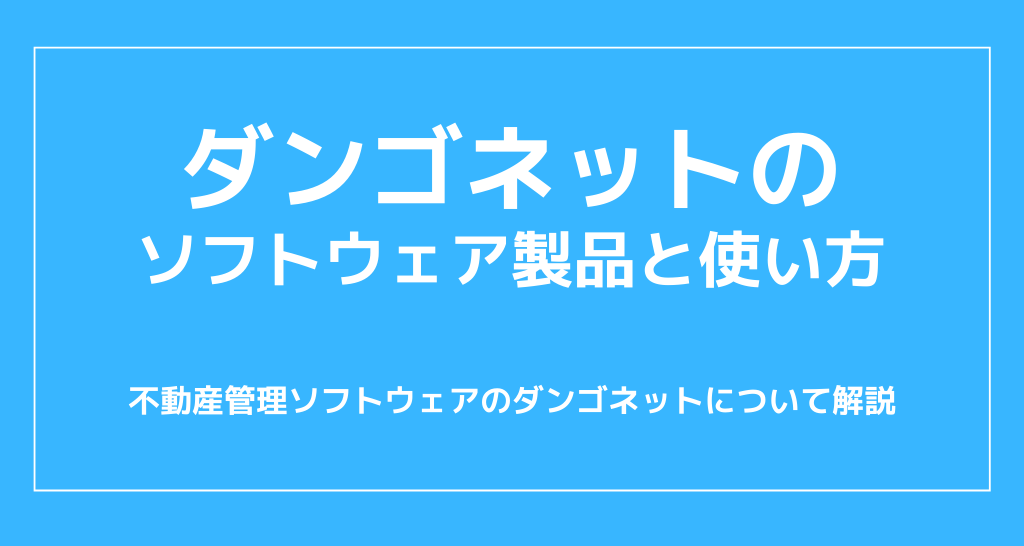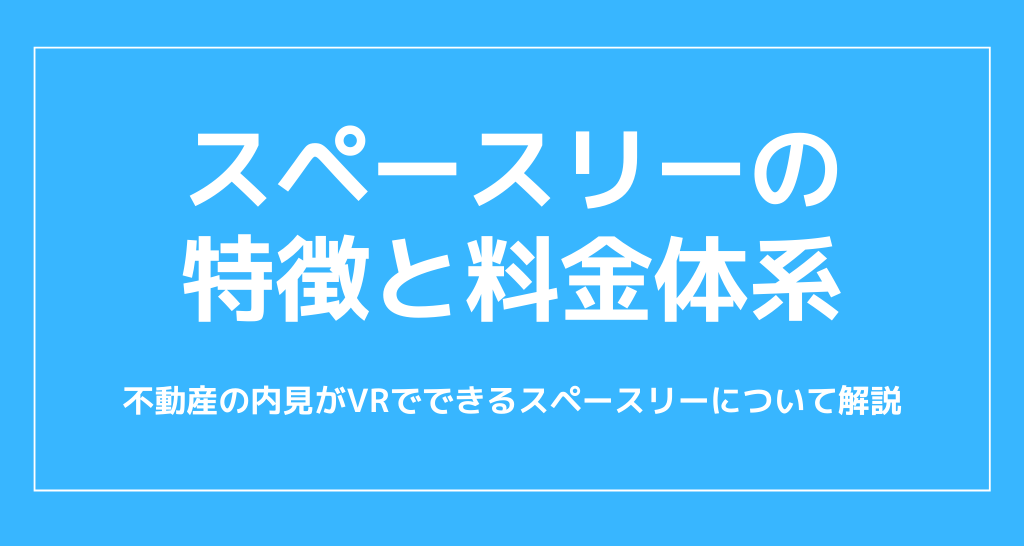【徹底解説】不動産売買のIT重説が全てわかる【2021年4月~】


「IT重説の意味がそもそもよく分からない」「ITオンチだから、かえって手間がかかりそう」
「今までの重説じゃだめなの?」
いきなり「IT重説」と言われても、戸惑う方は多いのではないでしょうか?
この記事では「IT重説」について、ITに苦手意識のある方にも分かりやすく解説していきます。
Table of Contents
IT重説とは?
「IT重説(アイティージュウセツ)」の意味がよく分からない、という方もいらっしゃるかと思います。
「重説」はご存じのように重要事項説明の略です。今までは、宅地建物取引士が「対面」で買主・借主の双方に重要事項の説明をしてきました。
従来の「対面」から、「非対面」の「IT」へ。
つまり、テレビ電話などのオンラインで行うことが可能になったのです。
「IT重説」2021年4月不動産売買で本格運用へ
2017年から実施可能になっていた、賃貸取引におけるIT重説。
社会実験を経て2021年4月、国土交通省は不動産売買においても「IT重説」を早急に本格運用する方針を明らかにしました。
コロナ禍&デジタル庁設立でニーズ急拡大
新型コロナウイルスの影響に加え、2021年9月デジタル庁発足などによって、社会はDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速しています。
各分野で、非対面化のニーズはますます高まるでしょう。不動産業界も例外ではありません
【IT重説】実施の流れを分かりやすく解説

IT重説の実施の流れを、要件と注意点に分けて解説します。
「IT重説」に必要な4つの要件
IT重説に必要な要件は4つです。
- 宅地建物取引士と買主、ともにやりとりできるIT環境が整っている
- 事前に「重要事項説明書」を送付している
- 説明開始前に買主に対して「重要事項説明書等の準備」と「IT環境の確認」をする
- 「宅地建物取引士証」を買主が画面から視認できたかを確認する
IT重説の実施には宅建士だけでなく、買主もやりとりが十分にできるIT環境が必要です。
IT重説では、買主に事前に重要事項説明書を送付します。
「PDFファイル」などによるメールでの送信は今のところ認められていないので、注意しましょう。
買主が重要事項説明書の内容をよく理解できるよう、送付から一定期間後に行うのが望ましいとされています。
IT重説開始前には、お互いの映像や音声を確認できること、重要事項説明書等が買主の手元にあるかの確認を行います。
買主が「宅地建物取引士証」を映像を通して確認できたかをチェックする必要もあります。宅建士の名前を読み上げてもらうなど、しっかり確認しましょう。
「IT重説」実施で押さえるべき4つの注意点
IT重説の実施で押さえるべき注意点は、主に以下の4つです。
- IT環境トラブルの場合は中断する
- 売主の同意を得る
- 内覧を実施する
- 録画・録音の対応をする
IT環境トラブルの場合は中断する
IT重説の実施中、映像や音声に支障をきたした場合は中断する必要があります。
国土交通省の「ITを活用した重要事項説明実施マニュアル」によると「社会実験における機器トラブルが生じた割合(売買取引)」は約10%で、約40%が音声トラブル、約30%が画像のトラブルという結果でした。
ネット回線の状況などを確認し、改善されれば再開が可能です。相手方の希望によっては、残りの部分を対面に切り替えることもできます。
売主の同意を得る
重要事項説明は、売主の個人情報が含まれることもあります。
個人情報保護の観点からも、売主など関係者の同意を得るのが望ましいとされています。
内覧を実施する
内覧をせずにIT重説を行った場合、イメージと違うなどの苦情やトラブルに発展する可能性もあります。
法的な義務はありませんが、内覧の実施を勧めることが望ましいでしょう。
録画・録音の対応をする
トラブルが発生した場合の解決手段として、録画・録音は有効です。
後で紹介する「Web会議ツール」には、録画・録音が手軽にできるものもあります。
不動産売買のIT重説におけるメリット・デメリット
IT重説におけるメリット・デメリットについて見ていきましょう。
「IT重説」のメリットとは
IT重説のメリットは、コロナ禍においても売買取引がしやすくなることでしょう。それ以外にも以下のメリットがあります。
- 遠方の方にも実施できる
- 病気やケガ、高齢の方にも実施しやすい
- 重説実施の日程の幅が広がる
遠方の方にとっては、時間や交通費の節約になります。
従来は代理人を立てる必要があった、病気やケガ・高齢で外出する体力がない方に対して直接オンラインで取引が可能です。
暑さが厳しい夏や大雨など天候が荒れた日に、自宅などで重説を受けられるのも大きなメリットと言えます。
重説実施の日程の幅が広がるのも、オンラインならではの特徴です。仕事で忙しいなど、日中なかなか時間を取れない方は時間を確保しやすいでしょう。
コロナ禍の状況下、感染リスクを抑えられるというメリットも重要です。
不動産業者としても業務の負担が軽減されたり、競合との差別化ができるなど、売買取引しやすくなると言えます。
「IT重説」のデメリットとは
IT重説のデメリットは、IT機器を利用するリスクや負担と言えるでしょう。
- IT環境の整備
- IT環境トラブルへの対応
IT重説では、パソコンなどの通信機器が必要となり、新たに導入する場合はコストがかかります。
IT機器を利用したやりとりの場合、通信トラブルは起こりうると考えた方がいいでしょう。音声が途切れたり、映像の映りがが悪くなったりすると、中断しなければいけません。
迅速に通信トラブルに対応できるスタッフがいない場合は、重説の再開に支障をきたしかねません。
通信トラブルを避けるためにも、性能の良い機器と通信状況を準備しておくことが重要です。
IT重説で使える!おすすめWeb会議ツール

Zoom Meetings
「Zoom Meetings」は利用者が急増しているWeb会議ツールです。一日の利用者数は2億人に達しています。
- 参加者(買主)の参加方法が簡単
- 録画保存はワンクリック
招待された参加者(買主)は、アカウントを作成する必要がありません。
Zoomを使ったことがない人でも、簡単に参加できます。
無料版でもWeb会議の録画保存をワンクリックで手軽にできるのは、Zoom Meetingsにしかない大きな特徴と言えます。
| Zoom Meetings | https://zoom.us/jp-jp/meetings.html |
Whereby
「Whereby」はノルウェーで開発されたWeb会議ツール、500万人以上のユーザーがいます。
- 有料プランが月額約800円
- インストール不要
今のところ日本語対応は行われてませんが、シンプル操作で簡単に利用できるはずです。
| Whereby | https://whereby.com/ |
Google Meet
「Google Meet」はGoogleが提供するWeb会議ツールです。
- 安全対策が継続的に更新
- クリアな映像と音声
「Google Meet」は。通信時に暗号化される他、保護強化のためにGoogleが実施するさまざまな安全対策が継続的に更新されます。
ネットワークの速度に応じて設定が自動調整されるので、どこでも高品質なビデオ通話ができるのもポイントです。
| Google Meet | https://apps.google.com/intl/ja/meet/ |
まとめ
Zoom Meetingsなど、IT重説で使えるおすすめのWeb会議ツールをご紹介しました。
2021年4月から本格運用となったIT重説は、非対面で行う重要事項説明のことです。IT重説を実施できる要件には、双方がやりとりできるIT環境などが必要です。IT重説特有の押さえるべき注意点も確認しておきましょう。
IT重説のメリットは、コロナ禍においても売買取引がしやすくなることが挙げられます。一方でデメリットは、IT機器を利用するリスクや負担と言えるでしょう。
「IT重説」でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。