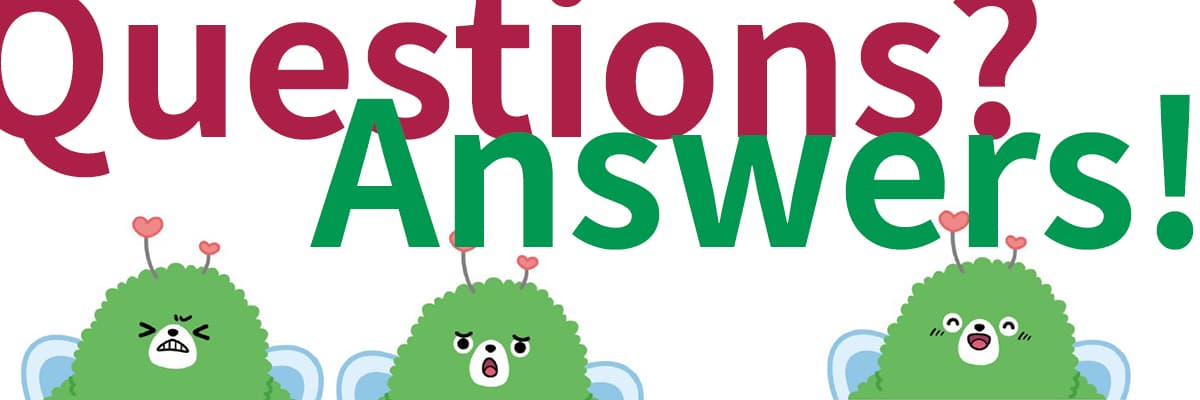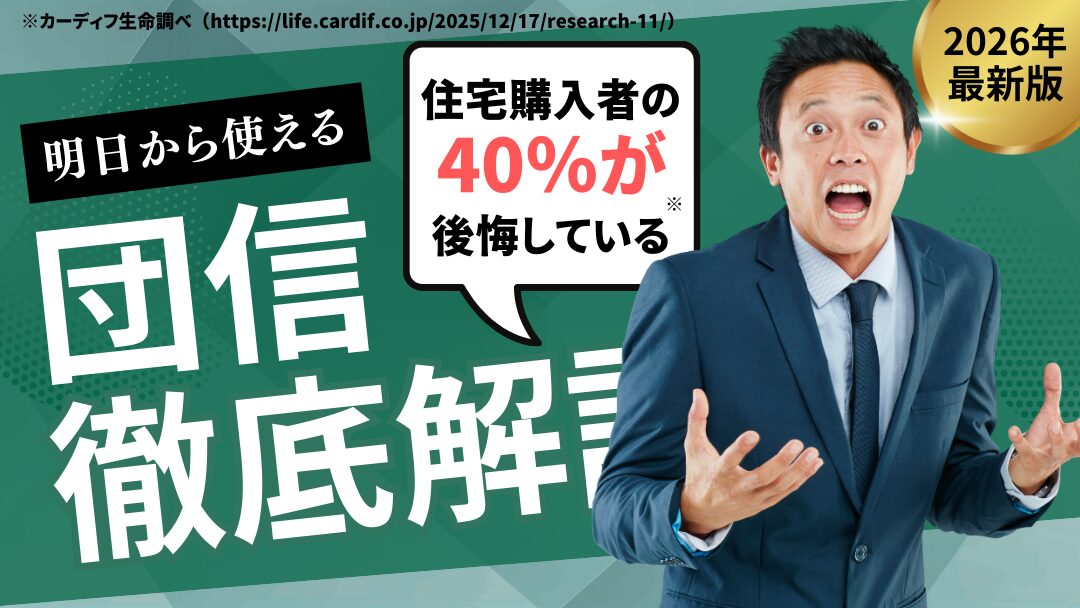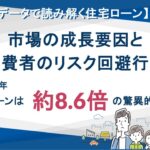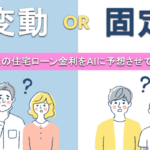団信の告知義務違反とは?お客さまが押さえるべき違反リスクと対策
【PR】投稿日 : 2025年11月11日

ネットの普及であらゆる情報が氾濫し、最近は団体信用生命保険(団信)の告知義務違反を軽く考えているお客さまが少なくないようです。
しかし、安易な告知義務違反によって団信契約が解除されれば、万が一のときに1円も保険金が支払われません。たった1つの嘘によって数千万円の保障が失われ、結果としてご家族の大切なマイホームを手放さざるを得なくなる可能性もあるのです。
そこで本記事では、不動産業界で働く人向けに、団信の告知義務違反の基本と発覚のタイミング、違反した際のリスクなどについて、告知義務違反が発生しやすい事例を交えて解説します。
Table of Contents
団信の告知義務違反とは?
お客さまが団信に加入する際は、健康状態を正しく保険会社に「告知」していただく必要があります。しかし、虚偽の申告や記載漏れなどがあると、引受保険会社によって「告知義務違反」とみなされることがあります。
【よくある告知義務違反の例】
- 告知が必要な持病や治療歴を意図的に書かない
- 入院・手術歴を投薬治療のみと書き、病歴を軽く見せる
- 複数の病歴の一部を省略する
上記のような行為によって団信に加入しても、告知義務違反が発覚すれば、残されたご家族はいざというときに必要な団信保障を受けることができません。では、どのようなときに違反が発生するのでしょうか。
告知義務違反が発覚するタイミング
多くの場合、告知義務違反が発覚するタイミングは団信の保険金請求時です。保険金請求の際に提出する死亡診断書や事故報告書には、団信被保険者(住宅ローン契約者・団信加入者)の詳しい死因が記載されています。過去の加入申込書兼告知書(告知書)と提出書類の内容に少しでも疑義があれば、保険会社は第三者機関に調査を依頼し、保険金支払いの可否を判断します。
調査では、告知時点の健康情報と実際の医療記録との照合が行われます。そのため、虚偽の告知で団信に加入しても、最終的には違反が発覚する可能性が高いと言えるでしょう。
したがって、「少しの隠し事やたった一つの嘘が将来大きなトラブルになり、残された家族を苦しめる可能性がある」ことを忘れてはいけません。
したがって、「少しの隠し事やたった一つの嘘が将来大きなトラブルになり、残された家族を苦しめる可能性がある」ことを忘れてはいけません。
告知義務違反による契約解除リスク
団信契約時のしおりには、告知義務違反によって団信契約が解除される可能性が記載されています。

※カーディフ生命保険株式会社 『被保険者のしおり』より抜粋し作成。
団信契約を解除された場合、お客さまとご家族に想定される重大なリスクは下記の2つです。
万一の際に保険金が支払われない
団信契約が解除されると、万が一の事態が発生しても団信の保険金は支払われません。つまり、住宅ローン契約者が亡くなってもローンは残り、遺族が引き続き返済を続けることになります。遺族だけで住宅ローン返済の継続が難しい場合は、いずれ大切なマイホームを手放す判断も必要になるでしょう。
住宅ローンの一括返済を求められることも
民間の金融機関では、融資の条件として団信の加入を義務付けています。契約解除の事実が発覚すれば、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められる可能性があります。このとき一括返済に対応できる資金がなければ、マイホームを売却し、そのお金を返済資金に充当することになりかねません。
「告知義務違反は2年で時効」は本当?
保険会社が告知義務違反によって団信契約を解除できる期間は、多くの場合、契約のしおり(約款)で「責任開始日から2年」と定められています(保険法では5年)。
こうした情報をどこかで見聞きし、「違反をしても2年経てば契約は解除されないから大丈夫」と安易に考えるお客さまは少なくありません。
こうした情報をどこかで見聞きし、「違反をしても2年経てば契約は解除されないから大丈夫」と安易に考えるお客さまは少なくありません。
しかし、契約のしおりでは、“告知義務違反の内容が特に重大であれば、経過年数にかかわらず保険金が支払われないことがある”とも記載されています。

※カーディフ生命保険株式会社『被保険者のしおり』より抜粋
特に重大な違反内容とは、下記のような事例です。
- 現代の医療水準では治癒が困難とされる病気を隠していた場合
- 明らかに死亡リスクが高い病気であるにもかかわらず、告知書でその病歴を隠していた場合
遺族が「きっと故意ではなく、うっかりしていて記入を忘れただけ」と主張しても、保険金支払いを決めるのは保険会社です。お客さまやそのご家族もちろん、不動産関連会社やローン借入金融機関の担当であっても、保険金支払いの妥当性は判断できません。
告知義務違反を防ぐ!お客さまが告知書を記入する際の注意点
団信はお客さまの大切なマイホームを守るために欠かせない保障です。お客さまがご自身の健康状態を隠して団信に加入しても、最終的に残された家族が保障を受けられないのであれば、団信の意義がありません。
お客さまが団信の告知書を記入する際の基本的な注意点は以下の3点です。
お客さまが団信の告知書を記入する際の基本的な注意点は以下の3点です。
”ありのまま”を”正確に”書く
告知書はありのままの事実を正確かつ詳細に書く必要があります。おぼろげな記憶を頼りに書いてしまうと、意図せず告知義務違反をしてしまう恐れがあり、有事の際に大切な団信保障を受け取れません。
そのようなことがないよう、告知の際は下記のような医療記録を参考にしてください。
そのようなことがないよう、告知の際は下記のような医療記録を参考にしてください。
<参考になる医療記録の例>
- 医療機関で発行される医療費の領収書、診療明細書
- 加入先健康保険から発送される「医療費のお知らせ」
- 自身のお薬手帳
- 健康診断・人間ドック・各種検診の結果通知書
- 手術を受けたときの同意書・説明書や入院時の入院診療計画書など
- 医師に作成してもらう診断書
- 障害者手帳
- マイナポータル※の診療・薬剤情報
- ※マイナンバーカードと利用者登録が必要
手元に記録がない場合、加入先の健康保険で「医療費のお知らせ」を再発行してもらうか、医療機関に直接問合せる方法があります。
お客さまがマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナポータルを利用する方法もおすすめです。事前の利用者登録は必要ですが、マイナポータルであればご自身の診療・薬剤情報を一括照会できます。複数の傷病歴がある場合でも告知書の記入をスムーズに進められます。
正式名称を書く
病気やケガ、薬の名前は、診療明細書などに記載されている正式名称を記入しなければなりません。
ケガであれば部位を、薬の処方があれば種類や量なども細かく書いていただく必要があります。
告知書記入時、お客さまは「審査を早く受けたい」と気がせいている状態かもしれません。しかし、急ぐばかりで正式名称を確認せず、情報が不十分なままの告知書を出しても、却って引受保険会社の審査に時間がかかることがあります。追加の告知や健康診断書を求められ、結果として必要な期日までに融資されないなど、重大なトラブルに繋がりかねません。
また、情報が不十分なために正確な病状が伝わらず、否決になってしまったり、後で告知義務違反とみなされたりする恐れもあります。このように、焦って正確性に欠ける告知をしても、何もよいことはありません。適正な審査を受けて必要な団信保障を得るためにも、正式名称で書くことが必要です。
自己判断しない
営業現場でお客さまから告知書の書き方で質問を受けたときは、自己判断せず、引受保険会社に確認していただくようにしましょう。
お客さまから質問をされれば「何とか回答してあげたい」と思うかもしれません。しかし、銀行代理業ではない不動産関連会社の立場では、健康状態や傷病歴について具体的な記入を助言することはできません。審査結果にも関わるため、告知書の書き方は引受保険会社に直接確認していただくようにしてください。
「この病気は告知項目でどう書けばよいのか」「この症例は告知項目に該当するのか」という疑問をぶつけられたときは、決して回答せず、お客さま自ら引受保険会社に直接確認するようにご案内ください。問合せ先は契約のしおりに記載があるため、お客さまサポートの際に活用してください。
営業現場で注意。告知義務違反につながりやすいお客さまの声
営業現場において、お客さまと下記のようなやり取りがある場合は要注意です。告知義務違反を未然に防ぐため、対応にはくれぐれも気を付けてください。
「書き忘れていた病気がありました」
告知書を提出したばかりのお客さまから「書き忘れた内容がある」と口頭で伝えられても、不動産関連会社には告知受領権がありません。
保険会社は告知書の内容をもとに審査を行います。書き忘れがある場合は、お客さま自らが、金融機関や団信の引受保険会社に連絡することが求められます。
「ちょっとお薬をもらっただけなんですけど……」
告知書に書くかどうかは、病気の程度や薬の処方回数ではなく、告知項目に該当するかどうかで判断します。お客さまや不動産関連会社が告知の記載を判断できるわけではありません。
そのため、「具合が悪くて、1度だけ薬を処方してもらった」という軽微な状態であっても、告知項目に該当する場合は告知書への記入が必要です。
ただし、風邪や花粉症など、告知書であらかじめ除外が認められている病気は告知不要です。不明点は、告知書に記載されている引受保険会社のコールセンターなどに問い合わせることで解消できることがほとんどです。
「もう治っているので書く必要ないですよね」
一通りの検査や治療を終え、現在は病状が回復・完治している場合であっても、告知項目に当てはまれば記入が必要です。
過去に高血圧症と診断され、薬物療法や生活習慣の改善によって現在は血圧値が安定しているお客さまがいたとします。この場合、現在は薬の服用がなくても、3年以内に何かしらの診察・検査を受けていれば、下記の告知項目に該当します。
過去に高血圧症と診断され、薬物療法や生活習慣の改善によって現在は血圧値が安定しているお客さまがいたとします。この場合、現在は薬の服用がなくても、3年以内に何かしらの診察・検査を受けていれば、下記の告知項目に該当します。
【一般的な告知項目の一例】
- 告知日より過去3年以内にがんや高血圧症など、所定の病気で診察・検査・治療・投薬歴がある
繰り返しになりますが、告知書への記入を勝手に判断してはいけません。お客さまご自身が団信の告知書に記載の内容をよく読み、「ありのままを正確に」記入することが重要です。
まとめ
団信の告知義務違反はお客さまとご家族の将来だけではなく、営業担当や会社の信頼にも関わる重要な問題です。
【重要な3つのポイント】
- 告知書記入前に団信保障の重要性と告知義務違反のリスクをしおりで確認する
- 告知書はお客さまご自身で記録に基づく記入をする
- 不明点は必ず保険会社に確認を取る
お客さまが軽い気持ちで告知義務違反をした結果、その違反リスクを被るのは残されたご家族です。お客さまの大切なご家族とマイホームを守るために、お客さまご自身が告知の重要性を理解し、正しく告知することが重要です。
提供:カーディフ生命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社
 |
この記事の執筆者服部ゆい 金融代理店での勤務経験と自身の投資経験を活かしたマネーコラムを多数執筆中。 子育て中のママFPでもあり、子育て世帯向けの資産形成、ライフプラン相談が得意。 |