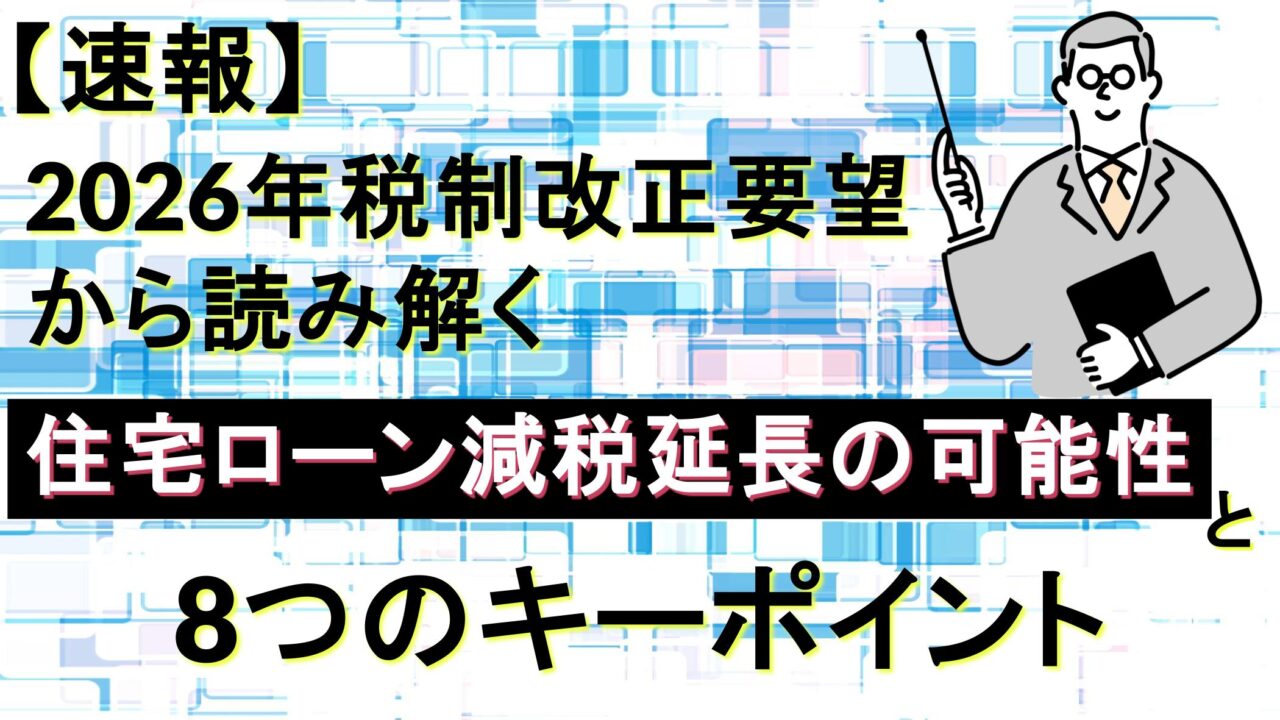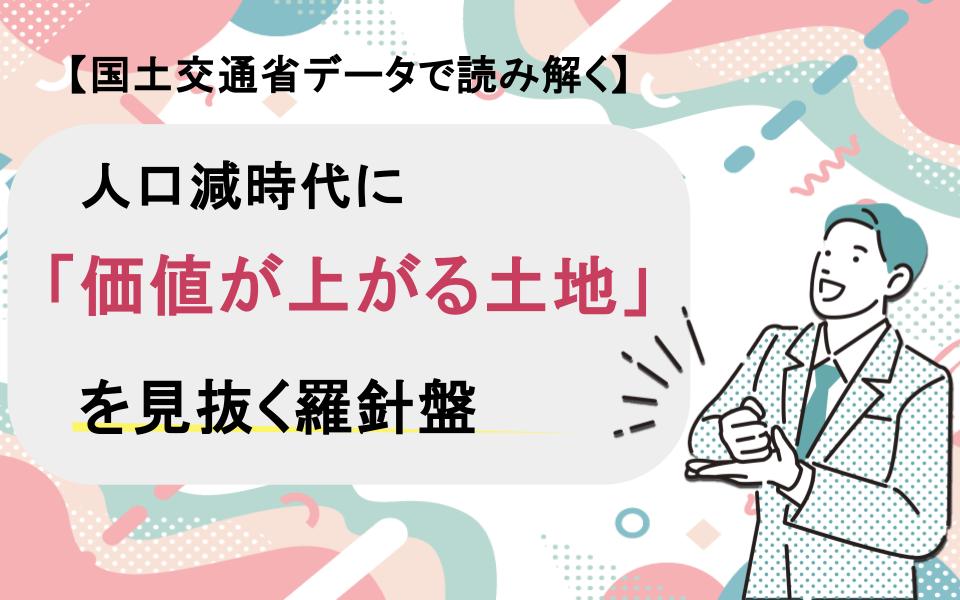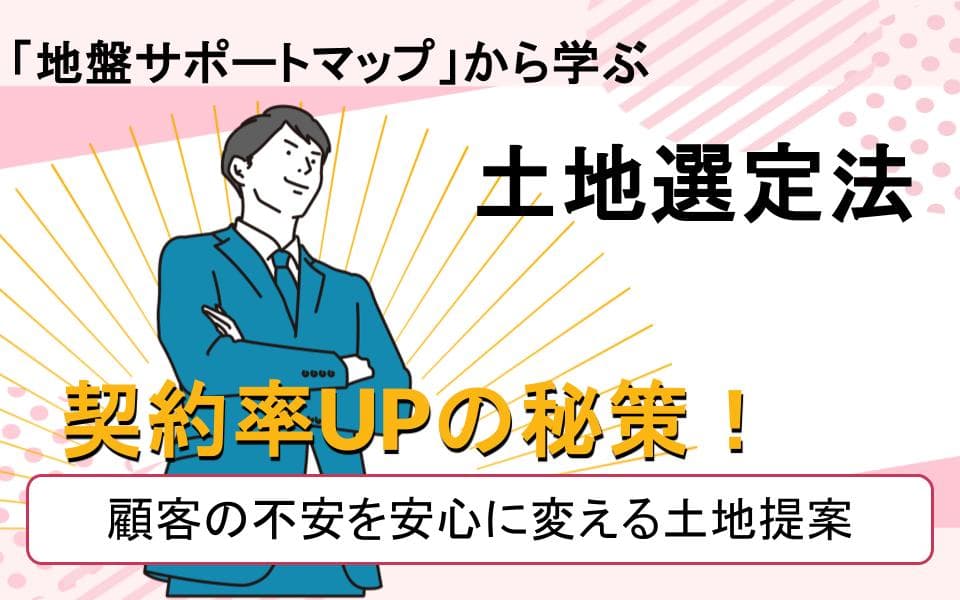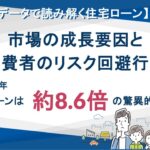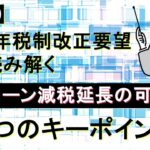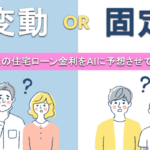たった15分で差をつける!「農地法」3条・4条・5条 完全マスター講座
更新日 : 2025年07月28日

住宅販売事業者の皆さん、農地法の許可制度は宅建試験だけでなく、実際の不動産取引においても非常に重要な知識です。特に、農地の売買や転用に関する3条許可、34条許可、5条許可の違いを正確に理解することは、お客様への適切なアドバイスや、法的なトラブルを避ける上で不可欠です。
この記事では、これらの許可の違いを、普段法律に馴染みのない方にも分かりやすく、具体的な事例と住宅販売実務での関連性を交えながら解説します。宅建合格、そして日々の業務に役立つ知識を習得しましょう。
Table of Contents
農地法とは?許可の必要性
農地法は、日本の貴重な農地が宅地などの他の用途に転用され続けることで起こりうる食料危機を防ぐことを目的とした法律です。この法律は、一定の農地を確保し、耕作者の地位を安定させるために制定されました。そのため、農地の利用者や利用方法を変更する際には、原則として国の許可を得る必要があります。
■「農地」の定義
農地法における「農地」は、登記簿上の地目(土地の用途を表す区分)に関わらず、現在、畑や田んぼとして実際に利用されている土地を指します。重要なのは、実際に農地として使われているかどうかという現状です。
農地法における「農地」は、登記簿上の地目(土地の用途を表す区分)に関わらず、現在、畑や田んぼとして実際に利用されている土地を指します。重要なのは、実際に農地として使われているかどうかという現状です。
- 含まれるもの:
- 現在耕作されている田んぼや畑
- 一時的に耕作を休んでいる休耕地
- 含まれないもの:
一時的な家庭菜園など、小規模で継続性のない利用
■「採草放牧地」も農地法の対象
農地と同様に、「採草放牧地」も農地法の適用を受けます。採草放牧地とは、主に以下のような目的で使われる、農地以外の土地を指します。
農地と同様に、「採草放牧地」も農地法の適用を受けます。採草放牧地とは、主に以下のような目的で使われる、農地以外の土地を指します。
- 耕作
- 家畜の放牧
- 家畜の餌や肥料を作るための採草
農地の権利移動(3条許可):農地を農地のまま売買
概要と目的
農地法第3条許可は、農地や採草放牧地を、そのままで売買したり、賃貸したりするなど、権利を移動させる際に必要となる許可です。具体的には、農地や採草放牧地について、所有権の移転や、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権、その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合に適用されます。
この許可の主な目的は、権利が移動した後も農地が適切に利用され続けることを確実にし、転売目的など不適切な権利移動による農地の荒廃を防ぐことです。農地法は、日本の食料自給のために農地を確保し、耕作者の地位を安定させることを目的とした法律です。

申請者と許可基準
申請者は、権利を取得する側(買主、借主など)です。ただし、許可申請は原則として当事者が連署した申請書を提出して行われます。
許可の判断基準としては、以下の点が考慮されます。
- 買受人がその農地を適切に耕作できるか。
- 周辺の農地の効率的な利用を阻害しないか。
事例
具体的なケースをいくつか見てみましょう。
■現役農家が農地を買い増すケース:
例えば、A農家がB農家から農地を購入し、引き続き農業を営む場合は、農地が農地のまま権利移動することに該当し、3条許可の対象となります。
例えば、A農家がB農家から農地を購入し、引き続き農業を営む場合は、農地が農地のまま権利移動することに該当し、3条許可の対象となります。
■新規就農者が農地を借りるケース:
Cさんが新たに農業を始めるために農地を賃借する場合も、使用収益権の移動に該当するため、3条許可が必要です。無償契約である使用貸借契約であっても同様に許可が必要とされます。
Cさんが新たに農業を始めるために農地を賃借する場合も、使用収益権の移動に該当するため、3条許可が必要です。無償契約である使用貸借契約であっても同様に許可が必要とされます。
住宅販売実務での関連性
一般の個人が将来的に宅地化を考えている農地を購入しようとする場合、耕作目的での取得ではないため、原則として農地法第3条許可は得られません。
農地は農地として利用され続けることが前提とされています。そのため、住宅販売事業者が「将来、宅地にできますよ」と安易に案内することは、農地法の趣旨に反する可能性があるため、十分な注意が必要です。
許可が不要な主なケース
以下の場合は、農地法第3条の許可は不要です。
- 国や都道府県が権利を取得する場合
- 遺産分割、相続、または離婚による財産分与によって権利が設定・移転した場合
- ただし、この場合も取得後に農業委員会への届出が必要です
- 抵当権を設定する場合
- 抵当権の設定は、使用収益権の移動を伴わないため、許可の対象外です
- 民事調停法による農事調停により権利を取得する場合
無許可行為の効力と罰則
農地法第3条の許可を受けずに売買契約などを締結した場合、その契約自体は無効となり、法的な効力は生じません。
また、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(法人の場合は1億円以下の罰金)。
自己転用(農地法第4条許可):自分の農地を自分で宅地にする
概要と目的
農地法第4条許可は、農地の所有者自身が、その農地を農地以外の用途(宅地や駐車場など)に転用する際に必要となる許可です。
この許可の主な目的は、日本の食料供給に欠かせない農地の無計画な転用を防ぐことにあります。これにより、食料生産量の維持を図り、日本の食料自給率への影響を防ぎ、さらに周辺農地の効率的な利用を妨げないことを目指しています。農地は食料生産の基盤であるため、その権利移動や転用は厳しく制限されています。農地法は、国にとって重要な資産である農地を保護することを目的としています。
申請者と許可権者・判断要素
申請者は、農地の所有者自身です。申請は農業委員会を経由して提出され、農業委員会は当該申請書に意見を付して都道府県知事等に送付します。
許可の判断は都道府県知事が行います。ただし、農林水産大臣が指定する市町村(「指定市町村」)の区域内では、その市町村長が行う場合もあります。これは、平成28年の法改正によって許可権者が都道府県知事に統一された上で、指定市町村長も許可権者に追加されたためです。
許可を判断する際には、農地の無計画な転用を防ぎ、食料生産量の維持を図り、かつ周辺農地の効率的な利用を阻害しないという農地法の目的に基づき、以下の点が考慮されます。
- 転用計画の実現可能性:
- 計画が確実に実行できるか。
- 周辺農地への悪影響の有無:
- 周囲の農地の利用に支障がないか。転用は、転用した土地の食料生産量低下だけでなく、近隣農地の効率的利用を阻害するおそれがあるため、より慎重な判断が必要です。
事例
具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 農家が自己所有の農地に自宅を新築するケース
- 農家が自己所有の農地の一部を駐車場にするケース
住宅販売実務での関連性
自己所有の農地を宅地化して住宅を建設・販売する際には、この農地法第4条許可が必須となります。
特に、市街化区域外の農地を宅地にする場合は、原則として4条許可が不可欠です。許可を得ずに工事を進めると、工事停止命令や原状回復命令などを受けるリスクがあります。

許可が不要な主なケース
以下の場合は、農地法第4条許可は不要です。
- 国や都道府県による転用の場合:
- 道路や農業用用水排水施設など、地域振興上または農業振興上の必要性が高い施設への転用目的の場合に該当します。
- ただし、学校や病院などへの転用目的の場合は、国または都道府県と都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなされます。
- 土地収用法により収用される場合:
- 市町村が道路、河川、堤防、水路などの公共施設に転用する場合。
- 自己所有の2アール(200平方メートル)未満の農地を農業用施設(畜舎、農業用倉庫、温室、サイロなど)に転用する場合。
- この特例は「2アール未満」の農地が対象であり、「2アール」ちょうどやそれ以上の場合は許可が必要です。
- なお、採草放牧地は4条の規制を受けません。
- 市街化区域内の農地を転用する場合:
- これは特例として、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、都道府県知事の許可が不要になります。市街化区域は都市計画が進んでいる地域であり、農地を転用するハードルが低いためとされています。
- ただし、この特例は農地法3条許可には適用されません。
無許可行為の効力と罰則
農地法第4条許可を受けずに農地を転用した場合、工事停止命令や原状回復命令を受けることがあります。
また、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。法人の場合は1億円以下の罰金が科されることがあります。
自己転用(農地法第4条許可):自分の農地を自分で宅地にする
概要と目的
農地法第5条許可は、農地または採草放牧地を、農地以外の用途に転用すること(例:宅地、駐車場など)を前提に、その権利を移動させる際に必要となる許可です。例えば、住宅建設のために農地を購入するケースなどがこれに該当します。
この許可の主な目的は、権利移動と転用が同時に行われることで発生する無計画な取引を防ぎ、食料生産や周辺農地の適切な利用を保護することにあります。
申請者と許可権者・基準
申請者は、買主と売主(または借主と貸主)の共同申請が原則です。ただし、民事調停法による調停が成立した場合など、一定の場合は連署が不要とされています。
許可の判断は都道府県知事が行います。ただし、農林水産大臣が指定する市町村(「指定市町村」)の区域内では、その市町村長が行う場合もあります。申請は農業委員会を経由して提出されます。
許可基準としては、以下の点が考慮されます。
- 転用計画の確実性:
- 転用計画が実現可能であるか
- 権利取得者の資力や信用:
- 適切に土地を管理・利用できる能力があるか
- 周辺農地への影響:
- 周囲の農地の効率的な利用を阻害しないか
- 土地利用規制との整合性:
- 都市計画などの他の土地利用に関する規制に適合しているか
事例
具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 宅地利用目的で農地を買い取るケース
- 住宅販売事業者が、分譲住宅を建てるために農地を取得する場合など
- 企業が工場建設のために農地を買い取るケース
住宅販売実務での関連性
農地を宅地として造成・販売する事業を行う場合、この農地法第5条許可は最も重要となります。
許可の取得には、転用計画の具体性や事業者の資力など、多くの要件が求められます。許可手続きには時間がかかることもあり、事業計画のスケジュールに大きな影響を与えるため、十分な計画とリスク管理が不可欠です。

許可が不要な主なケース
以下の場合は、農地法第5条許可が不要です。
- 国や都道府県が地域振興上または農業振興上の必要性が高い施設のために権利を取得する場合
- 土地収用法により収用される場合
- 市町村が道路、河川、堤防、水路などの公共施設に供するために取得する場合
- 市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合
- これも特例として、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、都道府県知事の許可が不要になります。
無許可行為の効力と罰則
農地法第5条許可を受けずに権利移動と転用を行った場合、その契約自体は無効となり、所有権移転の効力は生じません。
また、原状回復命令や工事停止命令を受けることもあり、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(法人の場合は1億円以下の罰金)。
農地法:3条、4条、5条許可の違い比較
農地法の3条、4条、5条許可は、それぞれ目的と対象となる行為が異なります。以下にその違いをまとめます。
| 許可区分 | 目的・対象となる行為 | 許可権者 | 無許可行為の効力と罰則 |
|---|---|---|---|
| 3条許可 | 農地を農地のまま他人に売却する(権利移動) | 農業委員会 | 契約無効 |
| 4条許可 | 農地の所有者自身が、その農地を農地以外の用途に転用する(自己転用) | 都道府県知事等(農業委員会経由) | 工事停止命令、原状回復命令、罰則 |
| 5条許可 | 農地を農地以外に転用することを前提に、その権利を他人に移動させる(転用目的権利移動) | 都道府県知事等(農業委員会経由) | 契約無効、工事停止命令、原状回復命令、罰則 |
※補足:3条許可については、市街化区域であっても必要となります。

過去問にチャレンジ
令和6年(2024年)
■問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
■選択肢
- 法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
- 法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
- 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
- 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
解説と解答のポイント
- 選択肢1(誤り)
- 農地法では、農地を売買するために農業委員会の許可が必要ですが、許可を停止条件とする「停止条件付き契約」に基づいて仮登記を申請する場合は、許可や届出は不要です。これは、正式な所有権移転登記の準備段階として仮登記が行われるためです。
- 選択肢2(正しい)
- 農地法第3条・第4条・第5条の許可申請は、原則として関係者全員(売主と買主、貸主と借主等)が一緒に署名した申請書(連署した申請書)を提出しなければなりません。ただし、競売や公売、遺贈、裁判の確定判決、調停や審判の成立による場合は連署が不要とされています。
- 選択肢3(正しい)
- 農地の賃貸借契約で期間の定めがある場合、契約期間が満了する1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと、契約は従前の賃貸借と同一の条件で更新されたとみなされます。ただし、期間については「期間の定めがない契約」として扱われます。
- 選択肢4(正しい)
- 農地や採草放牧地の賃貸借の契約解除等については、原則として都道府県知事の許可が必要です。これには契約の解除、解約の申し入れ、合意解除、更新拒絶の通知が含まれます。ただし、契約期間が10年以上の場合や、民事調停法による農事調停での合意解除の場合は許可が不要です。
令和元年(2019年)
■問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
■選択肢
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
解説と解答のポイント
- 選択肢1(正しい)
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 「原野」は農地ではないため、農地ではない土地を農地に転用する場合、農地法の許可は不要です。農地法の対象は「農地」および「採草放牧地」であり、現況が農地であるかどうかで判断されます。
- 選択肢2(誤り)
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 農地に抵当権を設定しても、使用収益権の移動には該当しないため、農地法第3条または第5条の許可は不要です。
- 選択肢3(誤り)
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 農地を農地以外のものに転用する行為は第4条許可の対象ですが、市街化区域内の農地については「市街化区域内の特例」が適用され、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば許可は不要となります。
- 選択肢4(誤り)
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
- 「貸し付ける」ことで「権利移動」が行われ、かつ「砂利採取」のために「転用」が行われるため、一時的な利用であっても農地法第5条の許可が必要です。
まとめ
農地法は、日本の食料生産を支える重要な法律であり、宅建試験においても「法令上の制限」分野で毎年出題される得点源となります。農地を「農地のまま売買する4条、5条許可の目的と手続きの違いを理解することは、宅建合格への道筋となるだけでなく、住宅販売の実務で農地が関わる取引を扱う際のトラブルを未然に防ぎ、お客様に適切な情報を提供するための基盤となります。ぜひ、この知識を日々の学習と業務に活かしてください。
┃いえーる 住宅研究所から最新情報をお届けします。
最新情報を一早くチェックしたい方は下記「登場する」からご登録ください。
最新情報を一早くチェックしたい方は下記「登場する」からご登録ください。