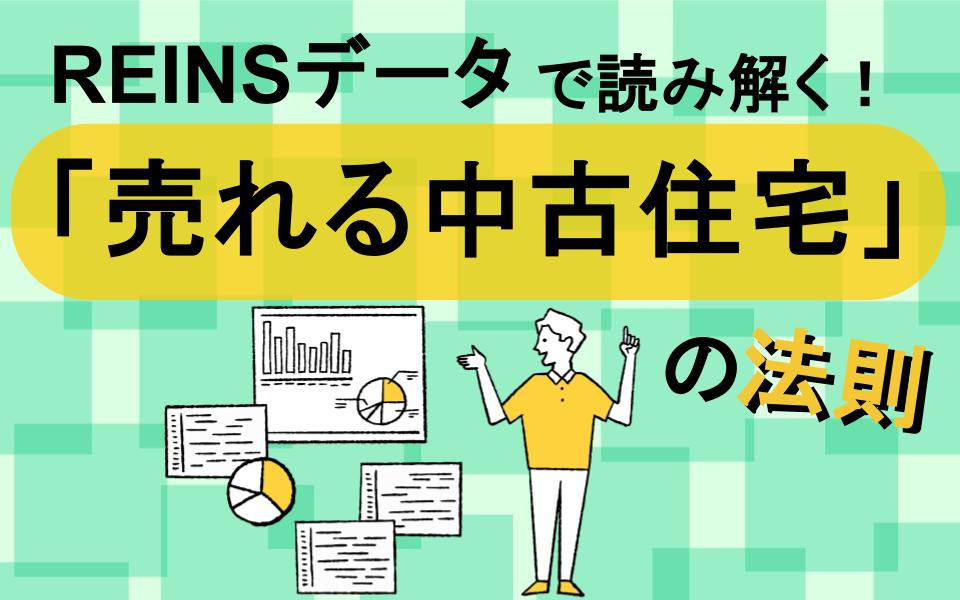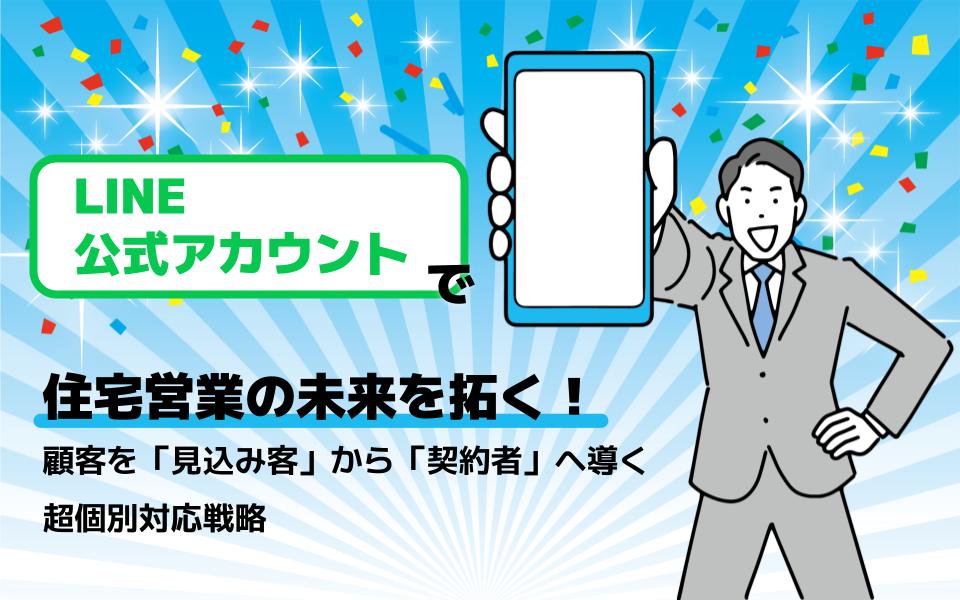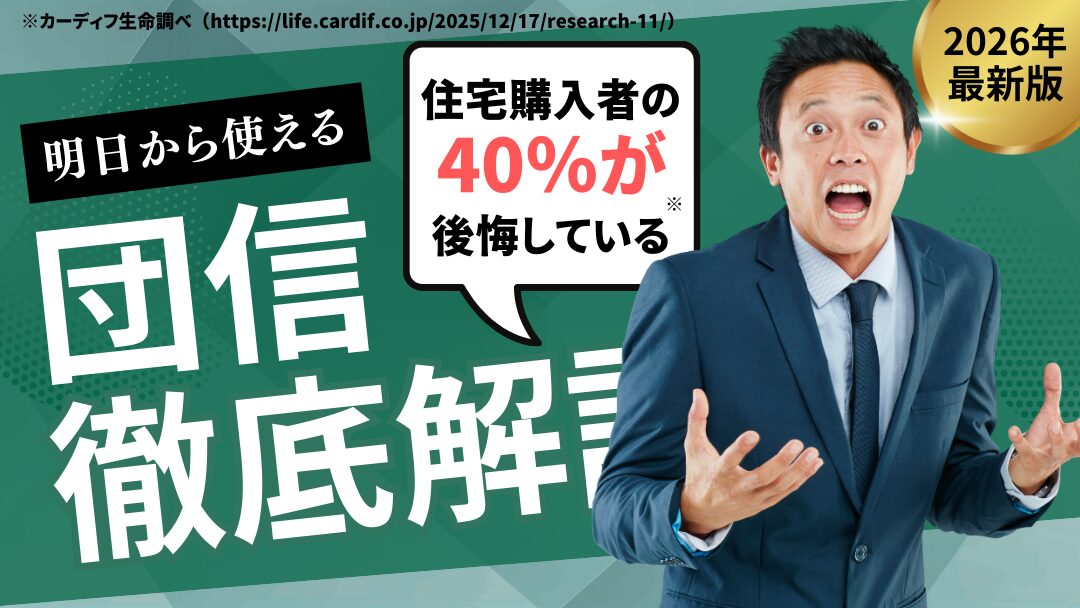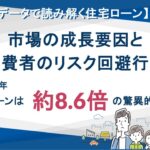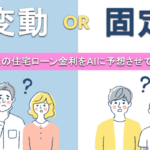2030年の住宅トレンドをAIが徹底予測! 5年後のビジネスチャンスを探る
投稿日 : 2025年07月11日

現代社会の急速な変化は、私たちの住まいにも大きな影響を与えています。5年後、2030年頃の日本の住宅はどのように変化しているのでしょうか。この疑問に答えるべく、本記事ではChatGPT、Gemini、Perplexity、Claudeという4つの異なるAIモデルに「5年後に流行る住宅トレンド」と「5年後に失われている住宅の既存トレンド」を尋ね、その計8つの予測資料を徹底的に比較分析しました。本記事は、提供されたAIの出力資料のみを根拠として分析しています。
テクノロジーの進化が著しい現代において、AIはもはや単なるツールではありません。特に予測能力においては、大量のデータからパターンを抽出し、未来の動向を推測する上で人間の能力をはるかに凌駕することがあります。住宅業界においても、市場の需要や消費者の行動、技術革新の方向性などをAIが予測することで、私たちはより精度の高い戦略を立てることが可能になります。
Table of Contents
なぜ今、AIによる住宅トレンド予測が必要なのか?
AIが予測する意義:データに基づいた未来洞察
住宅業界は、景気変動、人口動態、技術革新など、多様な要因に影響される複雑な市場です。これまで、これらのトレンド予測は専門家個人の経験や知識に頼る部分が大きく、客観性に欠ける場合がありました。
しかし、AIはインターネット上の膨大な情報や過去の市場データを瞬時に分析し、客観的かつ定量的な根拠に基づいた予測を導き出すことができます。これにより、私たちはあいまいな情報に惑わされることなく、確度の高い未来像を共有し、ビジネス戦略に落とし込むことが可能になります。
ビジネスチャンスを掴む:予測されるトレンドの活用法
AIが予測するトレンドは、単なる未来の絵空事ではありません。これらは、住宅販売事業者の皆様にとって、新たなビジネスモデルの創出、商品開発の方向性決定、マーケティング戦略の立案など、具体的なアクションに繋がる重要なヒントとなります。例えば、特定のAIモデルが「スマートホーム機能の普及」を強く予測している場合、関連する技術の導入や提携先の検討を加速させるべきでしょう。また、「郊外型住宅への回帰」が予測されれば、土地仕入れ戦略や販売エリアの見直しが必要になるかもしれません。
4大AIの個性と予測の傾向
AIへの質問方法と各AIモデルの「得意分野」
今回比較対象としたChatGPT、Gemini、Perplexity、Claudeは、それぞれ異なる学習データとアルゴリズムを持っています。そのため、同じ質問に対しても、それぞれが異なる視点や重点を置いて予測を生成する傾向が見られました。
いえーる 住宅研究所は、これらのAIモデルに以下の共通のプロンプトを用いて質問し、回答を収集しました。これにより、各AIがどのような情報に重きを置き、どのような視点で未来を予測するのかを比較分析しました。
■【流行る住宅トレンドのプロンプト(要約)】
「現在(2025年7月)から5年後の未来(2030年頃)において、日本で特に人気が出ると予測される住宅のトレンドを具体的に予測してください。予測の根拠は、インターネット上で公開されている情報のみとします。社会・ライフスタイルの変化、経済状況、技術進化、政府の政策・法規制の動向、災害リスク・気候変動への適応の5つの要素を総合的に分析し、具体的な住宅の特徴やコンセプト、機能、あるいは立地やコミュニティとの関係性に落とし込んでリスト形式で提示してください。」
■【淘汰される住宅トレンドのプロンプト(要約)】
「現在(2025年7月)から5年後の未来(2030年頃)において、日本で需要が大幅に減少している、あるいは完全に失われていると予測される既存の住宅トレンドを具体的に予測してください。予測の根拠は、インターネット上で公開されている情報のみとします。社会・ライフスタイルの変化、経済状況、技術進化、政府の政策・法規制の動向、災害リスク・気候変動への適応の5つの要素を総合的に分析し、どのような既存トレンドがなぜ失われるのか、具体的な住宅の特徴やコンセプト、機能、あるいは立地やコミュニティとの関係性に落とし込んでリスト形式で提示してください。」
■予測の根拠となった主要要素
- 社会・ライフスタイルの変化:
- リモートワークの定着、共働き世帯・単身世帯・多様な家族構成の増加、少子高齢化、健康意識・環境意識の高まり、趣味の多様化が、住宅に柔軟性、効率性、安全性、健康性、そしてコミュニティとの繋がりを求めるようになる
- 政策法規:
- 2025年以降の省エネ基準義務化、2030年までのZEH基準への引き上げ、GHG削減目標、防災・減災基準の強化などが、高性能化と安全性の向上を後押しする
- 技術進化:
- 5G/6G通信インフラ、AI、IoT、スマート家電、再生可能エネルギー技術の発展とコストダウンが、住宅のスマート化とエネルギー自給自足システムを可能にする
- 経済状況:
- 光熱費の高騰、インフレ、建設コストの上昇が、維持管理コストの低い省エネ住宅やコストパフォーマンスを重視した住宅への需要を高める
- 災害リスク:
- 地震・豪雨・台風の激甚化が、災害時も自宅で生活できるレジリエンスの高い住宅へのニーズを劇的に高める
上記のプロンプトに対し、各AIは以下のような傾向を見せました。
ChatGPT:
照明・空調・防犯・家電がIoTで連携し、AIが行動を学習し自動制御される住宅など、より具体的な機能的空間や技術の普及に焦点を当てた予測が目立ちます。職人頼みの伝統工法の衰退など、業界構造の変化にも言及しています。
照明・空調・防犯・家電がIoTで連携し、AIが行動を学習し自動制御される住宅など、より具体的な機能的空間や技術の普及に焦点を当てた予測が目立ちます。職人頼みの伝統工法の衰退など、業界構造の変化にも言及しています。
Gemini:
IoTデバイスとAIの統合による「賢い住まい」の普及、ZEHの標準化、災害レジリエンスの強化など、網羅的かつ具体的な技術革新とその背景にある社会の変化を深く掘り下げて予測しています。既存住宅の活用とリノベーションの高度化にも独自に言及しています。
IoTデバイスとAIの統合による「賢い住まい」の普及、ZEHの標準化、災害レジリエンスの強化など、網羅的かつ具体的な技術革新とその背景にある社会の変化を深く掘り下げて予測しています。既存住宅の活用とリノベーションの高度化にも独自に言及しています。
Perplexity:
IoT家電・設備による一元管理やAIによる居住者の行動予測・最適環境制御といった技術面に加え、高断熱・高気密構造の標準装備、モジュラー建築によるコスト削減など、実用性やコスト効率を重視した予測が特徴です。
IoT家電・設備による一元管理やAIによる居住者の行動予測・最適環境制御といった技術面に加え、高断熱・高気密構造の標準装備、モジュラー建築によるコスト削減など、実用性やコスト効率を重視した予測が特徴です。
Claude:
居住者行動予測AIによる自動環境制御、エネルギー消費最適化AIによる電力使用量自動調整など、AIとデータ活用に特化した詳細な予測が多い傾向です。コンパクト・高密度居住型住宅やデジタルツイン・データ活用型住宅といった、都市構造や情報技術の進化に焦点を当てた予測も特徴的です。
居住者行動予測AIによる自動環境制御、エネルギー消費最適化AIによる電力使用量自動調整など、AIとデータ活用に特化した詳細な予測が多い傾向です。コンパクト・高密度居住型住宅やデジタルツイン・データ活用型住宅といった、都市構造や情報技術の進化に焦点を当てた予測も特徴的です。
徹底比較から見えてくる2030年の住宅トレンド
全AIが共通して予測する「流行るトレンド」
複数のAIモデルが共通して予測するトレンドは、特に注目に値します。これらは、2030年における住宅市場の「主流」となる可能性が高いと考えられます。
■スマートホーム・AI統合型住宅:
全てのAIが、IoTデバイスとAIが住宅に深く統合され、居住者の行動パターンを学習し、照明、空調、セキュリティなどを最適に自動制御する「賢い住まい」の普及を予測しています。
全てのAIが、IoTデバイスとAIが住宅に深く統合され、居住者の行動パターンを学習し、照明、空調、セキュリティなどを最適に自動制御する「賢い住まい」の普及を予測しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- 照明・空調・防犯・家電がIoTで連携し、AIが行動を学習し自動制御される住宅 。スマート宅配ロッカーも標準装備されると予測
- Gemini
- IoTデバイスとAIが住宅に深く統合され、居住者の行動パターンを学習し、照明、空調、セキュリティなどを最適に自動制御する「賢い住まい」が普及する
-
- AIアシスタントが献立提案や在庫管理、健康管理までサポートすると予測
- Perplexity
- IoT家電・設備による一元管理(照明・空調・セキュリティ・エネルギー管理)やAIによる居住者の行動予測・最適環境制御、音声操作・遠隔操作・自動化の徹底
-
- 5G/6G対応による高速通信インフラも強調
- Claude
- 居住者行動予測AIによる自動環境制御(温度、湿度、照明、空気質)、音声認識・顔認証による玄関・室内セキュリティシステム、統合型ホームアシスタントによる家電・設備の一元管理
-
- エネルギー消費最適化AIによる電力使用量の自動調整
リモートワークの定着、共働き家庭の増加による「遠隔操作」「見守り」「節電」への関心の高まり、5G/6G通信インフラの普及、IT・AI分野の技術革新とコストダウン、高齢社会の進行による自動化・遠隔操作可能な住宅の需要増大、そしてIoT機器の導入率の上昇とMatter規格の普及が背景にあります。
Matter規格
AppleやGoogleなどが策定したスマートホーム共通規格で、異なるメーカーのIoT機器同士がシームレスに連携し、安全かつ簡単に操作できることを目的としています。

■ZEH・サステナブル住宅の標準化:
新築住宅においてZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)が完全に標準化され、高断熱・高気密構造、太陽光発電や蓄電池の導入が一般的になると予測されています。
新築住宅においてZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)が完全に標準化され、高断熱・高気密構造、太陽光発電や蓄電池の導入が一般的になると予測されています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- 高気密・高断熱、太陽光+蓄電池、パッシブ設計、地域材活用、水利用システム
-
- HEAT20 G2~G3水準/ZEH義務化に適合する住宅が標準化されると予測
- Gemini
- 新築住宅においてZEHが完全に標準化され、住宅の断熱性能が飛躍的に向上する
-
- 太陽光発電や蓄電池の導入が一般的になり、住宅自体がエネルギーを自給自足するシステムが普及すると予測
- Perplexity
- 高断熱・高気密構造、熱交換型24時間換気システムの標準装備、太陽光発電パネルと蓄電池の普及
-
- エネルギー消費量ゼロまたはマイナスを目指す設計
- Claude
- 断熱等級5以上が新築住宅の最低基準として義務化され、太陽光発電システムと蓄電池が標準装備されると予測
-
- 高性能窓(トリプルガラス・樹脂サッシ)の普及拡大と全館空調システムによる快適な室内環境の実現
2025年以降の省エネ基準義務化と2030年までのZEH基準への引き上げ、補助金や税制支援、環境・健康意識の高まり、光熱費高騰が主な要因です。

■防災・レジリエンス重視住宅:
住宅の耐震性、耐水害性、耐風圧性が一層強化され、停電対策として蓄電池やV2Hシステムが不可欠となり、災害時でも自立して生活できる機能が重視されるという点で各AIの意見が一致しています。
住宅の耐震性、耐水害性、耐風圧性が一層強化され、停電対策として蓄電池やV2Hシステムが不可欠となり、災害時でも自立して生活できる機能が重視されるという点で各AIの意見が一致しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- 制震・免震構造、太陽光+蓄電池+雨水タンク、停電・風水害対策が標準装備されると予測
- Gemini
- 住宅の耐震性、耐水害性、耐風圧性が一層強化され、停電対策としてZEH住宅の蓄電池やV2Hシステムが不可欠となり、災害時でも自立して生活できる機能が重視される
- Perplexity
- 耐震・耐水害・耐風圧設計、防火・断熱素材の採用、停電時の自家発電・蓄電池システム、防災設備(非常用井戸、多機能トイレなど)の標準化
- Claude
- 耐水害設計(浸水対策、排水システム強化)、停電時自立電源(大容量蓄電池、非常用発電機)、構造躯体の耐震性向上(免震・制震システム)、非常用備蓄スペースの確保
地震・豪雨・台風の激甚化による「災害時も自宅でしのげる」住宅ニーズの高まり、国による防災・減災基準強化、省エネ義務化も後押しとなっています。
AI間で異なる「見解」から探る潜在的ニーズ
一方で、AIモデル間で予測が分かれる点もまた、興味深い洞察を与えてくれます。これは、まだ顕在化していない潜在的なニーズや、地域性・ライフスタイルの多様性によって異なる需要が存在する可能性を示唆しています。
■ライフスタイル対応の可変型住空間:
全てのAIがライフスタイルの多様化とリモートワークの定着を背景に、柔軟な空間利用の必要性を認識しています。
全てのAIがライフスタイルの多様化とリモートワークの定着を背景に、柔軟な空間利用の必要性を認識しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- 「ランドリールーム」「ヌック」といった具体的な機能的空間に焦点
- Gemini
- より広範な「可変性のある空間」や「多目的で利用できる共有スペース」を強調
- Claude・Perplexity
- リモートワークに特化した空間の具体的な機能や、多世代・単身者への対応という視点を含む
これは、各AIが重視するトレンドの切り口や、ユーザーのニーズをどの程度具体的に捉えているかの違いに起因している可能性があります。

■健康・ウェルネス設計住宅:
ChatGPT、Claude、Perplexityの3つのAIが「健康」や「ウェルネス」に注目しています。
ChatGPT、Claude、Perplexityの3つのAIが「健康」や「ウェルネス」に注目しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- 空気質や素材に重きを置く
- Claude・Perplexity
- サーカディアンリズム対応照明やホームジム、メンタルヘルス配慮の空間設計といった、より生活に密着した要素を強調
これは、健康に対する消費者の意識が多岐にわたる中で、AIがどの側面に焦点を当てるかの違いを示唆しています。

■既存住宅の活用とリノベーションの高度化:
Geminiのみがこのトレンドを明確に挙げています。新築住宅着工戸数が長期的に減少傾向にある中で、既存の住宅ストックの価値向上が重要視され、耐震性や断熱性を向上させる大規模リノベーションが活発化すると予測しています。
Geminiのみがこのトレンドを明確に挙げています。新築住宅着工戸数が長期的に減少傾向にある中で、既存の住宅ストックの価値向上が重要視され、耐震性や断熱性を向上させる大規模リノベーションが活発化すると予測しています。
これは、新築中心の市場から既存住宅の活用へと政策が転換している背景をGeminiが特に重視しているためと考えられます。
■郊外・地方移住とコミュニティ志向の住まい:
Gemini、Claude、Perplexityの3つのAIがコミュニティや地方移住に注目しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- Gemini
- 都市部の住宅価格高騰やリモートワークの普及を背景に、子育て世代を中心に郊外や地方への移住ニーズが高まり、地域コミュニティとの繋がりや自然豊かな環境での生活を重視する価値観が強まると予測
- Perplexity
- 地域資源活用や地産地消型の建築、コミュニティスペースやシェア設備の充実
- Claude
- 多世代での居住形態や地域コミュニティとの連携、バリアフリー・ユニバーサルデザインの標準化
これは、人口減少や高齢化という社会課題に対するAIの視点の違いを反映している可能性があります。

■コンパクト・高密度居住型住宅:
Claudeのみがこのトレンドを挙げています。狭小地対応の高効率設計、縦方向活用による空間最大化、共用施設充実型マンションの進化、立地利便性重視の都市型住宅を特徴としています。住宅市場の縮小予測を踏まえ、効率的な土地活用と利便性の高い立地での住宅供給の重要性に特化した予測であると考えられます。
Claudeのみがこのトレンドを挙げています。狭小地対応の高効率設計、縦方向活用による空間最大化、共用施設充実型マンションの進化、立地利便性重視の都市型住宅を特徴としています。住宅市場の縮小予測を踏まえ、効率的な土地活用と利便性の高い立地での住宅供給の重要性に特化した予測であると考えられます。
■デジタルツイン・データ活用型住宅:
Claudeのみが住宅性能のリアルタイム監視、予防保全システムによる設備メンテナンス最適化、居住者行動データを活用した空間最適化、エネルギー使用パターン分析による省エネ提案を挙げています。
Claudeのみが住宅性能のリアルタイム監視、予防保全システムによる設備メンテナンス最適化、居住者行動データを活用した空間最適化、エネルギー使用パターン分析による省エネ提案を挙げています。
これは、IoT技術の発達とビッグデータ解析技術の進歩に着目し、住宅がデータを生成・活用する「スマートな建物」となる未来を具体的に描いているためと考えられます。
■建築コスト・経済状況への適応:
Perplexityのみがモジュラー建築や省施工化で工期短縮・コスト削減、リフォーム・リノベーション市場の拡大、賃貸住宅の多機能化・空室対策を挙げています。新築着工数の減少と建設コスト上昇という経済的な背景から、コストパフォーマンス重視の住宅が強まるという視点は、市場の現状をより強く反映している可能性があります。
Perplexityのみがモジュラー建築や省施工化で工期短縮・コスト削減、リフォーム・リノベーション市場の拡大、賃貸住宅の多機能化・空室対策を挙げています。新築着工数の減少と建設コスト上昇という経済的な背景から、コストパフォーマンス重視の住宅が強まるという視点は、市場の現状をより強く反映している可能性があります。
■流行る住宅トレンド 対比表(AIツール別)
トレンド分類ごとに各AIツールの回答を表にまとめました。
| トレンド分類 | ChatGPT | Gemini | Perplexity | Claude |
|---|---|---|---|---|
| スマートホーム | 照明・空調・防犯をAIが自動制御、宅配ロッカーも標準 | AIが献立・在庫・健康も管理 | 音声操作・遠隔操作・行動予測・5G/6G連携 | 音声・顔認証・環境自動制御 |
| ZEH・省エネ住宅 | パッシブ設計・HEAT20 G2〜G3対応 | 太陽光+蓄電池、完全自給型が主流に | 高断熱・熱交換換気+エネルギー消費ゼロ設計 | 断熱等級5+トリプル窓が標準に |
| 防災・レジリエンス | 制震・免震+停電対策+雨水利用 | V2HやZEH活用で災害時も自立 | 非常用井戸・トイレなどを標準装備 | 蓄電+発電+備蓄スペース確保 |
| 可変性・ライフスタイル対応 | ヌックやランドリールームなど機能特化空間 | 可変間取り+多目的共有スペース | シェア住宅+ガーデニング等の趣味空間+バリアフリー | モジュール間仕切り+趣味空間+Web会議対応 |
| ウェルネス・健康設計 | 換気・PM2.5・天然素材重視 | –(未言及) | 室内運動・空気清浄・自然光の最大化 | 照明・緑視率・空気質管理+ヨガ空間 |
| 既存住宅リノベ | –(未言及) | 大規模リノベと既存活用が進む | – | – |
| 地方移住・コミュニティ | – | 郊外移住+自然重視+地域連携 | 地域資源活用+コンパクトシティ連携 | 多世代住宅+バリアフリー+共有施設 |
| コンパクト住宅 | – | – | – | 狭小対応・共用施設強化・縦空間活用 |
| デジタルツイン住宅 | – | – | – | 予防保全+データ解析で最適化 |
| コスト適応型住宅 | – | – | モジュラー建築・省施工+多機能賃貸 | – |
5年後に失われている既存トレンド:淘汰される住宅様式
AIが予測する「需要の減少」
AIは、未来に流行るトレンドだけでなく、今後需要が減少していく既存の住宅トレンドについても示唆しています。これは、市場から撤退すべきビジネス領域や、改善・刷新が必要なサービスを見極める上で非常に重要です。
■断熱性能の低い住宅:
全てのAIが、単板ガラス窓、断熱材の薄い壁・屋根、気密性能C値5.0以上の住宅など、旧省エネ基準以下の断熱性能を持つ住宅の需要がなくなると予測しています。
全てのAIが、単板ガラス窓、断熱材の薄い壁・屋根、気密性能C値5.0以上の住宅など、旧省エネ基準以下の断熱性能を持つ住宅の需要がなくなると予測しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- 古い木造一戸建てや外断熱未施工
- Gemini
- 「夏は暑く、冬は寒い」といった室内温度が外気温に大きく左右される住宅
- Perplexity
- 高エネルギー消費型の冷暖房・給湯設備
- Claude
- 冬場の結露やカビが発生しやすい構造
2025年4月からの新築住宅への省エネ基準適合義務化、2030年までのZEH水準への引き上げ、光熱費の高騰によるランニングコスト意識の高まり、消費者の健康・快適性への意識の高まりが共通の背景です。

■固定的な間取りの住宅:
全てのAIが、夫婦+子供2人を前提とした4LDK固定間取りや、家族構成の変化に対応できない用途が固定された空間構成の需要が減少すると予測しています。
全てのAIが、夫婦+子供2人を前提とした4LDK固定間取りや、家族構成の変化に対応できない用途が固定された空間構成の需要が減少すると予測しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- 用途が固定された空間構成
- Gemini
- LDKが住宅の中心で広さを最優先する間取り
- Perplexity
- 標準的なファミリー向け間取りや独立した和室
- Claude
- 壁による完全な部屋分離やリビング・ダイニング・キッチンが独立した3点分離型
人口・世帯数の減少、単身世帯・多様な家族構成の増加、リモートワークの定着による柔軟な空間活用の必要性、家に「自分の場」が求められる傾向が共通の背景です。
■IoT・スマートホーム機能未対応の住宅:
全てのAIが、従来型の電気配線設備、手動操作のみの設備機器など、スマートホーム技術やIoT機能がほとんど搭載されていない「旧来型」住宅が淘汰されると予測しています。
全てのAIが、従来型の電気配線設備、手動操作のみの設備機器など、スマートホーム技術やIoT機能がほとんど搭載されていない「旧来型」住宅が淘汰されると予測しています。
<各AIが挙げた主な特徴>
- ChatGPT
- ネット設備が最小限(光回線なし、Wi-Fi弱い)
- Gemini
- 照明、エアコン、給湯器が個別に操作され連携機能がない住宅
- Perplexity
- AIアシスト機能がない住宅
- Claude
- インターネット接続機能のない住宅設備やセキュリティシステム未搭載
5G/6G通信インフラの普及とスマートホーム機能の標準化、高齢社会の進行による自動化・遠隔操作可能な住宅の需要の急速な高まり、快適性・利便性の追求と省エネ効果、防犯・防災機能の向上が挙げられています。
変化に適応するための戦略
これらの予測は、単に「なくなるもの」を示すだけでなく、私たちが変化にどう適応していくべきかを教えてくれます。例えば、画一的な住宅の需要が減少すると予測されるなら、よりパーソナライズされた住宅設計や、多様なライフスタイルに対応できるフレキシブルなプランニングが求められるでしょう。
■エネルギー効率の悪い設備機器を搭載した住宅:
Claudeのみが、従来型給湯器(効率80%以下)、単機能エアコン(APF4.0以下)、白熱電球やハロゲン電球の照明設備、24時間換気システム未搭載の住宅が淘汰されると具体的に予測しています。ZEHレベルへの引き上げや光熱費高騰といった背景から、設備機器単体のエネルギー効率に注目していると考えられます。
Claudeのみが、従来型給湯器(効率80%以下)、単機能エアコン(APF4.0以下)、白熱電球やハロゲン電球の照明設備、24時間換気システム未搭載の住宅が淘汰されると具体的に予測しています。ZEHレベルへの引き上げや光熱費高騰といった背景から、設備機器単体のエネルギー効率に注目していると考えられます。
■災害リスクの高い立地・構造の住宅:
Claude、Perplexity、Geminiの3つのAIがこのトレンドを指摘しています。液状化リスクエリア、耐震等級1のみの住宅、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内の住宅などが挙げられています。激甚化する自然災害、政府・自治体の防災・減災基準の強化と支援策、メディア・SNSによる情報拡散といった多様な側面から淘汰される背景が分析されています。
Claude、Perplexity、Geminiの3つのAIがこのトレンドを指摘しています。液状化リスクエリア、耐震等級1のみの住宅、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内の住宅などが挙げられています。激甚化する自然災害、政府・自治体の防災・減災基準の強化と支援策、メディア・SNSによる情報拡散といった多様な側面から淘汰される背景が分析されています。

■過度な装飾・設備を持つ住宅:
Claude、ChatGPT、Perplexityの3つのAIが、高級輸入建材、維持管理費の高い設備(プール、サウナ、エレベーター)、過度な造作家具・装飾、大型吹き抜けなど、維持管理コストが高い、あるいは過度な装飾を持つ住宅が淘汰されると予測しています。給料が上がらないことや建設コストの上昇、インフレと金利上昇によるランニングコスト意識の転換、費用対効果重視への消費意識の転換が共通の背景です。
Claude、ChatGPT、Perplexityの3つのAIが、高級輸入建材、維持管理費の高い設備(プール、サウナ、エレベーター)、過度な造作家具・装飾、大型吹き抜けなど、維持管理コストが高い、あるいは過度な装飾を持つ住宅が淘汰されると予測しています。給料が上がらないことや建設コストの上昇、インフレと金利上昇によるランニングコスト意識の転換、費用対効果重視への消費意識の転換が共通の背景です。
■郊外大型住宅:
Claudeのみが延床面積150㎡以上の大型住宅、車でのアクセスが前提の立地、公共交通機関からの徒歩圏外の住宅が淘汰されると具体的に予測しています。新設住宅着工戸数の長期的な減少予測や高齢化による車中心の生活からのシフトが主な理由であり、住宅市場の縮小というマクロな視点からの予測と考えられます。
Claudeのみが延床面積150㎡以上の大型住宅、車でのアクセスが前提の立地、公共交通機関からの徒歩圏外の住宅が淘汰されると具体的に予測しています。新設住宅着工戸数の長期的な減少予測や高齢化による車中心の生活からのシフトが主な理由であり、住宅市場の縮小というマクロな視点からの予測と考えられます。
■職人頼みの伝統工法による高コスト住宅:
ChatGPTのみが、大工技能に依存した高級伝統建築が淘汰されると予測しています。2030年までの大工職人の約半減予測や建設DX・プレハブ化推進、資材費・人件費の高騰といった具体的な業界動向を背景に、価格と施工可能性の面で伝統技術だけに依存する家が淘汰されると予測しています。
ChatGPTのみが、大工技能に依存した高級伝統建築が淘汰されると予測しています。2030年までの大工職人の約半減予測や建設DX・プレハブ化推進、資材費・人件費の高騰といった具体的な業界動向を背景に、価格と施工可能性の面で伝統技術だけに依存する家が淘汰されると予測しています。
■シックハウス原因=揮発性物質の室内ゼロ化が進まない住宅 / 換気・健康配慮のない住宅:
ChatGPTとPerplexityが、有害化学物質を発生させる建材(接着材・塗料など)を使用する住宅や、換気性能が低い、VOC対策が不十分な住宅が淘汰されると予測しています。健康志向の高まりやVOC・ホルムアルデヒド規制の強化、室内空気質への意識の高まりが背景にあります。
ChatGPTとPerplexityが、有害化学物質を発生させる建材(接着材・塗料など)を使用する住宅や、換気性能が低い、VOC対策が不十分な住宅が淘汰されると予測しています。健康志向の高まりやVOC・ホルムアルデヒド規制の強化、室内空気質への意識の高まりが背景にあります。

■用途特化型・孤立型コミュニティ住宅:
ChatGPT、Perplexity、Geminiの3つのAIがこのトレンドを指摘しています。子育て・高齢者向けなど用途が明確で閉鎖的なコミュニティ形成や、趣味や用途に特化しすぎた間取り、地域コミュニティや共用スペースを排除した住宅が挙げられています。趣味の多様化やテレワーク普及による「コミュニティ閉塞」の拒否、若者層の「閉じた同質集団」への拒絶感強化が共通の背景です。
ChatGPT、Perplexity、Geminiの3つのAIがこのトレンドを指摘しています。子育て・高齢者向けなど用途が明確で閉鎖的なコミュニティ形成や、趣味や用途に特化しすぎた間取り、地域コミュニティや共用スペースを排除した住宅が挙げられています。趣味の多様化やテレワーク普及による「コミュニティ閉塞」の拒否、若者層の「閉じた同質集団」への拒絶感強化が共通の背景です。
■淘汰される住宅トレンド 対比表(AIツール別)
トレンド分類ごとに各AIツールの回答を表にまとめました。
| トレンド分類 | ChatGPT | Gemini | Perplexity | Claude |
|---|---|---|---|---|
| 低断熱・非省エネ住宅 | 単板ガラス・外断熱なし・古木造住宅 | シングルガラス・断熱不十分・高エネ消費住宅 | 旧基準以下の高エネ住宅・給湯効率低 | 気密性能C値5.0以上・カビ結露多発住宅 |
| 固定的な間取り | 用途が限定された固定空間 | LDK中心・ファミリー前提間取り | 和室・子ども部屋前提・非フレキシブル | 4LDK固定型・壁分離・和室固定用途 |
| 非スマート住宅 | Wi-Fi弱く光回線なし | 機器が連携しない、セキュリティ旧式 | IoT/AI非搭載・遠隔操作できない | 手動操作・旧電気配線・セキュリティなし |
| 非効率な設備 | – | – | – | 白熱電球・旧式エアコン・非24h換気 |
| 災害リスク住宅 | – | 土砂・液状化・洪水リスク住宅 | 対策不十分・高リスク立地 | 耐震等級1・液状化エリア・備蓄なし |
| 豪華すぎる住宅 | プール・庭・高価格豪邸 | – | 大型住宅・維持費過大・装飾過多 | サウナ・輸入建材・造作過剰 |
| 伝統高コスト工法 | 職人依存・高級伝統工法 | – | – | – |
| 健康配慮がない住宅 | VOC含む建材使用 | – | 換気性能低・VOC対策不足 | – |
| 用途特化・閉鎖型住宅 | 子育て・高齢者特化型の閉鎖住宅 | 高齢者施設隣接のリゾート住宅等 | 用途限定住宅・共用拒否型 | – |
| 郊外大型住宅 | – | – | – | 延床150㎡超・車必須・公共交通外 |
総合的な5年後(2030年頃)の住宅トレンド予測まとめ
提供された8つのAI予測資料を総合的に分析すると、5年後の日本の住宅は、「高性能」「スマート」「柔軟性」「安全性」「健康」の5つの大きな潮流によってその姿を大きく変えることが確度の高い結論として導き出されます。
流行るトレンドと失われるトレンドの相互関係
「流行るトレンド」と「失われるトレンド」は密接に連携しています。
- 断熱性能の低い住宅やエネルギー効率の悪い設備が淘汰されることで、ZEHや高性能断熱住宅の標準化が加速します。
- 固定的な間取りの住宅が失われることで、多様なライフスタイルに対応するフレキシブルな住空間への需要が高まります。
- IoT・スマートホーム機能未対応の住宅が市場から消えることで、AIスマートホームの普及と進化が実現します。
- 災害リスクの高い住宅が敬遠されることで、災害レジリエンスが強化された住宅が求められるようになります。
このように、旧来の住宅が持つ課題が、新たな価値を持つ住宅の誕生を促す構図が見て取れます。
住宅購入を検討している読者、住宅業界関係者にとっての重要メッセージ
住宅購入を検討している方は、今後5年間で「高性能」「スマート」「柔軟性」「安全性」「健康」の5つの要素が住宅の標準となることを認識し、これらの要素を満たす住宅を選ぶことが、長期的な資産価値の維持と快適な生活に繋がるでしょう。特に、省エネ性能や災害対策は、光熱費や保険料にも直結するため、初期投資を惜しまない視点が重要です。
住宅業界関係者にとっては、旧来の常識にとらわれず、社会の変化と技術の進化に合わせた住宅の企画・設計・供給が不可欠となります。既存住宅の価値向上も重要なビジネスチャンスとなるでしょう。
AI予測をあなたのビジネスにどう活かしますか?
本記事で提示したAI予測を元に、貴社の今後の事業戦略について具体的なアイデアは浮かびましたでしょうか?AIが示す未来の住宅トレンドは、単なる予測に留まらず、具体的なビジネスチャンスへと繋がる羅針盤です。
ここでは、住宅販売事業者の皆様がこのAI予測を最大限に活用し、2030年に向けた競争優位性を確立するための具体的なアクションプランを提案します。
1. 自社の商品・サービスの再評価とアップデート
AIが共通して予測した「スマートホーム・AI統合型住宅」「ZEH・サステナブル住宅」「防災・レジリエンス重視住宅」は、今後住宅市場の標準となる可能性が高いです。
- 既存商品の見直し:
- 現在提供している住宅がこれらのトレンドに対応できているかを確認しましょう。断熱性能の低い住宅や固定的な間取りの住宅は、淘汰されるトレンドとして挙げられています。これらを早急に改善する計画が必要です。
- 新商品・サービスの開発:
- AIが予測するトレンドを参考に、新たな商品ラインナップやサービスを企画しましょう。例えば、AIが予測する「ライフスタイル対応の可変型住空間」に対応した、間取り変更が容易な住宅プランの開発や、スマートホーム機能を標準搭載した住宅パッケージの提供などが考えられます。
- リノベーション事業の強化:
- Geminiが指摘したように、既存住宅の活用とリノベーションの重要性が高まっています。高断熱化リノベーション、スマートホーム化改修、災害対策リノベーションなど、既存顧客へのアップセルや新たな顧客層の開拓に繋がる可能性があります。
2. マーケティング・営業戦略の最適化
AIの予測は、顧客が何を求めているのか、何に価値を感じなくなるのかを示唆しています。
- 顧客ターゲットの見直し:
単身世帯や多様な家族構成が増加し、画一的なファミリー向け間取りの需要が減少すると予測されています。ターゲット顧客層を再定義し、それぞれのニーズに合わせたメッセージングを強化しましょう。 - 訴求ポイントの明確化:
「高性能」「スマート」「柔軟性」「安全性」「健康」といったキーワードを軸に、住宅の価値を再構築し、顧客への訴求ポイントを明確にしましょう。特に、光熱費の高騰や災害リスクへの意識の高まりは、省エネ性能や災害対策の重要性を顧客に理解してもらう絶好の機会です。 - デジタルマーケティングの強化:
AIが予測するデジタルツインやデータ活用型住宅の登場は、顧客の住宅選びにおける情報収集の変化を示唆しています。VR/ARを活用したバーチャル内見、パーソナライズされた住宅提案システムなど、デジタル技術を駆使した顧客体験の向上を図りましょう。

3. パートナーシップの検討
自社だけでは対応しきれないトレンドに対しては、外部パートナーとの連携が有効です。
- テクノロジー企業との提携:
- スマートホーム機器メーカー、AIソリューション提供企業などと連携し、最新技術を住宅にスムーズに統合できる体制を構築しましょう
- 環境・エネルギー関連企業との連携:
- ZEHやサステナブル住宅の需要増加に対応するため、太陽光発電、蓄電池、断熱材メーカーなどとの協力関係を深め、最新の省エネ技術を取り入れましょう
- 地域コミュニティとの連携:
- 郊外・地方移住やコミュニティ志向の住まいがトレンドとなる可能性も指摘されています。地域に根差したNPOや地方自治体との連携を通じて、新たな住宅地の開発やコミュニティ形成に貢献することも視野に入れましょう
AIの予測は、未来を完全に言い当てるものではありませんが、その傾向と背景を理解し、自社の事業戦略に落とし込むことで、5年後の市場において優位なポジションを築くことができるでしょう。ぜひ、本記事をきっかけに、貴社のビジネスにおける「次のステップ」を具体的に描き始めてください。
まとめ
本記事では、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claudeの4つのAIモデルが予測する「2030年の住まい」を徹底的に比較分析しました。共通のプロンプトで質問することで、AIたちが導き出した未来の住宅像は、社会・ライフスタイルの変化、経済状況、技術進化、政策、災害リスクといった複合的な要因によって形作られることが明らかになりました。
「スマートホーム・AI統合型住宅」「ZEH・サステナブル住宅」「防災・レジリエンス重視住宅」は、今後の住宅市場の主流となる確度の高いトレンドです。これらは、遠隔操作、省エネ、災害時の自立性といった現代社会のニーズに深く根差しています。一方で、断熱性能の低い住宅や固定的な間取りの住宅、スマートホーム未対応の住宅は市場から淘汰されるでしょう。
AI予測は、住宅販売事業者の皆様にとって、ビジネスチャンスを発見し、リスクを回避するための強力な羅針盤となります。自社の商品・サービスを「高性能」「スマート」「柔軟性」「安全性」「健康」といった未来の価値観に合わせて再評価し、マーケティング戦略を最適化することが不可欠です。また、テクノロジー企業や環境関連企業、地域コミュニティとの連携も、変化に対応し競争優位性を確立するための重要な鍵となります。
AIの予測はあくまでデータに基づく推測であり、不確実な要素は含まれますが、未来への準備を進める上で非常に有効な示唆を与えてくれます。本記事が、2030年の住宅市場をリードするための一助となれば幸いです。
【免責事項】
- 本記事に掲載されているAIによる予測は、提供された情報源に基づいたものであり、未来の動向を保証するものではありません。予期せぬ社会情勢の変化、技術革新、新たな政策導入などにより、予測と異なる結果となる可能性があります。
- 各AIは、公開されているWebサイト、ニュース記事、統計データ、研究論文など、膨大なインターネット上の情報を学習し、予測を生成しています。
┃いえーる 住宅研究所から最新情報をお届けします。
最新情報を一早くチェックしたい方は下記「登場する」からご登録ください。
最新情報を一早くチェックしたい方は下記「登場する」からご登録ください。