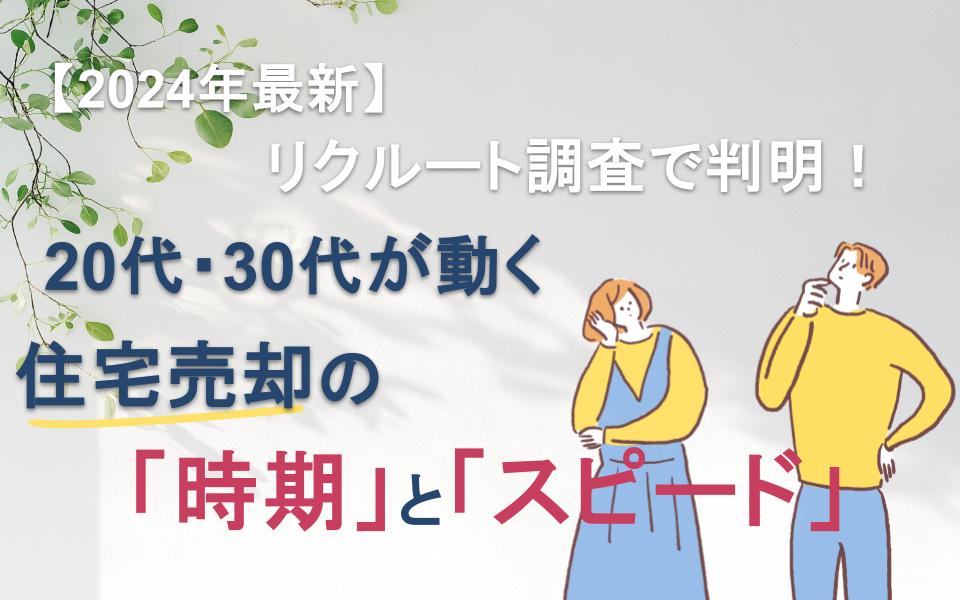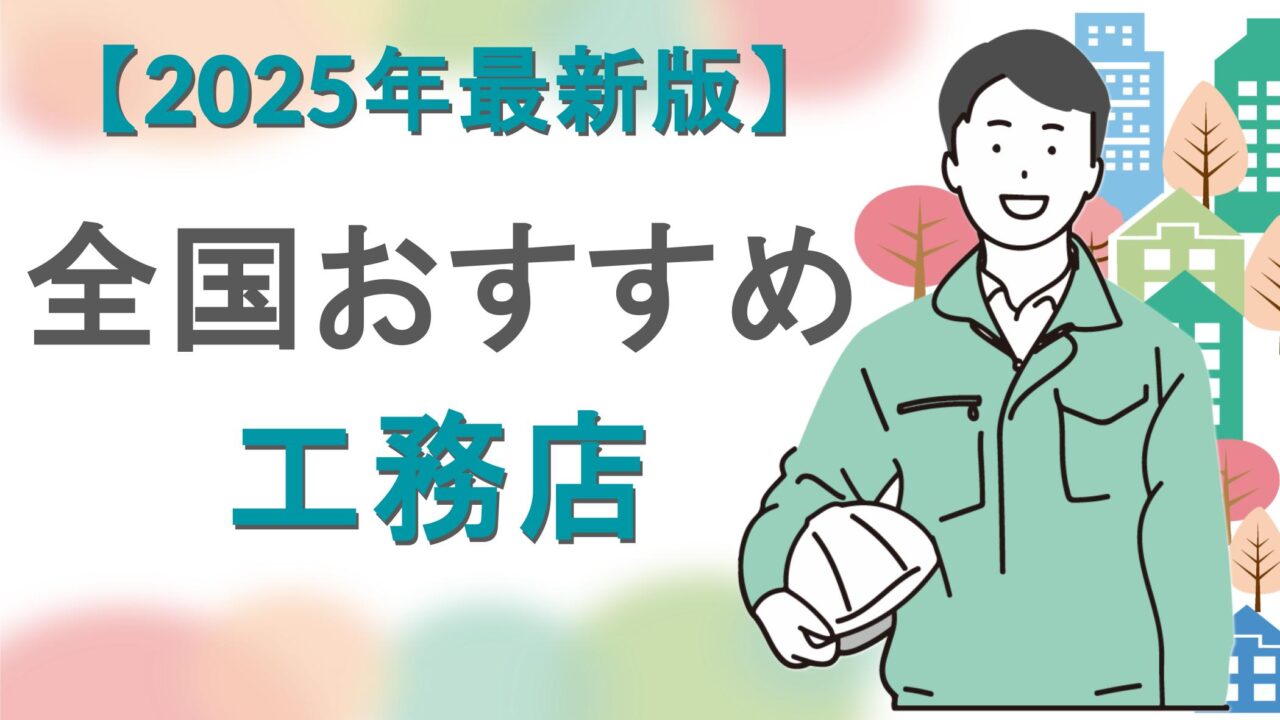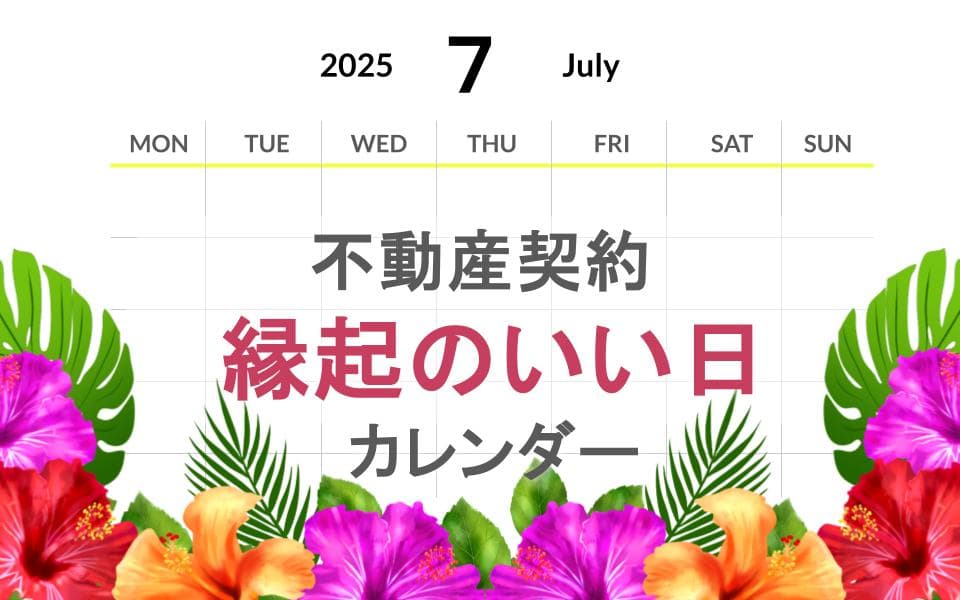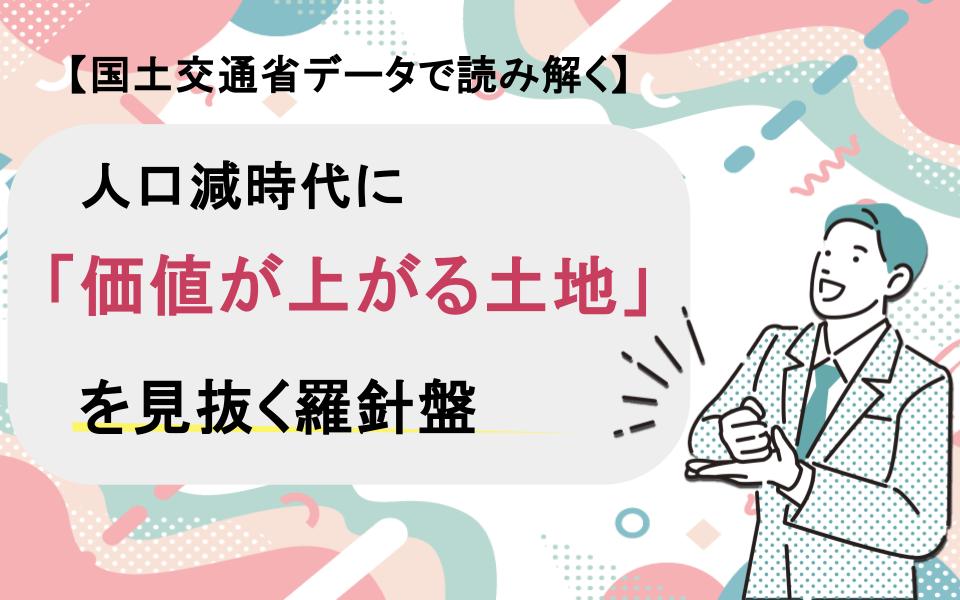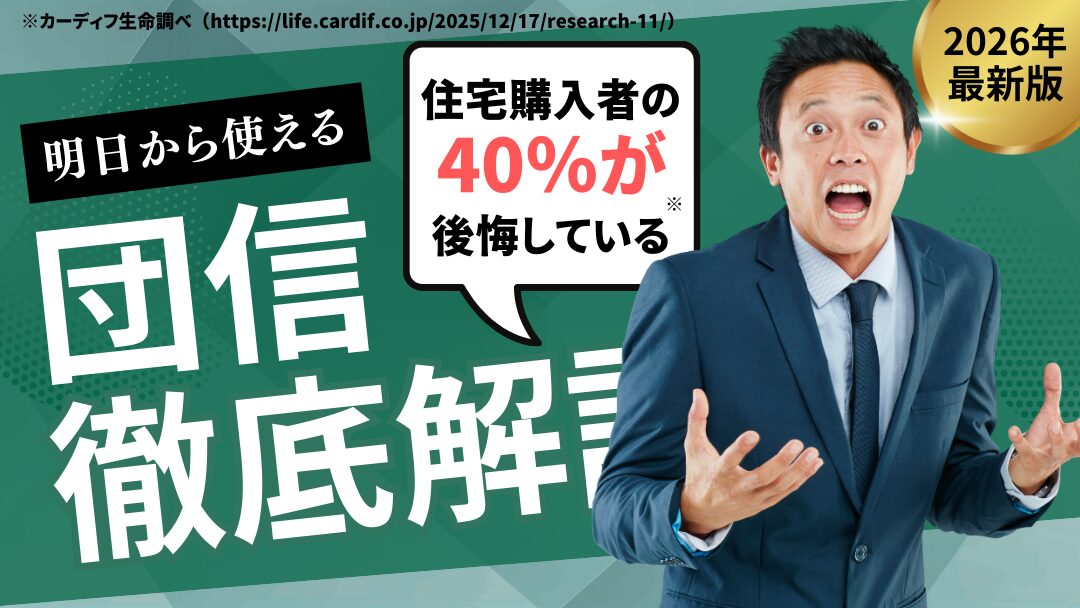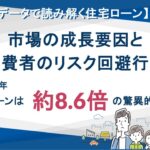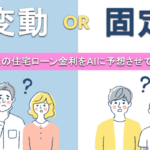たった15分で差をつける!間違えやすい「不動産鑑定評価」完全マスター講座
投稿日 : 2025年07月26日
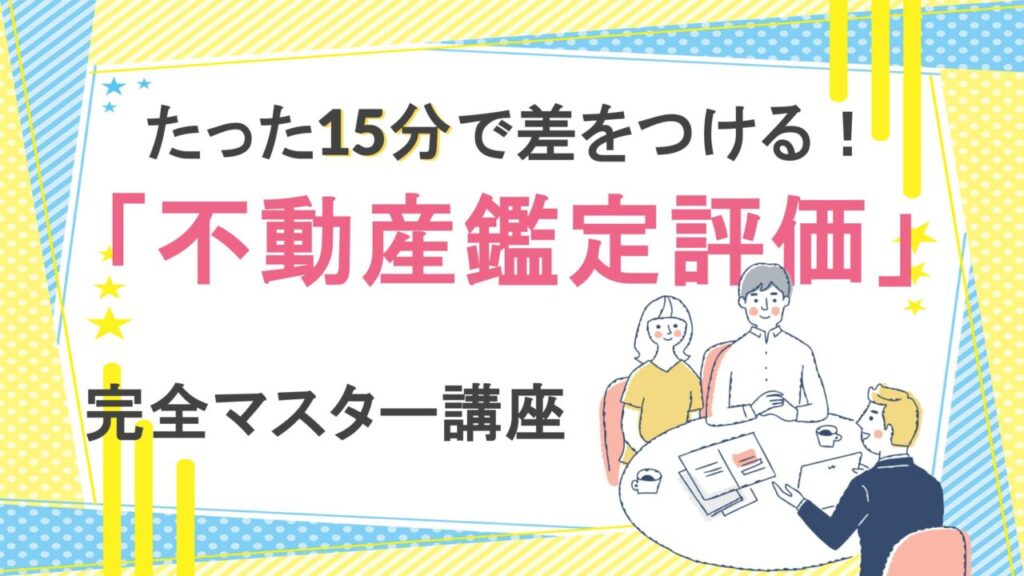
「不動産鑑定評価基準」は、不動産の適正な価格を判断するために重要な知識であり、宅建試験でも頻繁に出題される分野です。この鑑定評価の理解は、試験対策だけでなく、お客様への適切な価格説明や市場動向の把握といった日々の実務にも役立ちます。
この記事では、不動産の価格が持つ「三面性」と、それを評価する「三手法」について、宅建試験合格と実務への活用という視点から分かりやすく解説します。
Table of Contents
鑑定評価の基本
鑑定評価とは?(定義、必要性、役割)
不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士が不動産の適正な経済価値を判断し、価格または賃料を決定する手続きのことです。
その主な目的は、関係者全員が納得できる客観的な価格を導き出すことにあります。
不動産鑑定評価は、以下のような多岐にわたる場面で必要とされます。
- 不動産の取引
- 担保評価
- 企業の資産評価
不動産価格の「三面性」
不動産の価格は、単一の要素ではなく、様々な要因の相互作用によって形成されます。これらの要因は、「原価性」「市場性」「収益性」の三つの側面から捉えることができます。
三面性の全体像(原価性、市場性、収益性)
価格の三面性とは、不動産の経済価値を以下の3つの視点から捉える考え方です。
- コスト(原価性)
- 市場での取引(市場性)
- 将来生み出す利益(収益性)

原価性(コスト視点)
原価性とは、不動産を新たに取得したり、作り直したりするのにかかる費用に着目する側面です。その中心となるのが再調達原価です。
再調達原価
価格時点において、対象不動産を再調達するために必要とされる適正な原価の総額を指します。例えば、土地を造成し直す費用や建物を再築する費用などがこれにあたります。
市場性(市場動向視点)
市場性とは、不動産が市場でどれくらいの価格で取引されているか、その市場の需給関係に着目する側面です。不動産の効用(どのような使い方ができるか)、相対的稀少性(物件の少なさ)、そして有効需要(物件を欲しいと思う人の多さ)の三者が市場性を形成し、価格に影響を与えます。一般的に、供給が少ないのに需要が多い物件は価格が上がり、逆の場合は価格が下がります。
市場価値
市場で形成されるであろう適正な価格を示すものです。
収益性(将来利益視点)
収益性とは、不動産が将来生み出すと期待される利益に着目する側面です。特に投資用不動産において重要視されます。
純収益
不動産から生み出される総収益から、経費などを控除した純粋な利益を指します。
還元利回り
純収益を不動産価格に換算するために用いられる比率で、投資家が期待する収益率を反映します。
鑑定評価の「三手法」
不動産の鑑定評価では、価格の三面性(原価性、市場性、収益性)をそれぞれの視点から評価するため、主に以下の三つの手法が用いられます。原則として、複数の手法を併用することが適切とされています。
三手法の概要
- 原価法(コストアプローチ):
- 原価性に着目した手法
- 取引事例比較法(マーケットアプローチ):
- 市場性に着目した手法
- 収益還元法(インカムアプローチ):
- 収益性に着目した手法

原価法(コストアプローチ)
■定義
対象不動産を価格時点において再調達原価を求め、これに減価修正を行って試算価格(積算価格)を求める手法です。建物や最近造成された土地など、再調達原価を適切に求められる場合に適用可能です。
対象不動産を価格時点において再調達原価を求め、これに減価修正を行って試算価格(積算価格)を求める手法です。建物や最近造成された土地など、再調達原価を適切に求められる場合に適用可能です。
計算例
■建物の場合
再築費用2,000万円から、築年数経過や劣化(例: シロアリ被害)による価値の減少分(例: 500万円+100万円)を減価修正として差し引き、1,400万円といった積算価格を算出します。地域が発展して利便性が向上するような「熟成度」があれば、その分は加算されることがあります。
再築費用2,000万円から、築年数経過や劣化(例: シロアリ被害)による価値の減少分(例: 500万円+100万円)を減価修正として差し引き、1,400万円といった積算価格を算出します。地域が発展して利便性が向上するような「熟成度」があれば、その分は加算されることがあります。
〔積算価格の計算式〕
- 再築費用 − (築年数経過による価値減少分 + 劣化による価値減少分) + 熟成度による加算
〔計算式〕
2,000万円 − (500万円 + 100万円) = 1,400万円
2,000万円 − (500万円 + 100万円) = 1,400万円
■土地の場合
山林取得費(例: 50万円)と宅地造成工事費(例: 950万円)を加え、再調達原価1,000万円を算出します。ここから地域衰退などの減価修正(例: 100万円)を行って積算価格900万円を求めます。
山林取得費(例: 50万円)と宅地造成工事費(例: 950万円)を加え、再調達原価1,000万円を算出します。ここから地域衰退などの減価修正(例: 100万円)を行って積算価格900万円を求めます。
〔積算価格の計算式〕
- 山林取得費 + 宅地造成工事費 − 減価修正額
〔計算式〕
50万円 + 950万円 − 100万円 = 900万円
50万円 + 950万円 − 100万円 = 900万円
積算価格
原価法によって求められる試算価格を指します。
減価修正
建物の劣化や周辺環境の変化などにより、再調達原価から価値の減少分を差し引くことです。耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用します。
取引事例比較法(マーケットアプローチ)
■定義
多数の取引事例を収集し、適切な事例を選択。その取引価格に事情補正や時点修正を行い、さらに地域要因や個別的要因を比較して、試算価格(比準価格)を求める手法です。市場での取引が活発なエリアの不動産評価に有効
です。
多数の取引事例を収集し、適切な事例を選択。その取引価格に事情補正や時点修正を行い、さらに地域要因や個別的要因を比較して、試算価格(比準価格)を求める手法です。市場での取引が活発なエリアの不動産評価に有効
です。
計算例
対象不動産と類似する、または代替関係にある近隣地域や同一需給圏内の類似地域、代替競争不動産の取引事例が参考にされます。例えば、不整形地を整形地にするために隣接する土地を購入するケースなど、相対的に限定された市場での価格を示す限定価格の評価にも用いられる考え方です。
比準価格
取引事例比較法によって求められる試算価格を指します。
事情補正
特殊な事情(例: 親子間の売買、売り急ぎ・買い急ぎ)による価格への影響を分析し、正常な取引価格に修正することです。事情が判明し、補正可能であれば、特殊な事例も採用できます。
時点修正
取引事例の時点と鑑定評価の時点との間に価格水準の変動がある場合に、その変動を考慮して修正することです。
地域要因
特定の地域全体の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格に全般的な影響を与える要因です。(例: 宅地地域、農地地域)。
個別的要因
個々の不動産に個別的な価値を形成する要因です。(例: 土地の形状(整形地か不整形地か)、土壌汚染の有無、道路への接道状況など)
収益還元法(インカムアプローチ)
■定義
対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、試算価格(収益価格)を求める手法
です。
対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、試算価格(収益価格)を求める手法
です。
計算例
不動産が将来どれだけの収入(純収益)を生み出すかを予測し、それを現在の価値に換算して合計します。特に賃貸用不動産や事業用不動産の価格を求める場合に有効な手法です。自用の住宅であっても、賃貸を想定することで適用できる場合があります。ただし、学校や公園などの公共・公益の目的に供される不動産や、文化財など一般的に市場性のない不動産には適用すべきではありません。
収益価格
収益還元法によって求められる試算価格を指します。
直接還元法
1年間の純収益を還元利回りで直接還元して収益価格を求める方法です。
DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フローほう)
将来複数年にわたる純収益と、期間満了時の不動産価格(復帰価格)をそれぞれ適切な利回りで現在価値に割り引いて合計する方法です。
三面性と三手法の関係
各手法が重視する三面性
不動産鑑定評価の三手法は、不動産価格の三面性と密接に結びついています。
- 原価法:
- 不動産の「原価性」に着目し、再調達に必要な費用から価値を評価します。
- 取引事例比較法:
- 不動産の「市場性」に着目し、実際の取引事例から市場価格を評価します。
- 収益還元法:
- 不動産の「収益性」に着目し、将来の収益力から価値を評価します。
試算価格の調整(複数手法を用いる理由)
鑑定評価手法は、どれも万能ではありません。それぞれの評価手法には強みと限界があり、対象不動産の特性や市場状況によって、どの手法がより適切か、あるいはどの手法を重視すべきかが異なります。
そのため、鑑定評価では原則として、対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価手法を適用するべきとされています。複数の手法で得られた試算価格を比較検討し、最終的な鑑定評価額を決定することで、より客観的で妥当な価格を導き出すことが可能になります。
事例で学ぶ鑑定評価
事例1:新築マンションの評価
新築マンションの鑑定評価では、以下の手法が有効です。
- 原価法:
- 建設費用が明確なため、この手法が特に有効です。
- 取引事例比較法:
- 周辺の新築・築浅マンションの取引事例があれば適用できます。
- 収益還元法:
- 居住用マンションでは直接適用されにくいですが、賃貸を想定すればその考え方を援用することも可能です。
事例2:中古戸建ての評価
中古戸建ての鑑定評価では、以下の手法が主要となります。
- 取引事例比較法:
- 多数の取引事例が存在することが多いため、主要な評価手法です。
- 原価法:
- 築年数や劣化状況を考慮し、再調達原価から減価修正を行うことで併用し、価格の妥当性を検証します。
事例3:投資用アパートの評価
投資用アパートの鑑定評価では、以下の手法が重要視されます。
- 収益還元法:
- 家賃収入を目的とするため、最も有効な評価手法です。将来の賃料収入や経費を詳細に分析し、純収益から収益価格を算出します。
- 取引事例比較法:
- 近隣の類似アパートの取引事例があれば併用し、市場動向も考慮して多角的に評価します。
住宅販売実務での関連性
鑑定評価の知識は、住宅販売の現場でも大いに役立ちます。
■顧客への価格説明
お客様に不動産の価格を説明する際、単に「相場だから」と言うだけでなく、原価性(この物件が作られるのにこれだけのコストがかかっている)、市場性(周辺でこれくらいの価格で取引されている)、収益性(投資用ならこれくらいの賃料が見込める)といった鑑定評価の視点から説明することで、価格の背景にある合理性を伝え、お客様の理解と納得度を深めることができます。
お客様に不動産の価格を説明する際、単に「相場だから」と言うだけでなく、原価性(この物件が作られるのにこれだけのコストがかかっている)、市場性(周辺でこれくらいの価格で取引されている)、収益性(投資用ならこれくらいの賃料が見込める)といった鑑定評価の視点から説明することで、価格の背景にある合理性を伝え、お客様の理解と納得度を深めることができます。
■適正価格の把握と交渉
不動産取引において、提示された価格が適正であるかを判断する能力は非常に重要です。鑑定評価の三手法の考え方を理解していれば、自身で概算の適正価格を把握し、売主・買主双方との価格交渉において、根拠に基づいた説得力のある提案を行うことが可能になります。
不動産取引において、提示された価格が適正であるかを判断する能力は非常に重要です。鑑定評価の三手法の考え方を理解していれば、自身で概算の適正価格を把握し、売主・買主双方との価格交渉において、根拠に基づいた説得力のある提案を行うことが可能になります。
■融資・担保評価との関連
住宅ローンなどの融資では、金融機関が対象不動産を担保として評価します。この担保評価には、鑑定評価の考え方が用いられています。鑑定評価基準の知識があれば、融資の際に金融機関がどのような視点で物件を評価しているかを予測し、お客様へのアドバイスや事前準備に役立てることができます。
住宅ローンなどの融資では、金融機関が対象不動産を担保として評価します。この担保評価には、鑑定評価の考え方が用いられています。鑑定評価基準の知識があれば、融資の際に金融機関がどのような視点で物件を評価しているかを予測し、お客様へのアドバイスや事前準備に役立てることができます。

過去問にチャレンジ
令和5年(2023年)
■問題
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
■選択肢
- 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。
- 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
- 取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
- 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産が取引されている場合に有効である。
解説と解答のポイント
- 選択肢1(誤り)
- 原価法は再調達原価を求め、減価修正を行って積算価格を求める手法です。「収益価格」や「比準価格」は他の手法で求められます。
- 選択肢2(誤り)
- 原価法は、対象不動産が建物やその敷地である場合に適用できるほか、造成されたばかりの土地など、再調達原価を適切に求められる場合には土地にも適用することができます。
- 選択肢3(誤り)
- 取引事例比較法において、特殊事情のある事例であっても、その事情が具体的に判明し、適切に事情補正できるものであれば採用することは可能です。
- 選択肢4(正しい)
- 取引事例比較法は、原則として近隣地域や同一需給圏内の類似地域に存する不動産、または同一需給圏内の代替競争不動産の取引事例が豊富にある場合に有効な手法です。
まとめ
不動産の鑑定評価は、不動産の価格が「原価性」「市場性」「収益性」という三つの側面から形成されるという基本原則に基づいています。これを評価するために、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」という三つの手法が存在し、それぞれが異なる側面に焦点を当てています。
宅建試験では、これらの鑑定評価の定義や適用範囲、各用語の意味が問われることが多く、正確な理解が合格への鍵となります。また、住宅販売実務においては、これらの知識がお客様への説得力ある説明や、適切な価格設定、交渉力の向上に直結します。ぜひ、今回の解説を参考に、鑑定評価の知識を深め、宅建試験合格と実務での成功につなげてください。