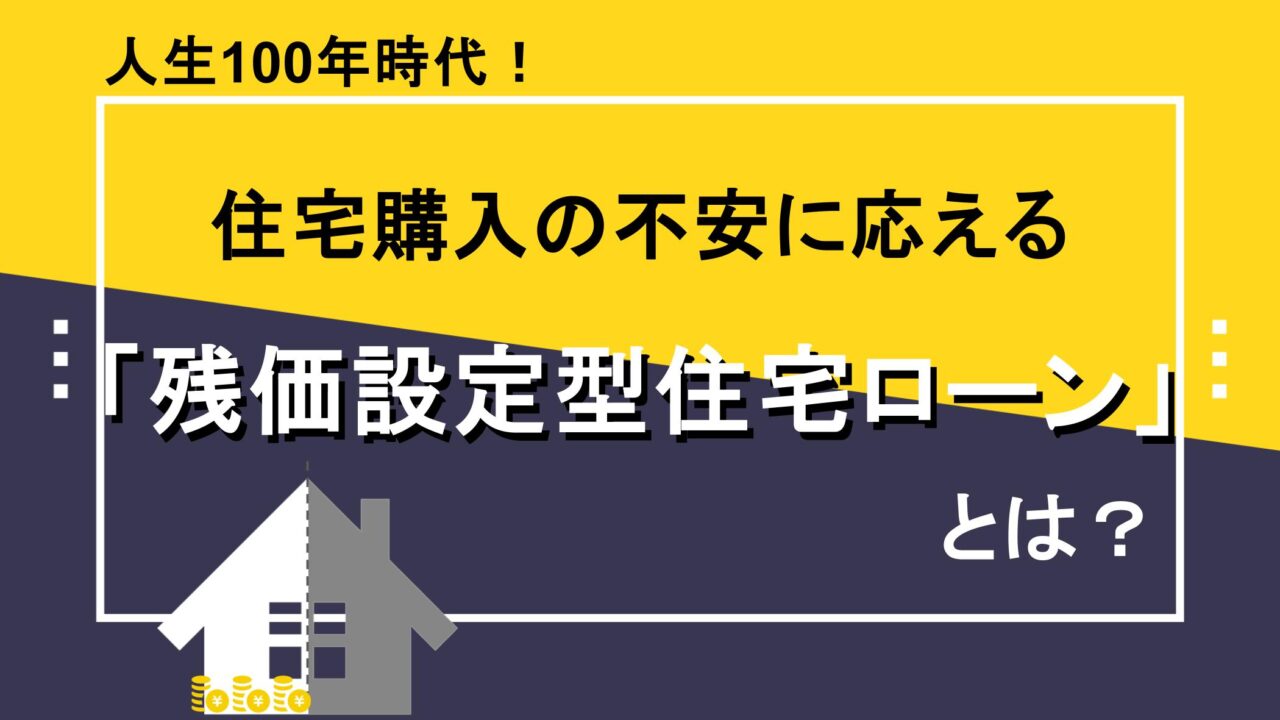【不動産IDの最新情報(2024年版)】基本のルールやメリット・デメリット、将来展望まで

各業界でDX推進に向けた取り組みが進む中、不動産業界においても新たなネットワークの整備が検討されています。
業界全体のDX推進のために期待されているのが「不動産ID」です。ここでは、不動産IDの仕組みや業界への影響など最新情報をふまえて解説します。
Table of Contents
不動産IDとは
不動産IDとは、土地や建物に付与される共通コードです。コードは17桁で構成され、前半13桁は不動産登記簿上の不動産番号、後半4桁は特定コードと呼ばれる符号で構成されます。
不動産ID(17桁)=不動産番号(13桁)+特定コード(4桁)
現状、日本の不動産には共通コードが存在しません。物件の住所と地番の表記が異なれば同一物件か否かを即座に判別できず、関連情報を収集する必要があります。
しかし、不動産の関連情報は、民間事業者や自治体が別々に保有しています。一つの物件情報について、複数の窓口で確認しなければなりません。
不動産業界全体で情報共有できていないため、各不動産会社が独自に時間をかけて情報を取得しているなど、非効率な物件の情報収集が業界全体の課題となっていました。
仮に、インフラの整備状況や修繕履歴を業界全体で共有できれば、業務効率化につながるのではないでしょうか。
そこで、検討されているのが「不動産ID」の整備です。不動産に共通コードを付与して、各事業者などが保有する情報と紐づけるという構想が検討されています。
不動産IDが整備されれば、業者間での連携が強まり、不動産の関連情報を容易に把握可能です。情報の活用が促進されることで、業界全体のDX推進の一翼を担うと期待されています。
不動産IDの条件やルール
不動産IDは全17桁の数字(またはアルファベット)で構成されるコードです。前半の13桁には、不動産登記簿上の不動産番号を採用します。
後半4桁の特定コードには、大きく2つのパターンがあります。
- 0000:不動産番号のみで物件を特定できる場合
- 4桁の符号:不動産番号のみでは物件を特定できない場合
例えば、土地の不動産番号は一筆ごとに付与される仕組みです。特定コードがなくても物件を特定できるため、不動産IDは「不動産番号(13桁)-0000」となります。
一方、賃貸アパートは、建物全体で1つの不動産番号が付与される仕組みです。しかし、実際の賃貸取引では建物全体ではなく、部屋ごとに入居者を募集するケースが多いでしょう。
このようなケースでは4桁の符号を付与します。賃貸アパート(居住用)の場合、不動産IDは「不動産番号(13桁)-部屋番号(4桁)」となります。
上記はほんの一例です。不動産IDのルールは下記のような建物の分類や用途別に定められています。
- 非区分建物or区分建物
- 商業用or居住用
不動産IDのメリット

不動産IDが整備されれば、共通コードとその不動産の関連情報が紐づき、利便性が高まります。
想定されるメリットについて、具体的に解説しましょう。
不動産物件の情報収集にかかる労力コストの大幅カット
不動産IDの恩恵を大きく受けられるのは、不動産事業者です。
不動産に共通コードがあれば、住所と地番の表記ゆれがあっても、同一物件であることを容易に把握できます。情報収集にかかる手間を大幅に削減できるでしょう。
重複掲載やおとり物件の排除
不動産IDの整備は、不動産ポータルサイト運営会社や消費者にとってもメリットがあります。
物件広告に不動産IDを記載することで、不動産ポータルサイトの運営側が管理しやすくなります。例えば、不動産IDで検索できれば、重複物件を一覧で表示可能です。成約済みなど、不要な広告を削除する際に役立つでしょう。
また、不動産IDが存在しない物件を一覧表示できれば、おとり物件の排除にもつながります。
同様に、消費者が不動産IDを確認できれば、類似の物件広告が同一物件であるかどうかを判別しやすくなります。
インフラ情報の取得と管理の容易さ
不動産IDは、電気・ガス・水道といったインフラの整備状況や取引価格の履歴など各種情報と紐づけて利便性を高めるものです。従来、各不動産会社が独自に収集していた情報を業界全体で共有できれば、各社の情報収集・管理の手間を省くことができます。
また、中長期の目線では、さらに幅広い活用が期待されています。例えば、都市計画情報やハザードマップと紐づけることで、エリアの調査負担も軽減可能です。
国土交通省が公表している「不動産IDルール検討会 中間取りまとめ」には、以下9つのメリットが記載されています。
- 自社データベース内や、自社データベースと外部から取得したデータの連携の際の、物件情報の名寄せ・紐付けの容易化
- 不動産情報サイトにおける、同一物件であることが分かりにくい形の重複掲載、おとり物件の排除
- 過去の取引時データの再利用による各種入力負担軽減
- 成約価格の推移の把握による価格査定の精度向上
- 住宅履歴情報との連携によるリフォーム履歴等の把握
- 電気・ガス・水道等の生活インフラ情報に関する、事業者間や自治体等との情報提供・交換の効率化および各種情報の統合管理
- (行政の保有するデータへの紐付けが行われた場合)行政保有情報の照会の容易化・効率化
- (最新の都市計画・ハザードマップ情報等がオープンデータ化され、公的図面として扱われるような環境が整備された場合) 都市計画情報・ハザードマップ等との連携による、調査負担の軽減や重要事項説明書の作成負担等の軽減
- 高精度のAI査定など、多様なエリア情報等のビッグデータの活用による新たな不動産関連サービスの創出
不動産IDのデメリットや注意点

新しい試みには、デメリットがつきものです。ここでは、事業者として知っておきたい不動産IDのデメリットや注意点について解説します。
情報漏えいのリスク
不動産IDは、それ自体が個人情報を有するものではありません。しかし、不動産IDに各種情報が紐付けられた状態でIDが公開されれば、個人の特定が容易になります。この場合、不動産IDを含む情報全体が個人情報に該当します。
不動産IDには、個人情報の漏洩リスクが潜んでいる点に注意が必要です。
ただし、住所や地番と同様に「不動産登記簿と照合すれば所有者を特定できる」という観点から、不動産IDは物件情報の一つとも考えられます。不動産IDの取り扱いについては、紐づけられている情報の性質や利用するシーンによってケースバイケースの判断が必要でしょう。
例えば、宅建業者のみが閲覧できるレインズとは異なり、消費者向けのポータルサイトは誰でも手軽に閲覧できます。当面は、消費者向けポータルサイトに不動産IDを表示しないということも選択肢の一つです。
個人情報保護法による規制と不動産IDの取り扱いに関する具体的な対応は、今後、整備されていくと考えられます。
活用促進に向けた各種整備などは道半ば
2022年3月、国土交通省が「不動産IDルールガイドライン」を公表しました。とはいえ、不動産IDの活用に向けた環境整備や、紐づいたデータの取り扱いについてなど、不透明な部分が多くあります。
例えば、不動産IDの整備には不動産IDと各種情報の紐づけが必要ですが、IDを入力する際は不動産登記簿を取得しなければなりません(不動産IDは不動産登記簿上の不動産番号が基礎となっているため)。不動産番号の取得を簡易化できるような仕組みが必要です。
不動産IDと情報の紐づけが進めば、活用の幅が広がります。ただし、実現に向けた課題が多数あるため、不動産IDの活用がどの程度、進むのかについては不透明です。
以下7つの項目は、国土交通省の「不動産IDルールガイドライン」で言及されている留意点です。
- 新築未登記の不動産にはIDを設けない
- 個人情報保護法による規制との関係について、ケースに応じた検討が必要
- 国が一元管理するものではなく、あくまでも各種情報を保有する主体間で広く普及させるものである
- 不動産IDの登録と公開は別の問題(不動産IDを登録したからといって、消費者向けポータルサイトなど外部への公開を強制されるものではない)
- 個人情報保護の観点から、元付業者が消費者向けポータルサイトで不動産IDを公開する場合など、状況に応じて売主から同意を得る必要がある
- 原則、誰でも自由に活用できるが、制度の信頼性が損なわれるような利用は認められない
- 不適切な利用が行われないよう、不動産IDに紐づく情報の連携・蓄積・活用には規約などを設ける必要がある
利用者間での共通認識が必要不可欠
不動産IDは誰でも利用できるものです。不動産事業者として、取引の際にIDや関連情報を入力する機会があるかもしれません。
その際に入力したデータはデータベースとして蓄積され、後の取引などで活用されます。入力者によって入力の基準や方法が異なれば、不動産IDの活用の妨げになるでしょう。
国土交通省の「不動産IDルールガイドライン」には、基本的なルールが記載されています。制度が本格的に開始する前に目を通しておくとよいでしょう。
不動産IDの今後は?

不動産IDのルールが公表されたのは、2022年3月のことです。
2023年前半に社会実装のためのモデル事業の公募が行われ、利活用に向けた取り組みが進められている段階です。今後は、モデル事業などで生じた課題をふまえつつ、本格始動に向けて整備が進むでしょう。
まとめ
不動産IDの整備が進めば、不動産事業者の業務効率化を期待できるだけでなく、社会全体でメリットを享受できる可能性があります。
不動産IDは各種情報と紐づけてデータベースを蓄積していく仕組みのため、利用者がルールを理解した上で正確に入力しなければなりません。
不動産事業者として取引時にデータを入力する可能性は高いため、この機会にガイドラインを確認してみてはいかがでしょうか。