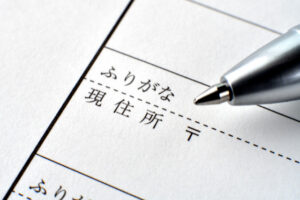不動産営業に興味がありつつも「自分に向いているのかわからない…」とお悩みではないでしょうか。 不動産営業と言っても複数の種類があるため、向き・不向きは勤め先によって大きく異なります。まずは不動産業界にはどのような仕事があ
( ⇒ 続きを読む )
「停止条件」と「解除条件」とは?|違いをわかりやすく徹底解説

宅建試験でもよく問われる不動産売買における「停止条件」と「解除条件」。混同しやすいこの2つの「条件」について詳しく解説します。
条件付き契約の法的効力
不動産売買の契約には、一定の条件を定めたものがあります。
この契約に定める条件は、契約の効力が発生する時期によって2種類に分類されます。1つは「停止条件」、もう1つは「解除条件」です。
- 停止条件…その条件を充たしたときに法的効力が「発生」する。
- 解除条件…その条件を充たしたときに法的効力が「消滅」する。
不動産業者でも混同している人がいるほど、この2つは紛らわしく、理解が難しい用語です。
しかし、この2つは全く異なる上に、当事者間でトラブルが発生した際に非常に大きな法的意味を帯びます。
売買契約の際には、取り扱う条件付き契約がどちらであるかを明確に区別する必要があるのです。
停止条件とは|わかりやすく解説
「停止条件」とは、その条件の成就が、ある法律行為に効力を生じさせる場合の、その条件のことを言います。
例えば、「宝くじが当たったら、プレゼントを買ってあげる」という契約をした場合、「宝くじが当たる」という条件が、プレゼント購入の「停止条件」となります。
つまり、「契約締結後、ある条件が整うまで法的効力の発生を停止させておくもの」という意味なのです。
停止条件付き売買契約
停止条件付き売買契約では、条件が成就したときに初めて、契約締結日までさかのぼって効力が発生します。
逆に言えば、売買契約を締結しても、停止条件が成就しない限りは、契約の法的効力は発生しないのです。
もし条件が成就できないことが確定したら、契約そのものが不成立となり、最初からなかったことになります。
上記の場合に損害が発生した場合でも、契約そのものがないので、損害賠償を請求することはできません。(ただし、故意による契約不成立はこの限りではありません)
◇「停止条件付き売買契約」の具体例
- 借地権付き土地売買契約…地主の承諾が停止条件となる。
- 任意売却…債権者の同意が停止条件となる。
解除条件とは|わかりやすく解説
「解除条件」とは、その条件の発生が、ある法律行為の効力を消滅させる、その条件のことを言います。
例えば、「ボーナスが下がったら、外食をやめる」という契約をした場合、「ボーナスが下がる」という条件が、外食の「解除条件」となります。
解除条件付き売買契約
解除条件付き売買契約では、一定の条件が発生した場合には、契約の効力が消滅し、契約解除となります。
当然、条件が発生しない限り契約は有効で、契約書に定める義務を履行しなければなりません。
また、契約解除の場合でも、それまでの契約は成立していたと見なされます。
そのため、停止条件と違い、契約締結時にさかのぼって無効になるわけではありません。
解除条件付き売買契約には、2パターンの定め方があります。
「解除条件型」と「解除留保型」です。
解除条件型
解除条件の発生で自動的に解除となる。
解除留保型
解除条件の発生で、解除する権利を得る。契約の続行を選ぶことも可能。
◇「解除条件付き売買契約」の具体例
- 融資利用特約…融資が不成立になった場合、解除することができる。
- 買い換え特約…元の自宅が売却できなかったら、新しい家の購入契約解除できる。
宅建試験の過去問題より例題
宅建試験の過去問題より「停止条件」に関する問題を見ていきましょう。
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (平成18年・問3)
- 「あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。」
- 「Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。」
- 「停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。」
- 「当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。」
解答は2です。条件が成就するのをAが故意に妨げているので、BはAに報酬を請求することができます。
(条件の成就の妨害等)第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
不動産営業実務マニュアルに興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本に興味がある方は下記の記事をご覧ください。
不動産業務実務の基本関連記事